2011年08月23日
消費税の費用計上事業年度はいつ?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
消費税の経理処理の方法で、
税込処理を採用している場合、
消費税を費用計上する必要があります。
消費税を費用計上する必要が
ナゼあるのか分からない方は
次を読んでください。
分かる方は次を飛ばしてくださいね。
***↓↓ここから説明↓↓***
スゴイ単純に説明しますと、
1個525円(税込)のりんごを仕入れました。
という場合、仕訳は
仕入高 525/現金 525
となります。
次にそのりんごを1,050円で売りました。
という場合、仕訳は
現金 1,050/売上高 1,050
となります。
では利益は??
1,050円(売上高)−525円(仕入高)=525円(利益)
このままだと、525円に対して法人税等がかかります。
さらに消費税が、50円−25円=25円かかります。
つまり消費税にも税金がかかります。
もしこれを『税抜処理』を行っていると、
仕入高 500 / 現金 525
仮払消費税 25 /
と、
現金 1,050 / 売上高 1,000
/ 仮受消費税 50
で、利益は、
1,000円(売上高)−500円(仕入高)=500円(利益)
消費税は、
50円(仮受消費税)−25円(仮払消費税)=25円(消費税)
となります。
この整合性を図るため、
税込処理を行っている場合、
消費税を費用計上して
1,050円(売上高)−525円(仕入高)−25円(消費税)
=500円(利益)
とします。
***↑↑ここまで説明↑↑***
では、この消費税ですが、いつの経費となるのでしょう??
これは法人税法基本通達に以下のように
定められています。
(租税の損金算入の時期)
法人税法基本通達9−5−1
法人が納付すべき国税及び地方税
(法人の各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されないものを除く。)については、
次に掲げる区分に応じ、
それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
(昭50年直法2−21「25」、昭55年直法2−15「十四」、
昭59年直法2−3「六」、平2年直法2−1「七」、
平5年課法2−1「八」、平15年課法2−7「二十六」により改正)
(1) 申告納税方式による租税
納税申告書に記載された税額については
当該納税申告書が提出された日の属する事業年度とし、
更正又は決定に係る税額については
当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。
つまり、消費税の申告書を提出した日の属する事業年度の
費用として処理することとされています。
ただし、決算においてその消費税額を未払金として
費用処理した時は、その費用処理をした日の属する
事業年度の費用として処理することも認められています。
**参考**
(消費税等の損金算入の時期)
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 7
法人税の課税所得金額の計算に当たり、
税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、
納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が
提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、
更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定が
あった日の属する事業年度の損金の額に算入する。
ただし、当該法人が申告期限未到来の
当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、
当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。
(平9年課法2-1により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

消費税の経理処理の方法で、
税込処理を採用している場合、
消費税を費用計上する必要があります。
消費税を費用計上する必要が
ナゼあるのか分からない方は
次を読んでください。
分かる方は次を飛ばしてくださいね。
***↓↓ここから説明↓↓***
スゴイ単純に説明しますと、
1個525円(税込)のりんごを仕入れました。
という場合、仕訳は
仕入高 525/現金 525
となります。
次にそのりんごを1,050円で売りました。
という場合、仕訳は
現金 1,050/売上高 1,050
となります。
では利益は??
1,050円(売上高)−525円(仕入高)=525円(利益)
このままだと、525円に対して法人税等がかかります。
さらに消費税が、50円−25円=25円かかります。
つまり消費税にも税金がかかります。
もしこれを『税抜処理』を行っていると、
仕入高 500 / 現金 525
仮払消費税 25 /
と、
現金 1,050 / 売上高 1,000
/ 仮受消費税 50
で、利益は、
1,000円(売上高)−500円(仕入高)=500円(利益)
消費税は、
50円(仮受消費税)−25円(仮払消費税)=25円(消費税)
となります。
この整合性を図るため、
税込処理を行っている場合、
消費税を費用計上して
1,050円(売上高)−525円(仕入高)−25円(消費税)
=500円(利益)
とします。
***↑↑ここまで説明↑↑***
では、この消費税ですが、いつの経費となるのでしょう??
これは法人税法基本通達に以下のように
定められています。
(租税の損金算入の時期)
法人税法基本通達9−5−1
法人が納付すべき国税及び地方税
(法人の各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されないものを除く。)については、
次に掲げる区分に応じ、
それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
(昭50年直法2−21「25」、昭55年直法2−15「十四」、
昭59年直法2−3「六」、平2年直法2−1「七」、
平5年課法2−1「八」、平15年課法2−7「二十六」により改正)
(1) 申告納税方式による租税
納税申告書に記載された税額については
当該納税申告書が提出された日の属する事業年度とし、
更正又は決定に係る税額については
当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。
つまり、消費税の申告書を提出した日の属する事業年度の
費用として処理することとされています。
ただし、決算においてその消費税額を未払金として
費用処理した時は、その費用処理をした日の属する
事業年度の費用として処理することも認められています。
**参考**
(消費税等の損金算入の時期)
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて 7
法人税の課税所得金額の計算に当たり、
税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、
納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が
提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、
更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定が
あった日の属する事業年度の損金の額に算入する。
ただし、当該法人が申告期限未到来の
当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、
当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。
(平9年課法2-1により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 20:39│Comments(0)
│知っていたら損しない税金豆知識
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。



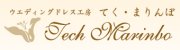


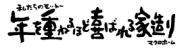




 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン





