2013年03月29日
父親に支払う地代家賃は事業所得の経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
生計を一にしている父親から
建物を借りて息子が個人で事業を
行っている場合に、父親に対して
家賃を支払った場合、
その支払った家賃は、
その息子の事業所得の金額の
計算上、必要経費とすることが
できるのでしょうか?
生計を一にする父親へ支払う
家賃は必要経費に算入することは
できません。
生計を一にする配偶者、その他の
親族に対して支払う地代等は
その事業所得の金額の計算上
必要経費に算入することは
できませんが、その建物に係る
固定資産税や減価償却費等に
ついては息子の事業所得の
金額の計算上必要経費に
算入することができます。
その一方で、父親については
その受取った地代やその建物に
かかる固定資産税や
減価償却費などの経費については
いずれもなかったものと
みなされます。
これは生計を一にする場合の
取り扱いとなりますので、
生計を一にしていない場合には
息子が支払った家賃は
事業所得の必要経費に算入され、
父親が受取った家賃については
不動産所得の総収入金額に、
固定資産税や減価償却費等に
ついてはその不動産所得の
必要経費にそれぞれ算入
されることになります。
**参考**
(事業から対価を受ける親族がある場合の
必要経費の特例)
所得税法第五十六条
居住者と生計を一にする配偶者
その他の親族がその居住者の営む
不動産所得、事業所得又は山林所得を
生ずべき事業に従事したこと
その他の事由により当該事業から
対価の支払を受ける場合には、
その対価に相当する金額は、
その居住者の当該事業に係る
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入しないものとし、
かつ、その親族のその対価に係る
各種所得の金額の計算上
必要経費に算入されるべき金額は、
その居住者の当該事業に係る
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。
この場合において、
その親族が支払を受けた対価の額
及びその親族のその対価に係る
各種所得の金額の計算上
必要経費に算入されるべき金額は、
当該各種所得の金額の計算上
ないものとみなす。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

生計を一にしている父親から
建物を借りて息子が個人で事業を
行っている場合に、父親に対して
家賃を支払った場合、
その支払った家賃は、
その息子の事業所得の金額の
計算上、必要経費とすることが
できるのでしょうか?
生計を一にする父親へ支払う
家賃は必要経費に算入することは
できません。
生計を一にする配偶者、その他の
親族に対して支払う地代等は
その事業所得の金額の計算上
必要経費に算入することは
できませんが、その建物に係る
固定資産税や減価償却費等に
ついては息子の事業所得の
金額の計算上必要経費に
算入することができます。
その一方で、父親については
その受取った地代やその建物に
かかる固定資産税や
減価償却費などの経費については
いずれもなかったものと
みなされます。
これは生計を一にする場合の
取り扱いとなりますので、
生計を一にしていない場合には
息子が支払った家賃は
事業所得の必要経費に算入され、
父親が受取った家賃については
不動産所得の総収入金額に、
固定資産税や減価償却費等に
ついてはその不動産所得の
必要経費にそれぞれ算入
されることになります。
**参考**
(事業から対価を受ける親族がある場合の
必要経費の特例)
所得税法第五十六条
居住者と生計を一にする配偶者
その他の親族がその居住者の営む
不動産所得、事業所得又は山林所得を
生ずべき事業に従事したこと
その他の事由により当該事業から
対価の支払を受ける場合には、
その対価に相当する金額は、
その居住者の当該事業に係る
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入しないものとし、
かつ、その親族のその対価に係る
各種所得の金額の計算上
必要経費に算入されるべき金額は、
その居住者の当該事業に係る
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額の計算上、
必要経費に算入する。
この場合において、
その親族が支払を受けた対価の額
及びその親族のその対価に係る
各種所得の金額の計算上
必要経費に算入されるべき金額は、
当該各種所得の金額の計算上
ないものとみなす。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月28日
失業保険を受取った場合所得税は課税される?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社を辞めた場合等において
支給を受けることが出来る
失業保険(失業保険という
言葉は行政上既に存在しない
らしいですが、ここでは
意味のわかりやすいように
するためにあえて使用します)。
その失業保険を受取った場合、
収入として所得税が課税される
のでしょうか?
それとも所得税の非課税と
なるのでしょうか?
失業保険は所得税の
非課税として取り扱われます。
そのため確定申告は
不要となります。
ただし、年の途中で会社を
辞めた場合、その会社では
年末調整をしてもらっていない
ため、給与から天引きされている
所得税がある場合、
確定申告をしなければ
返ってきませんので、
確定申告をした方が
得する場合がありますので、
注意して下さい。
**参考**
(公課の禁止)
雇用保険法第十二条
租税その他の公課は、
失業等給付として支給を受けた
金銭を標準として課することが
できない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

会社を辞めた場合等において
支給を受けることが出来る
失業保険(失業保険という
言葉は行政上既に存在しない
らしいですが、ここでは
意味のわかりやすいように
するためにあえて使用します)。
その失業保険を受取った場合、
収入として所得税が課税される
のでしょうか?
それとも所得税の非課税と
なるのでしょうか?
失業保険は所得税の
非課税として取り扱われます。
そのため確定申告は
不要となります。
ただし、年の途中で会社を
辞めた場合、その会社では
年末調整をしてもらっていない
ため、給与から天引きされている
所得税がある場合、
確定申告をしなければ
返ってきませんので、
確定申告をした方が
得する場合がありますので、
注意して下さい。
**参考**
(公課の禁止)
雇用保険法第十二条
租税その他の公課は、
失業等給付として支給を受けた
金銭を標準として課することが
できない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月27日
小規模企業共済制度を活用して節税を行う。
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
小規模企業共済制度については、
先日その取り扱いについて
説明しました。
今回はこの小規模企業共済制度を
活用した節税についてお伝えします。
まず小規模企業共済制度の掛金は
その支払をしても法人の必要経費、
事業所得の必要経費、
どちらにも該当しません。
小規模企業共済制度の掛金は
所得控除としてその支払った全額を
所得から差し引くこととなります。
まず法人の役員が活用する場合、
方法としては、小規模企業共済制度
の掛金と同額程度、役員報酬を
増額させます。
すると法人側では、支給する
役員報酬の増額分経費が増え、
利益の圧縮、つまり節税ができます。
そして役員報酬を受取る個人では
役員報酬の増額分、所得税が
増加しそうですが、
小規模企業共済制度の掛金は
支払った全額が所得控除として
所得金額から控除できるので、
増減0円となりそうですが、
実は給与所得控除額は
小規模企業共済制度の
掛金を控除する前の給与の
金額に応じて計算されるため、
給与所得控除額が僅かですが
大きくなります。
その結果、税額は加入前に
比べて僅かですが少なくなります。
さらに会社を辞めた場合など
一定の要件に該当した場合に
一括して支給を受ける金額は、
退職所得に該当しますので、
支給を受けた金額から、
退職所得控除額を控除し、
さらにその金額に1/2を
乗じた金額に対して
所得税が課税されます。
例えば、
支給を受けた金額が1,200万円
勤続年数が20年の場合、
退職所得控除額は、
40万円×20年=800万円
となりますので、
1,200円−800万円=400万円
400万円×1/2=200万円
となり、この200万円についてのみ
所得税の課税対象となります。
小規模企業共済制度を活用すると
このように節税を行うこともできます。
個人事業主の場合にも同様に、
毎年については、
事業所得で発生した利益から
結果的にはその支払った掛金を
控除することができますので、
その分所得税の節税を行えます。
そして事業を辞めた場合等、
一定の要件に該当した場合には
一括して支給を受ける金額は、
退職所得に該当しますので、
法人役員の場合と同様となります。
実際に小規模企業共済制度に
加入する際には、要件などにより
損をする可能性もありますので
よく検討をして加入してください。
**参考**
(小規模企業共済等掛金控除)
所得税法第七十五条
居住者が、各年において、
小規模企業共済等掛金を
支払つた場合には、
その支払つた金額を、
その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は
山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する
小規模企業共済等掛金とは、
次に掲げる掛金をいう。
一 小規模企業共済法
(昭和四十年法律第百二号)
第二条第二項 (定義)に
規定する共済契約
(政令で定めるものを除く。)に
基づく掛金
二 確定拠出年金法
(平成十三年法律第八十八号)
第三条第三項第七号の二
(規約の承認)に規定する
企業型年金加入者掛金又は
同法第五十五条第二項第四号
(規約の承認)に規定する
個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ
(年金等の非課税)に規定する
政令で定める共済制度に係る
契約に基づく掛金
3 第一項の規定による控除は、
小規模企業共済等掛金控除という。
小規模企業共済制度パンフレットはこちら
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

小規模企業共済制度については、
先日その取り扱いについて
説明しました。
今回はこの小規模企業共済制度を
活用した節税についてお伝えします。
まず小規模企業共済制度の掛金は
その支払をしても法人の必要経費、
事業所得の必要経費、
どちらにも該当しません。
小規模企業共済制度の掛金は
所得控除としてその支払った全額を
所得から差し引くこととなります。
まず法人の役員が活用する場合、
方法としては、小規模企業共済制度
の掛金と同額程度、役員報酬を
増額させます。
すると法人側では、支給する
役員報酬の増額分経費が増え、
利益の圧縮、つまり節税ができます。
そして役員報酬を受取る個人では
役員報酬の増額分、所得税が
増加しそうですが、
小規模企業共済制度の掛金は
支払った全額が所得控除として
所得金額から控除できるので、
増減0円となりそうですが、
実は給与所得控除額は
小規模企業共済制度の
掛金を控除する前の給与の
金額に応じて計算されるため、
給与所得控除額が僅かですが
大きくなります。
その結果、税額は加入前に
比べて僅かですが少なくなります。
さらに会社を辞めた場合など
一定の要件に該当した場合に
一括して支給を受ける金額は、
退職所得に該当しますので、
支給を受けた金額から、
退職所得控除額を控除し、
さらにその金額に1/2を
乗じた金額に対して
所得税が課税されます。
例えば、
支給を受けた金額が1,200万円
勤続年数が20年の場合、
退職所得控除額は、
40万円×20年=800万円
となりますので、
1,200円−800万円=400万円
400万円×1/2=200万円
となり、この200万円についてのみ
所得税の課税対象となります。
小規模企業共済制度を活用すると
このように節税を行うこともできます。
個人事業主の場合にも同様に、
毎年については、
事業所得で発生した利益から
結果的にはその支払った掛金を
控除することができますので、
その分所得税の節税を行えます。
そして事業を辞めた場合等、
一定の要件に該当した場合には
一括して支給を受ける金額は、
退職所得に該当しますので、
法人役員の場合と同様となります。
実際に小規模企業共済制度に
加入する際には、要件などにより
損をする可能性もありますので
よく検討をして加入してください。
**参考**
(小規模企業共済等掛金控除)
所得税法第七十五条
居住者が、各年において、
小規模企業共済等掛金を
支払つた場合には、
その支払つた金額を、
その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は
山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する
小規模企業共済等掛金とは、
次に掲げる掛金をいう。
一 小規模企業共済法
(昭和四十年法律第百二号)
第二条第二項 (定義)に
規定する共済契約
(政令で定めるものを除く。)に
基づく掛金
二 確定拠出年金法
(平成十三年法律第八十八号)
第三条第三項第七号の二
(規約の承認)に規定する
企業型年金加入者掛金又は
同法第五十五条第二項第四号
(規約の承認)に規定する
個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ
(年金等の非課税)に規定する
政令で定める共済制度に係る
契約に基づく掛金
3 第一項の規定による控除は、
小規模企業共済等掛金控除という。
小規模企業共済制度パンフレットはこちら
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月26日
小規模企業共済制度の掛金を支払った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
小規模企業共済制度は、
個人事業をやめられたとき、
会社等の役員を退職したとき、
個人事業の廃業などにより
共同経営者を退任したときなどの
生活資金等をあらかじめ
積み立てておくための
共済制度で、小規模企業共済法に
基づき、独立行政法人
中小企業基盤整備機構が
運営しています。
(中小機構HP参照)
この掛金を支払った場合、
法人の経費となるのでしょうか?
個人事業の経費となるのでしょうか?
それとも・・・
小規模企業共済制度の掛金を
支払った場合には、その掛金は
法人の経費でもなく、
個人事業の経費でもなく、
所得控除である、
小規模企業共済等掛金控除
として、その年中に支払った
掛金の全額を所得から
差し引くこととなります。
なお、小規模企業共済等
掛金控除の適用を受ける
ためには、支払った掛金の
控除証明書を確定申告書に
添付する必要がありますので
注意して下さい。
**参考**
(小規模企業共済等掛金控除)
所得税法第七十五条
居住者が、各年において、
小規模企業共済等掛金を
支払つた場合には、
その支払つた金額を、
その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は
山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する
小規模企業共済等掛金とは、
次に掲げる掛金をいう。
一 小規模企業共済法
(昭和四十年法律第百二号)
第二条第二項 (定義)に
規定する共済契約
(政令で定めるものを除く。)に
基づく掛金
二 確定拠出年金法
(平成十三年法律第八十八号)
第三条第三項第七号の二
(規約の承認)に規定する
企業型年金加入者掛金又は
同法第五十五条第二項第四号
(規約の承認)に規定する
個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ
(年金等の非課税)に規定する
政令で定める共済制度に係る
契約に基づく掛金
3 第一項の規定による控除は、
小規模企業共済等掛金控除という。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

小規模企業共済制度は、
個人事業をやめられたとき、
会社等の役員を退職したとき、
個人事業の廃業などにより
共同経営者を退任したときなどの
生活資金等をあらかじめ
積み立てておくための
共済制度で、小規模企業共済法に
基づき、独立行政法人
中小企業基盤整備機構が
運営しています。
(中小機構HP参照)
この掛金を支払った場合、
法人の経費となるのでしょうか?
個人事業の経費となるのでしょうか?
それとも・・・
小規模企業共済制度の掛金を
支払った場合には、その掛金は
法人の経費でもなく、
個人事業の経費でもなく、
所得控除である、
小規模企業共済等掛金控除
として、その年中に支払った
掛金の全額を所得から
差し引くこととなります。
なお、小規模企業共済等
掛金控除の適用を受ける
ためには、支払った掛金の
控除証明書を確定申告書に
添付する必要がありますので
注意して下さい。
**参考**
(小規模企業共済等掛金控除)
所得税法第七十五条
居住者が、各年において、
小規模企業共済等掛金を
支払つた場合には、
その支払つた金額を、
その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は
山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する
小規模企業共済等掛金とは、
次に掲げる掛金をいう。
一 小規模企業共済法
(昭和四十年法律第百二号)
第二条第二項 (定義)に
規定する共済契約
(政令で定めるものを除く。)に
基づく掛金
二 確定拠出年金法
(平成十三年法律第八十八号)
第三条第三項第七号の二
(規約の承認)に規定する
企業型年金加入者掛金又は
同法第五十五条第二項第四号
(規約の承認)に規定する
個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ
(年金等の非課税)に規定する
政令で定める共済制度に係る
契約に基づく掛金
3 第一項の規定による控除は、
小規模企業共済等掛金控除という。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月25日
スポーツクラブへ支払う年会費や利用料の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
従業員の健康のため、
福利厚生としてスポーツクラブに
会社が入会した場合の入会金の
取扱に関しては、
先日取り上げましたが、
その後に発生する年会費や
使用する際に発生する利用料等
の取扱はどのようになるのでしょう?
年会費や利用料については、
その利用の用途によって
以下のように取扱が異なります。
? 全ての従業員が使用できる
場合において、従業員が
利用した場合には、
その利用料は福利厚生費等
として取り扱われます。
? 従業員以外の事業関係者
に対して接待・慰安等の目的で
利用させた場合には、
その利用料は交際費等として
取り扱われます。
? その利用が役員や特定の
従業員のみの場合、
その役員、特定の従業員が
利用した場合の利用料は、
その者の給与等として
取り扱われます。
利用した者の給与等として
取り扱われる場合、
源泉徴収が必要になります
ので、注意して下さい。
**参考**
(レジャークラブの入会金)
法人税法基本通達9−7−13の2
9−7−11及び9−7−12の取扱いは、
法人がレジャークラブ(宿泊施設、
体育施設、遊技施設その他の
レジャー施設を会員に利用させることを
目的とするクラブでゴルフクラブ以外
のものをいう。以下9−7−14において
同じ。)に対して支出した入会金に
ついて準用する。
ただし、その会員としての有効期間が
定められており、かつ、その脱退に
際して入会金相当額の返還を
受けることができないものと
されているレジャークラブに
対して支出する入会金(役員又は
使用人に対する給与とされるものを
除く。)については、
繰延資産として償却することが
できるものとする。
(昭52年直法2−33「14」により追加)
(注) 年会費その他の費用は、
その使途に応じて交際費等又は
福利厚生費若しくは給与となることに
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

従業員の健康のため、
福利厚生としてスポーツクラブに
会社が入会した場合の入会金の
取扱に関しては、
先日取り上げましたが、
その後に発生する年会費や
使用する際に発生する利用料等
の取扱はどのようになるのでしょう?
年会費や利用料については、
その利用の用途によって
以下のように取扱が異なります。
? 全ての従業員が使用できる
場合において、従業員が
利用した場合には、
その利用料は福利厚生費等
として取り扱われます。
? 従業員以外の事業関係者
に対して接待・慰安等の目的で
利用させた場合には、
その利用料は交際費等として
取り扱われます。
? その利用が役員や特定の
従業員のみの場合、
その役員、特定の従業員が
利用した場合の利用料は、
その者の給与等として
取り扱われます。
利用した者の給与等として
取り扱われる場合、
源泉徴収が必要になります
ので、注意して下さい。
**参考**
(レジャークラブの入会金)
法人税法基本通達9−7−13の2
9−7−11及び9−7−12の取扱いは、
法人がレジャークラブ(宿泊施設、
体育施設、遊技施設その他の
レジャー施設を会員に利用させることを
目的とするクラブでゴルフクラブ以外
のものをいう。以下9−7−14において
同じ。)に対して支出した入会金に
ついて準用する。
ただし、その会員としての有効期間が
定められており、かつ、その脱退に
際して入会金相当額の返還を
受けることができないものと
されているレジャークラブに
対して支出する入会金(役員又は
使用人に対する給与とされるものを
除く。)については、
繰延資産として償却することが
できるものとする。
(昭52年直法2−33「14」により追加)
(注) 年会費その他の費用は、
その使途に応じて交際費等又は
福利厚生費若しくは給与となることに
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月22日
福利厚生目的でスポーツクラブに入会した場合の入会金の取扱い
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
従業員の健康のため、
福利厚生としてスポーツクラブに
会社が入会した場合、
そのスポーツクラブへの
入会金はその法人の経費として
処理することができるのでしょうか?
この場合、
以下のように取り扱うこととなります。
(1) 法人会員として入会する場合
入会金は資産として計上します。
ただし、名義人である特定の役員や
使用人が専ら個人的に利用する
ためのものであるときには、
その入会金に相当する金額は、
これら特定の役員や使用人の
給与として取り扱われます。
(2) 個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員
又は使用人に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度が
ないため個人会員として入会し、
その入会金を法人が資産に計上した
場合で、その入会金が法人の
負担すべきものであると
認められるときは、法人のものとして
処理することができます。
なお、この入会金が会員としての
有効期間が定められており、かつ、
脱退してもその入会金の返還を
受けることが出来ないもので
あるときは、繰延資産として
その有効期間を基礎として
償却を行うことができます。
ただし、有効期間が定められて
いない場合には、たとえ脱退を
してもその入会金の返還を
受けることが出来ないもの
であっても償却することは
できませんので、注意して下さい。
このように償却できないもの
については、脱退をした場合には
その脱退をした事業年度、
その会員としての権利を譲渡
した場合には、その譲渡をした
事業年度において損金として
処理することとなります。
**参考**
(ゴルフクラブの入会金)
法人税法基本通達9−7−11
法人がゴルフクラブに対して
支出した入会金については、
次に掲げる場合に応じ、
次による。
(昭49年直法2−71「15」、
昭55年直法2−15「十六」
により改正)
(1) 法人会員として入会する場合
入会金は資産として計上する
ものとする。ただし、
記名式の法人会員で名義人たる
特定の役員又は使用人が
専ら法人の業務に関係なく
利用するためこれらの者が
負担すべきものであると
認められるときは、
当該入会金に相当する金額は、
これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の
役員又は使用人に対する給与
とする。ただし、無記名式の
法人会員制度がないため
個人会員として入会し、
その入会金を法人が資産に
計上した場合において、
その入会が法人の業務の
遂行上必要であるため
法人の負担すべきもので
あると認められるときは、
その経理を認める。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに
入会するために支出する費用で
あるから、他人の有する会員権を
購入した場合には、
その購入代価のほか他人の
名義を変更するために
ゴルフクラブに支出する費用も
含まれる。
(資産に計上した入会金の処理)
法人税法基本通達9−7−12
法人が資産に計上した入会金に
ついては償却を認めないものと
するが、ゴルフクラブを脱退しても
その返還を受けることができない
場合における当該入会金に
相当する金額及びその会員たる
地位を他に譲渡したことにより
生じた当該入会金に係る
譲渡損失に相当する金額については、
その脱退をし、又は譲渡をした日の
属する事業年度の損金の額に
算入する。
(昭55年直法2−15「十六」、
平12年課法2−7「十七」、
平16年課法2−14「十二」により改正)
(注) 預託金制ゴルフクラブの
ゴルフ会員権については、
退会の届出、預託金の一部切捨て、
破産手続開始の決定等の事実に
基づき預託金返還請求権の
全部又は一部が顕在化した
場合において、当該顕在化した
部分については、金銭債権として
貸倒損失及び貸倒引当金の
対象とすることができることに
留意する。
(レジャークラブの入会金)
法人税法基本通達9−7−13の2
9−7−11及び9−7−12の取扱いは、
法人がレジャークラブ(宿泊施設、
体育施設、遊技施設その他の
レジャー施設を会員に利用させることを
目的とするクラブでゴルフクラブ以外
のものをいう。以下9−7−14において
同じ。)に対して支出した入会金に
ついて準用する。
ただし、その会員としての有効期間が
定められており、かつ、その脱退に
際して入会金相当額の返還を
受けることができないものと
されているレジャークラブに
対して支出する入会金(役員又は
使用人に対する給与とされるものを
除く。)については、
繰延資産として償却することが
できるものとする。
(昭52年直法2−33「14」により追加)
(注) 年会費その他の費用は、
その使途に応じて交際費等又は
福利厚生費若しくは給与となることに
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

従業員の健康のため、
福利厚生としてスポーツクラブに
会社が入会した場合、
そのスポーツクラブへの
入会金はその法人の経費として
処理することができるのでしょうか?
この場合、
以下のように取り扱うこととなります。
(1) 法人会員として入会する場合
入会金は資産として計上します。
ただし、名義人である特定の役員や
使用人が専ら個人的に利用する
ためのものであるときには、
その入会金に相当する金額は、
これら特定の役員や使用人の
給与として取り扱われます。
(2) 個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員
又は使用人に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度が
ないため個人会員として入会し、
その入会金を法人が資産に計上した
場合で、その入会金が法人の
負担すべきものであると
認められるときは、法人のものとして
処理することができます。
なお、この入会金が会員としての
有効期間が定められており、かつ、
脱退してもその入会金の返還を
受けることが出来ないもので
あるときは、繰延資産として
その有効期間を基礎として
償却を行うことができます。
ただし、有効期間が定められて
いない場合には、たとえ脱退を
してもその入会金の返還を
受けることが出来ないもの
であっても償却することは
できませんので、注意して下さい。
このように償却できないもの
については、脱退をした場合には
その脱退をした事業年度、
その会員としての権利を譲渡
した場合には、その譲渡をした
事業年度において損金として
処理することとなります。
**参考**
(ゴルフクラブの入会金)
法人税法基本通達9−7−11
法人がゴルフクラブに対して
支出した入会金については、
次に掲げる場合に応じ、
次による。
(昭49年直法2−71「15」、
昭55年直法2−15「十六」
により改正)
(1) 法人会員として入会する場合
入会金は資産として計上する
ものとする。ただし、
記名式の法人会員で名義人たる
特定の役員又は使用人が
専ら法人の業務に関係なく
利用するためこれらの者が
負担すべきものであると
認められるときは、
当該入会金に相当する金額は、
これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の
役員又は使用人に対する給与
とする。ただし、無記名式の
法人会員制度がないため
個人会員として入会し、
その入会金を法人が資産に
計上した場合において、
その入会が法人の業務の
遂行上必要であるため
法人の負担すべきもので
あると認められるときは、
その経理を認める。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに
入会するために支出する費用で
あるから、他人の有する会員権を
購入した場合には、
その購入代価のほか他人の
名義を変更するために
ゴルフクラブに支出する費用も
含まれる。
(資産に計上した入会金の処理)
法人税法基本通達9−7−12
法人が資産に計上した入会金に
ついては償却を認めないものと
するが、ゴルフクラブを脱退しても
その返還を受けることができない
場合における当該入会金に
相当する金額及びその会員たる
地位を他に譲渡したことにより
生じた当該入会金に係る
譲渡損失に相当する金額については、
その脱退をし、又は譲渡をした日の
属する事業年度の損金の額に
算入する。
(昭55年直法2−15「十六」、
平12年課法2−7「十七」、
平16年課法2−14「十二」により改正)
(注) 預託金制ゴルフクラブの
ゴルフ会員権については、
退会の届出、預託金の一部切捨て、
破産手続開始の決定等の事実に
基づき預託金返還請求権の
全部又は一部が顕在化した
場合において、当該顕在化した
部分については、金銭債権として
貸倒損失及び貸倒引当金の
対象とすることができることに
留意する。
(レジャークラブの入会金)
法人税法基本通達9−7−13の2
9−7−11及び9−7−12の取扱いは、
法人がレジャークラブ(宿泊施設、
体育施設、遊技施設その他の
レジャー施設を会員に利用させることを
目的とするクラブでゴルフクラブ以外
のものをいう。以下9−7−14において
同じ。)に対して支出した入会金に
ついて準用する。
ただし、その会員としての有効期間が
定められており、かつ、その脱退に
際して入会金相当額の返還を
受けることができないものと
されているレジャークラブに
対して支出する入会金(役員又は
使用人に対する給与とされるものを
除く。)については、
繰延資産として償却することが
できるものとする。
(昭52年直法2−33「14」により追加)
(注) 年会費その他の費用は、
その使途に応じて交際費等又は
福利厚生費若しくは給与となることに
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月21日
登記上の名義人と実際に事業を行っている者が異なる場合
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
登記上父親が名義人となっている
賃貸物件について、
父親は一切関与をしておらず、
実際には息子が賃貸業務を行い、
その賃料等を収受している場合、
その所得はやはり登記上の
名義人である父親に帰属し、
父親が所得税の申告を
行う必要があるのでしょうか?
それとも実質的な賃貸人で
ある息子が所得税の申告を
行う必要があるのでしょうか?
このように、登記上の名義人が
単なる名義人であって、
実際にその賃貸物件から生じる
収入を受け取っておらず、
その息子が実質的に
不動産賃貸業を行い、
そこから生ずる収入を
受取っている場合には、
息子が所得税の申告を
行うこととなります。
これは所得税法において
実質所得者課税の原則
が定められており、
資産から生ずる収益の
法律上の帰属者が
単なる名義人である場合、
その収益を実質的に
享受すると認められる者に
その所得が帰属するもの
とみなして所得税を
課税するという原則になります。
**参考**
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
所得税法基本通達12−1
法第12条の適用上、資産から生ずる
収益を享受する者がだれであるかは、
その収益の基因となる資産の
真実の権利者がだれであるかにより
判定すべきであるが、
それが明らかでない場合には、
その資産の名義者が真実の
権利者であるものと推定する。
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
所得税法基本通達12−2
事業から生ずる収益を享受する者が
だれであるかは、その事業を
経営していると認められる者
(以下12−5までにおいて「事業主」
という。)がだれであるかにより
判定するものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

登記上父親が名義人となっている
賃貸物件について、
父親は一切関与をしておらず、
実際には息子が賃貸業務を行い、
その賃料等を収受している場合、
その所得はやはり登記上の
名義人である父親に帰属し、
父親が所得税の申告を
行う必要があるのでしょうか?
それとも実質的な賃貸人で
ある息子が所得税の申告を
行う必要があるのでしょうか?
このように、登記上の名義人が
単なる名義人であって、
実際にその賃貸物件から生じる
収入を受け取っておらず、
その息子が実質的に
不動産賃貸業を行い、
そこから生ずる収入を
受取っている場合には、
息子が所得税の申告を
行うこととなります。
これは所得税法において
実質所得者課税の原則
が定められており、
資産から生ずる収益の
法律上の帰属者が
単なる名義人である場合、
その収益を実質的に
享受すると認められる者に
その所得が帰属するもの
とみなして所得税を
課税するという原則になります。
**参考**
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
所得税法基本通達12−1
法第12条の適用上、資産から生ずる
収益を享受する者がだれであるかは、
その収益の基因となる資産の
真実の権利者がだれであるかにより
判定すべきであるが、
それが明らかでない場合には、
その資産の名義者が真実の
権利者であるものと推定する。
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
所得税法基本通達12−2
事業から生ずる収益を享受する者が
だれであるかは、その事業を
経営していると認められる者
(以下12−5までにおいて「事業主」
という。)がだれであるかにより
判定するものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月19日
携帯電話の契約事務手数料の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
携帯電話を購入する際に、
契約事務手数料を支払いますが、
この契約事務手数料は
どのように取り扱われるのでしょう?
携帯電話の契約事務手数料は
原則、電気通信施設利用権に
該当し、無形固定資産となるため、
資産計上後、減価償却により
費用化となります。
ただし、その契約事務手数料の
金額が10万円未満である場合、
会社が経費として処理をすれば
事業の用に供した日の属する
事業年度の損金として
処理することができます。
**参考**
(減価償却資産の範囲)
法人税法施行令第十三条
法第二条第二十三号
(減価償却資産の意義)に規定する
政令で定める資産は、棚卸資産、
有価証券及び繰延資産以外の
資産のうち次に掲げるもの
(事業の用に供していないもの及び
時の経過によりその価値の
減少しないものを除く。)とする。
八 次に掲げる無形固定資産
ツ 電気通信施設利用権
(電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)
第九条第一号 (電気通信事業の
登録)に規定する電気通信回線
設備を設置する同法第二条第五号
(定義)に規定する電気通信事業者
に対して同条第四号 に規定する
電気通信事業の用に供する
同条第二号 に規定する
電気通信設備の設置に要する
費用を負担し、
その設備を利用して同条第三号
に規定する電気通信役務の
提供を受ける権利(電話加入権
及びこれに準ずる権利を除く。)
をいう。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

携帯電話を購入する際に、
契約事務手数料を支払いますが、
この契約事務手数料は
どのように取り扱われるのでしょう?
携帯電話の契約事務手数料は
原則、電気通信施設利用権に
該当し、無形固定資産となるため、
資産計上後、減価償却により
費用化となります。
ただし、その契約事務手数料の
金額が10万円未満である場合、
会社が経費として処理をすれば
事業の用に供した日の属する
事業年度の損金として
処理することができます。
**参考**
(減価償却資産の範囲)
法人税法施行令第十三条
法第二条第二十三号
(減価償却資産の意義)に規定する
政令で定める資産は、棚卸資産、
有価証券及び繰延資産以外の
資産のうち次に掲げるもの
(事業の用に供していないもの及び
時の経過によりその価値の
減少しないものを除く。)とする。
八 次に掲げる無形固定資産
ツ 電気通信施設利用権
(電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)
第九条第一号 (電気通信事業の
登録)に規定する電気通信回線
設備を設置する同法第二条第五号
(定義)に規定する電気通信事業者
に対して同条第四号 に規定する
電気通信事業の用に供する
同条第二号 に規定する
電気通信設備の設置に要する
費用を負担し、
その設備を利用して同条第三号
に規定する電気通信役務の
提供を受ける権利(電話加入権
及びこれに準ずる権利を除く。)
をいう。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月18日
生活費として取得した金銭で株の購入等をした場合
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
大学に入学することになった等の
理由により親から生活費等の
仕送りを受けた場合、
その生活費等の仕送りが
通常必要と認められる範囲の
ものであり、必要な都度行われる
贈与については、
贈与税の非課税として
取り扱われます。
このような場合において、
生活費として受けていた金銭で
使わなかった部分の金額で
株の購入を行った場合も
非課税として取り扱われる
のでしょうか?
上記の場合、その株の購入に
当てた部分については、
贈与税の課税対象となります。
これは株式の購入が通常の
日常生活に必要な生活費等に
該当しないためです。
また仕送りをされた生活費で
使用しなかった部分については
通常必要な生活費を超える部分
として贈与税の課税対象と
なる場合がありますので、
注意して下さい。
**参考**
(生活費及び教育費の取扱い)
相続税法基本通達21の3−5
法第21条の3第1項の規定により
生活費又は教育費に充てるための
ものとして贈与税の課税価格に
算入しない財産は、生活費又は
教育費として必要な都度直接
これらの用に充てるために
贈与によって取得した財産を
いうものとする。
したがって、生活費又は教育費の
名義で取得した財産を
預貯金した場合又は
株式の買入代金若しくは
家屋の買入代金に充当したような
場合における当該預貯金又は
買入代金等の金額は、
通常必要と認められるもの以外の
ものとして取り扱うものとする。
(平15課資2−1改正)
(生活費等で通常必要と認められるもの)
相続税法基本通達21の3−6
法第21条の3第1項第2号に規定する
「通常必要と認められるもの」は、
被扶養者の需要と扶養者の資力
その他一切の事情を勘案して
社会通念上適当と認められる範囲の
財産をいうものとする。
(平15課資2−1改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

大学に入学することになった等の
理由により親から生活費等の
仕送りを受けた場合、
その生活費等の仕送りが
通常必要と認められる範囲の
ものであり、必要な都度行われる
贈与については、
贈与税の非課税として
取り扱われます。
このような場合において、
生活費として受けていた金銭で
使わなかった部分の金額で
株の購入を行った場合も
非課税として取り扱われる
のでしょうか?
上記の場合、その株の購入に
当てた部分については、
贈与税の課税対象となります。
これは株式の購入が通常の
日常生活に必要な生活費等に
該当しないためです。
また仕送りをされた生活費で
使用しなかった部分については
通常必要な生活費を超える部分
として贈与税の課税対象と
なる場合がありますので、
注意して下さい。
**参考**
(生活費及び教育費の取扱い)
相続税法基本通達21の3−5
法第21条の3第1項の規定により
生活費又は教育費に充てるための
ものとして贈与税の課税価格に
算入しない財産は、生活費又は
教育費として必要な都度直接
これらの用に充てるために
贈与によって取得した財産を
いうものとする。
したがって、生活費又は教育費の
名義で取得した財産を
預貯金した場合又は
株式の買入代金若しくは
家屋の買入代金に充当したような
場合における当該預貯金又は
買入代金等の金額は、
通常必要と認められるもの以外の
ものとして取り扱うものとする。
(平15課資2−1改正)
(生活費等で通常必要と認められるもの)
相続税法基本通達21の3−6
法第21条の3第1項第2号に規定する
「通常必要と認められるもの」は、
被扶養者の需要と扶養者の資力
その他一切の事情を勘案して
社会通念上適当と認められる範囲の
財産をいうものとする。
(平15課資2−1改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月15日
成績優秀者を対象に旅行へ行った場合、源泉は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
例えば一定期間において営業成績が
優秀だった従業員を対象として
旅行に連れて行った場合、
この旅行の代金は経費として
計上できるのでしょうか?
特定の者のみを対象に行う旅行は
福利厚生費等の経費には該当せず、
その参加者に対する給与又は賞与に
該当することとなるので、
所得税の源泉が必要となります。
旅行が慰安として福利厚生費として
みなされるには、
その旅行が全従業員を対象に
行われるもの等の要件を
満たす必要があります。
そのため、成績優秀者のみに
限定するような旅行の場合、
福利厚生費等には該当せず、
その者の給与又は賞与として
所得税の源泉徴収の対象と
なりますので、注意して下さい。
**参考**
(課税しない経済的利益……
使用者が負担するレクリエーションの費用)
所得税法基本通達36−30
使用者が役員又は使用人の
レクリエーションのために
社会通念上一般的に行われていると
認められる会食、旅行、演芸会、
運動会等の行事の費用を
負担することにより、
これらの行事に参加した役員又は
使用人が受ける経済的利益に
ついては、使用者が、当該行事に
参加しなかった役員又は使用人
(使用者の業務の必要に基づき
参加できなかった者を除く。)に
対しその参加に代えて金銭を
支給する場合又は役員だけを
対象として当該行事の費用を
負担する場合を除き、
課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者
(使用者の業務の必要に基づき
参加できなかった者を含む。)に
支給する金銭については、
給与等として課税することに
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

例えば一定期間において営業成績が
優秀だった従業員を対象として
旅行に連れて行った場合、
この旅行の代金は経費として
計上できるのでしょうか?
特定の者のみを対象に行う旅行は
福利厚生費等の経費には該当せず、
その参加者に対する給与又は賞与に
該当することとなるので、
所得税の源泉が必要となります。
旅行が慰安として福利厚生費として
みなされるには、
その旅行が全従業員を対象に
行われるもの等の要件を
満たす必要があります。
そのため、成績優秀者のみに
限定するような旅行の場合、
福利厚生費等には該当せず、
その者の給与又は賞与として
所得税の源泉徴収の対象と
なりますので、注意して下さい。
**参考**
(課税しない経済的利益……
使用者が負担するレクリエーションの費用)
所得税法基本通達36−30
使用者が役員又は使用人の
レクリエーションのために
社会通念上一般的に行われていると
認められる会食、旅行、演芸会、
運動会等の行事の費用を
負担することにより、
これらの行事に参加した役員又は
使用人が受ける経済的利益に
ついては、使用者が、当該行事に
参加しなかった役員又は使用人
(使用者の業務の必要に基づき
参加できなかった者を除く。)に
対しその参加に代えて金銭を
支給する場合又は役員だけを
対象として当該行事の費用を
負担する場合を除き、
課税しなくて差し支えない。
(注)上記の行事に参加しなかった者
(使用者の業務の必要に基づき
参加できなかった者を含む。)に
支給する金銭については、
給与等として課税することに
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月14日
共働きの夫婦が住宅を購入する場合、贈与税がかかる場合がある?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
厚生労働省の統計によると
共働きの世帯数は、
1997(平成9)年以降は
片働き世帯を上回って
推移しているそうです。
今日はそんな共働きの夫婦が
住宅を購入する場合に注意
しなければ、贈与税を課される
可能性があるの事を紹介します。
贈与税が課税される可能性が
ある場合とは、その住宅の購入資金を
夫婦共同で負担する場合です。
夫婦共同で購入資金を負担すること
には問題はありませんが、
実際の購入資金の負担割合と
所有権登記の持分割合が異なる場合、
贈与税の問題が発生する事があります。
それはどういったことかと言うと、
例えば、総額5,000万円の住宅を購入し、
夫が3,500万円、妻が1,500万円の
資金負担をした場合に
それぞれが異なる金額を負担して
いるのにもかかわらず、
所有権の登記は夫と妻それぞれの
持分を2分の1ずつとした場合です。
この場合、妻の所有権は
登記持分の2分の1となりますので、
5,000万円の2分の1の2,500万円と
なります。
しかし、購入のための資金は
1,500万円しか負担していないため、
差額の1,000万円については
夫から妻へ贈与があったとみなされて
しまいます。
このように、資金の負担割合と
所有権の登記割合が異なると
贈与税が課税されてしまう
ということが起きる可能性が
ありますので、注意して下さい。
共同で購入資金を出し合う場合、
資金の負担割合に応じて
所有権登記を行えば、
贈与税の問題は生じません。
**参考**
相続税法第九条
第五条から前条まで及び次節に
規定する場合を除くほか、
対価を支払わないで、又は
著しく低い価額の対価で
利益を受けた場合においては、
当該利益を受けた時において、
当該利益を受けた者が、
当該利益を受けた時における
当該利益の価額に相当する金額
(対価の支払があつた場合には、
その価額を控除した金額)を
当該利益を受けさせた者から
贈与(当該行為が遺言により
なされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該行為が、
当該利益を受ける者が資力を喪失して
債務を弁済することが困難である場合
において、その者の扶養義務者から
当該債務の弁済に充てるために
なされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により
取得したものとみなされた金額のうち
その債務を弁済することが
困難である部分の金額については、
この限りでない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

厚生労働省の統計によると
共働きの世帯数は、
1997(平成9)年以降は
片働き世帯を上回って
推移しているそうです。
今日はそんな共働きの夫婦が
住宅を購入する場合に注意
しなければ、贈与税を課される
可能性があるの事を紹介します。
贈与税が課税される可能性が
ある場合とは、その住宅の購入資金を
夫婦共同で負担する場合です。
夫婦共同で購入資金を負担すること
には問題はありませんが、
実際の購入資金の負担割合と
所有権登記の持分割合が異なる場合、
贈与税の問題が発生する事があります。
それはどういったことかと言うと、
例えば、総額5,000万円の住宅を購入し、
夫が3,500万円、妻が1,500万円の
資金負担をした場合に
それぞれが異なる金額を負担して
いるのにもかかわらず、
所有権の登記は夫と妻それぞれの
持分を2分の1ずつとした場合です。
この場合、妻の所有権は
登記持分の2分の1となりますので、
5,000万円の2分の1の2,500万円と
なります。
しかし、購入のための資金は
1,500万円しか負担していないため、
差額の1,000万円については
夫から妻へ贈与があったとみなされて
しまいます。
このように、資金の負担割合と
所有権の登記割合が異なると
贈与税が課税されてしまう
ということが起きる可能性が
ありますので、注意して下さい。
共同で購入資金を出し合う場合、
資金の負担割合に応じて
所有権登記を行えば、
贈与税の問題は生じません。
**参考**
相続税法第九条
第五条から前条まで及び次節に
規定する場合を除くほか、
対価を支払わないで、又は
著しく低い価額の対価で
利益を受けた場合においては、
当該利益を受けた時において、
当該利益を受けた者が、
当該利益を受けた時における
当該利益の価額に相当する金額
(対価の支払があつた場合には、
その価額を控除した金額)を
当該利益を受けさせた者から
贈与(当該行為が遺言により
なされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該行為が、
当該利益を受ける者が資力を喪失して
債務を弁済することが困難である場合
において、その者の扶養義務者から
当該債務の弁済に充てるために
なされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により
取得したものとみなされた金額のうち
その債務を弁済することが
困難である部分の金額については、
この限りでない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月13日
死亡保険金を受取った場合は相続税?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
生命保険は基本的に、
被保険者(保険の対象となっている者)
が亡くなった場合に、保険事故の発生
として死亡保険が支払われます。
では例えば、
父親が保険契約者(保険料の
支払を行う)で、被保険者は母、
保険金受取人が子であった場合、
母親の死亡により保険金を
受取った場合、
この保険金は相続税が
課税されるのでしょうか?
実はこの場合、その保険金は
相続税ではなく、贈与税が
課税されることとなります。
これは保険金を受取った子が
保険料を負担していた父親から
贈与により受けたとされるためです。
保険金の課税関係は、
その保険料を実質的に負担
していたのは誰かにより
課税関係が変わりますので
注意が必要となります。
例えば、
保険料の負担者=保険金受取人
の場合には、一時所得(年金
形式で受取る場合には雑所得)
として所得税が課税され、
保険料の負担者≠保険金受取人
の場合で、
保険料の負担者=被保険者
の場合には相続税
保険料の負担者≠保険金受取人
の場合で、
保険料の負担者≠被保険者
の場合には贈与税
と言うような取り扱いとなります。
**参考**
(贈与により取得したものとみなす場合)
相続税法第五条
生命保険契約の保険事故(傷害、
疾病その他これらに類する保険事故で
死亡を伴わないものを除く。)又は
損害保険契約の保険事故(偶然な
事故に基因する保険事故で死亡を
伴うものに限る。)が発生した場合において、
これらの契約に係る保険料の全部
又は一部が保険金受取人以外の
者によつて負担されたものであるときは、
これらの保険事故が発生した時において、
保険金受取人が、その取得した保険金
(当該損害保険契約の保険金については、
政令で定めるものに限る。)のうち
当該保険金受取人以外の者が
負担した保険料の金額の
これらの契約に係る保険料で
これらの保険事故が発生した時までに
払い込まれたものの全額に対する割合に
相当する部分を当該保険料を
負担した者から贈与により取得したものと
みなす。
2 前項の規定は、生命保険契約又は
損害保険契約(傷害を保険事故とする
損害保険契約で政令で定めるものに
限る。)について返還金その他
これに準ずるものの取得があつた
場合について準用する。
3 前二項の規定の適用については、
第一項(前項において準用する場合を
含む。)に規定する保険料を
負担した者の被相続人が
負担した保険料は、その者が負担した
保険料とみなす。
ただし、第三条第一項第三号の
規定により前二項に規定する
保険金受取人又は返還金
その他これに準ずるものの取得者が
当該被相続人から同号に掲げる
財産を相続又は遺贈により
取得したものとみなされた
場合においては、
当該被相続人が負担した
保険料については、この限りでない。
4 第一項の規定は、第三条第一項第一号
又は第二号の規定により第一項に
規定する保険金受取人が
同条第一項第一号に掲げる保険金
又は同項第二号に掲げる給与を
相続又は遺贈により取得したものと
みなされる場合においては、
当該保険金又は給与に相当する
部分については、適用しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

生命保険は基本的に、
被保険者(保険の対象となっている者)
が亡くなった場合に、保険事故の発生
として死亡保険が支払われます。
では例えば、
父親が保険契約者(保険料の
支払を行う)で、被保険者は母、
保険金受取人が子であった場合、
母親の死亡により保険金を
受取った場合、
この保険金は相続税が
課税されるのでしょうか?
実はこの場合、その保険金は
相続税ではなく、贈与税が
課税されることとなります。
これは保険金を受取った子が
保険料を負担していた父親から
贈与により受けたとされるためです。
保険金の課税関係は、
その保険料を実質的に負担
していたのは誰かにより
課税関係が変わりますので
注意が必要となります。
例えば、
保険料の負担者=保険金受取人
の場合には、一時所得(年金
形式で受取る場合には雑所得)
として所得税が課税され、
保険料の負担者≠保険金受取人
の場合で、
保険料の負担者=被保険者
の場合には相続税
保険料の負担者≠保険金受取人
の場合で、
保険料の負担者≠被保険者
の場合には贈与税
と言うような取り扱いとなります。
**参考**
(贈与により取得したものとみなす場合)
相続税法第五条
生命保険契約の保険事故(傷害、
疾病その他これらに類する保険事故で
死亡を伴わないものを除く。)又は
損害保険契約の保険事故(偶然な
事故に基因する保険事故で死亡を
伴うものに限る。)が発生した場合において、
これらの契約に係る保険料の全部
又は一部が保険金受取人以外の
者によつて負担されたものであるときは、
これらの保険事故が発生した時において、
保険金受取人が、その取得した保険金
(当該損害保険契約の保険金については、
政令で定めるものに限る。)のうち
当該保険金受取人以外の者が
負担した保険料の金額の
これらの契約に係る保険料で
これらの保険事故が発生した時までに
払い込まれたものの全額に対する割合に
相当する部分を当該保険料を
負担した者から贈与により取得したものと
みなす。
2 前項の規定は、生命保険契約又は
損害保険契約(傷害を保険事故とする
損害保険契約で政令で定めるものに
限る。)について返還金その他
これに準ずるものの取得があつた
場合について準用する。
3 前二項の規定の適用については、
第一項(前項において準用する場合を
含む。)に規定する保険料を
負担した者の被相続人が
負担した保険料は、その者が負担した
保険料とみなす。
ただし、第三条第一項第三号の
規定により前二項に規定する
保険金受取人又は返還金
その他これに準ずるものの取得者が
当該被相続人から同号に掲げる
財産を相続又は遺贈により
取得したものとみなされた
場合においては、
当該被相続人が負担した
保険料については、この限りでない。
4 第一項の規定は、第三条第一項第一号
又は第二号の規定により第一項に
規定する保険金受取人が
同条第一項第一号に掲げる保険金
又は同項第二号に掲げる給与を
相続又は遺贈により取得したものと
みなされる場合においては、
当該保険金又は給与に相当する
部分については、適用しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月12日
給与以外の収入がある場合でも確定申告が不要となる場合とは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
1箇所からの給与所得のみの
サラリーマンの場合で、
年間の給与の金額が2,000万円以下
の場合には、原則年末調整により
所得税の課税関係が終了するため
確定申告が不要となります。
ではもしこの他に収入があれば
必ず確定申告しなければ
ならないのでしょうか?
1箇所からの給与の支払を
受けるサラリーマンで、
年間の給与所得の金額が
2,000万円以下の場合、
給与所得の金額と
退職所得の金額の以外の
収入が20万円以下の場合には
確定申告をする必要がありません。
そのため、
例えばネットオークションにより
商品等の販売を行っていても
その年間の収入金額が
20万円以下の場合には
確定申告は必要になりませんので
注意して下さい。
**参考**
(確定所得申告を要しない場合)
所得税法第百二十一条
その年において給与所得を有する
居住者で、その年中に支払を
受けるべき第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等
(以下この項において「給与等」という。)
の金額が二千万円以下であるものは、
次の各号のいずれかに該当する
場合には、前条第一項の規定に
かかわらず、その年分の
課税総所得金額及び課税山林所得金額に
係る所得税については、
同項の規定による申告書を
提出することを要しない。
ただし、不動産その他の資産を
その給与所得に係る給与等の支払者の
事業の用に供することによりその対価の
支払を受ける場合その他の政令で
定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の
支払を受け、かつ、当該給与等の
全部について第百八十三条
(給与所得に係る源泉徴収義務)
又は第百九十条(年末調整)の
規定による所得税の徴収をされた
又はされるべき場合において、
その年分の利子所得の金額、
配当所得の金額、不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額、一時所得の金額
及び雑所得の金額の合計額
(以下この項において「給与所得及び
退職所得以外の所得金額」という。)が
二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等
の支払を受け、かつ、当該給与等の
全部について第百八十三条又は
第百九十条の規定による所得税の
徴収をされた又はされるべき場合に
おいて、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与
についての扶養控除等申告書)に
規定する従たる給与等の支払者
から支払を受けるその年分の
給与所得に係る給与等の金額と
その年分の給与所得及び
退職所得以外の所得金額との
合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、
その年分の給与所得に係る給与等の
金額が百五十万円と社会保険料控除
の額、小規模企業共済等掛金控除
の額、生命保険料控除の額、
地震保険料控除の額、障害者控除
の額、寡婦(寡夫)控除の額、
勤労学生控除の額、配偶者控除の額、
配偶者特別控除の額及び扶養控除
の額との合計額以下で、かつ、
その年分の給与所得及び
退職所得以外の所得金額が
二十万円以下であるとき。
2 その年において退職所得を有する
居住者は、次の各号のいずれかに
該当する場合には、前条第一項の
規定にかかわらず、その年分の
課税退職所得金額に係る所得税
については、同項の規定による
申告書を提出することを要しない。
一 その年分の退職所得に係る
第三十条第一項(退職所得)に
規定する退職手当等
(以下この項において
「退職手当等」という。)の全部
について第百九十九条
(退職所得に係る源泉徴収義務)
及び第二百一条第一項
(退職所得に係る源泉徴収税額)
の規定による所得税の徴収を
された又はされるべき場合
二 前号に該当する場合を除き、
その年分の課税退職所得金額に
つき第八十九条(税率)の規定を
適用して計算した所得税の額が
その年分の退職所得に係る
退職手当等につき源泉徴収を
された又はされるべき所得税の額
以下である場合
3 その年において第三十五条第三項
(雑所得)に規定する公的年金等
(以下この条において「公的年金等」
という。)に係る雑所得を有する居住者で、
その年中の公的年金等の収入金額が
四百万円以下であるものが、
その年分の公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額(利子所得の
金額、配当所得の金額、
不動産所得の金額、事業所得の金額、
給与所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額、一時所得の金額
及び公的年金等に係る雑所得以外の
雑所得の金額の合計額をいう。)が
二十万円以下であるときは、
前条第一項の規定にかかわらず、
その年分の課税総所得金額又は
課税山林所得金額に係る所得税
については、同項の規定による
申告書を提出することを要しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

1箇所からの給与所得のみの
サラリーマンの場合で、
年間の給与の金額が2,000万円以下
の場合には、原則年末調整により
所得税の課税関係が終了するため
確定申告が不要となります。
ではもしこの他に収入があれば
必ず確定申告しなければ
ならないのでしょうか?
1箇所からの給与の支払を
受けるサラリーマンで、
年間の給与所得の金額が
2,000万円以下の場合、
給与所得の金額と
退職所得の金額の以外の
収入が20万円以下の場合には
確定申告をする必要がありません。
そのため、
例えばネットオークションにより
商品等の販売を行っていても
その年間の収入金額が
20万円以下の場合には
確定申告は必要になりませんので
注意して下さい。
**参考**
(確定所得申告を要しない場合)
所得税法第百二十一条
その年において給与所得を有する
居住者で、その年中に支払を
受けるべき第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等
(以下この項において「給与等」という。)
の金額が二千万円以下であるものは、
次の各号のいずれかに該当する
場合には、前条第一項の規定に
かかわらず、その年分の
課税総所得金額及び課税山林所得金額に
係る所得税については、
同項の規定による申告書を
提出することを要しない。
ただし、不動産その他の資産を
その給与所得に係る給与等の支払者の
事業の用に供することによりその対価の
支払を受ける場合その他の政令で
定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の
支払を受け、かつ、当該給与等の
全部について第百八十三条
(給与所得に係る源泉徴収義務)
又は第百九十条(年末調整)の
規定による所得税の徴収をされた
又はされるべき場合において、
その年分の利子所得の金額、
配当所得の金額、不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額、一時所得の金額
及び雑所得の金額の合計額
(以下この項において「給与所得及び
退職所得以外の所得金額」という。)が
二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等
の支払を受け、かつ、当該給与等の
全部について第百八十三条又は
第百九十条の規定による所得税の
徴収をされた又はされるべき場合に
おいて、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与
についての扶養控除等申告書)に
規定する従たる給与等の支払者
から支払を受けるその年分の
給与所得に係る給与等の金額と
その年分の給与所得及び
退職所得以外の所得金額との
合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、
その年分の給与所得に係る給与等の
金額が百五十万円と社会保険料控除
の額、小規模企業共済等掛金控除
の額、生命保険料控除の額、
地震保険料控除の額、障害者控除
の額、寡婦(寡夫)控除の額、
勤労学生控除の額、配偶者控除の額、
配偶者特別控除の額及び扶養控除
の額との合計額以下で、かつ、
その年分の給与所得及び
退職所得以外の所得金額が
二十万円以下であるとき。
2 その年において退職所得を有する
居住者は、次の各号のいずれかに
該当する場合には、前条第一項の
規定にかかわらず、その年分の
課税退職所得金額に係る所得税
については、同項の規定による
申告書を提出することを要しない。
一 その年分の退職所得に係る
第三十条第一項(退職所得)に
規定する退職手当等
(以下この項において
「退職手当等」という。)の全部
について第百九十九条
(退職所得に係る源泉徴収義務)
及び第二百一条第一項
(退職所得に係る源泉徴収税額)
の規定による所得税の徴収を
された又はされるべき場合
二 前号に該当する場合を除き、
その年分の課税退職所得金額に
つき第八十九条(税率)の規定を
適用して計算した所得税の額が
その年分の退職所得に係る
退職手当等につき源泉徴収を
された又はされるべき所得税の額
以下である場合
3 その年において第三十五条第三項
(雑所得)に規定する公的年金等
(以下この条において「公的年金等」
という。)に係る雑所得を有する居住者で、
その年中の公的年金等の収入金額が
四百万円以下であるものが、
その年分の公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額(利子所得の
金額、配当所得の金額、
不動産所得の金額、事業所得の金額、
給与所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額、一時所得の金額
及び公的年金等に係る雑所得以外の
雑所得の金額の合計額をいう。)が
二十万円以下であるときは、
前条第一項の規定にかかわらず、
その年分の課税総所得金額又は
課税山林所得金額に係る所得税
については、同項の規定による
申告書を提出することを要しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月11日
カード払いで行った寄付に係る寄付金控除はいつ?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
一定の先に個人が金銭等を寄付した場合、
所得税法の規定による寄付金控除の
適用を受けることができます。
ではこの寄付をカード払いで行った場合、
カードを使用した日が支払日と
なるのでしょうか?
それとも、カード会社から寄付先に
支払われた日が支払日となるのでしょうか?
それとも、カード会社から引き落としが
された日が支払日となるのでしょうか?
クレジットカードにより支払われる場合、
支払先からの領収書の日付は、
クレジットカード会社から支払を受けた日
となりますので、
寄付金控除は、その領収書の日付、
つまり、クレジットカード会社から
その寄付先に支払われた日となります。
年末付近に寄付をする場合、
その年で寄付金控除を受けられない
場合がありますので、
気を付けて下さい。
**参考**
(寄附金控除)
所得税法第七十八条
居住者が、各年において、
特定寄附金を支出した場合において、
第一号に掲げる金額が第二号に
掲げる金額を超えるときは、
その超える金額を、
その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から
控除する。
一 その年中に支出した特定寄附金の
額の合計額(当該合計額がその者
のその年分の総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の
合計額の百分の四十に相当する
金額を超える場合には、
当該百分の四十に相当する金額)
二 二千円
2 前項に規定する特定寄附金とは、
次に掲げる寄附金(学校の入学に関して
するものを除く。)をいう。
一 国又は地方公共団体(港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)の
規定による港務局を含む。)に対する
寄附金(その寄附をした者が
その寄附によつて設けられた設備を
専属的に利用することその他
特別の利益がその寄附をした者に
及ぶと認められるものを除く。)
二 公益社団法人、公益財団法人
その他公益を目的とする事業を
行う法人又は団体に対する寄附金
(当該法人の設立のためにされる
寄附金その他の当該法人の
設立前においてされる寄附金で
政令で定めるものを含む。)のうち、
次に掲げる要件を満たすと
認められるものとして政令で
定めるところにより財務大臣が
指定したもの
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に寄与するための
支出で緊急を要するものに
充てられることが確実であること。
三 別表第一に掲げる法人その他
特別の法律により設立された
法人のうち、教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に著しく寄与
するものとして政令で定めるものに
対する当該法人の主たる目的である
業務に関連する寄附金(前二号に
規定する寄附金に該当するものを
除く。)
3 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ
関スル法律第一条 (公益信託)に
規定する公益信託で信託の終了の時に
おける信託財産がその信託財産に係る
信託の委託者に帰属しないこと及び
その信託事務の実施につき政令で
定める要件を満たすものであることに
ついて政令で定めるところにより
証明がされたものをいう。)のうち、
その目的が教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に著しく
寄与するものとして政令で定めるものの
信託財産とするために支出した金銭は、
前項に規定する特定寄附金と
みなして第一項の規定を適用する。
4 第一項の規定による控除は、
寄附金控除という。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

一定の先に個人が金銭等を寄付した場合、
所得税法の規定による寄付金控除の
適用を受けることができます。
ではこの寄付をカード払いで行った場合、
カードを使用した日が支払日と
なるのでしょうか?
それとも、カード会社から寄付先に
支払われた日が支払日となるのでしょうか?
それとも、カード会社から引き落としが
された日が支払日となるのでしょうか?
クレジットカードにより支払われる場合、
支払先からの領収書の日付は、
クレジットカード会社から支払を受けた日
となりますので、
寄付金控除は、その領収書の日付、
つまり、クレジットカード会社から
その寄付先に支払われた日となります。
年末付近に寄付をする場合、
その年で寄付金控除を受けられない
場合がありますので、
気を付けて下さい。
**参考**
(寄附金控除)
所得税法第七十八条
居住者が、各年において、
特定寄附金を支出した場合において、
第一号に掲げる金額が第二号に
掲げる金額を超えるときは、
その超える金額を、
その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から
控除する。
一 その年中に支出した特定寄附金の
額の合計額(当該合計額がその者
のその年分の総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の
合計額の百分の四十に相当する
金額を超える場合には、
当該百分の四十に相当する金額)
二 二千円
2 前項に規定する特定寄附金とは、
次に掲げる寄附金(学校の入学に関して
するものを除く。)をいう。
一 国又は地方公共団体(港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)の
規定による港務局を含む。)に対する
寄附金(その寄附をした者が
その寄附によつて設けられた設備を
専属的に利用することその他
特別の利益がその寄附をした者に
及ぶと認められるものを除く。)
二 公益社団法人、公益財団法人
その他公益を目的とする事業を
行う法人又は団体に対する寄附金
(当該法人の設立のためにされる
寄附金その他の当該法人の
設立前においてされる寄附金で
政令で定めるものを含む。)のうち、
次に掲げる要件を満たすと
認められるものとして政令で
定めるところにより財務大臣が
指定したもの
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に寄与するための
支出で緊急を要するものに
充てられることが確実であること。
三 別表第一に掲げる法人その他
特別の法律により設立された
法人のうち、教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に著しく寄与
するものとして政令で定めるものに
対する当該法人の主たる目的である
業務に関連する寄附金(前二号に
規定する寄附金に該当するものを
除く。)
3 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ
関スル法律第一条 (公益信託)に
規定する公益信託で信託の終了の時に
おける信託財産がその信託財産に係る
信託の委託者に帰属しないこと及び
その信託事務の実施につき政令で
定める要件を満たすものであることに
ついて政令で定めるところにより
証明がされたものをいう。)のうち、
その目的が教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に著しく
寄与するものとして政令で定めるものの
信託財産とするために支出した金銭は、
前項に規定する特定寄附金と
みなして第一項の規定を適用する。
4 第一項の規定による控除は、
寄附金控除という。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月08日
融資を受けるために付加された生命保険の保険料は必要経費?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人で不動産の賃貸業を行っている場合
において新たに不動産の取得をするために
銀行から借入を行う際、生命保険に加入
することを付加されている場合のその
生命保険の保険料は、その不動産所得の
金額の計算上、必要経費に算入することが
できるのでしょうか?
この場合、その生命保険契約が、融資を
受けることを条件に締結したものであり、
その保険金の受取人がその銀行である
場合には、その生命保険契約に係る
保険料は、事業の遂行上必要なもの
として、不動産所得の金額の計算上
必要経費に算入することができます。
ただし、その保険金の受取人が
借入を行った本人であり、
その保険金に対して質権が
設定されているような場合、
その保険契約はあくまでもその者
個人のための生命保険契約であって、
銀行が質権を設定することにより
二次的に担保の提供を受けている
ということに過ぎないため、
不動産所得の必要経費ではなく、
生命保険料控除として
取り扱うこととなります。
**参考**
(必要経費)
所得税法第三十七条
その年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は雑所得の金額
(事業所得の金額及び雑所得の
金額のうち山林の伐採又は
譲渡に係るもの並びに雑所得の金額
のうち第三十五条第三項
(公的年金等の定義)に規定する
公的年金等に係るものを除く。)の
計算上必要経費に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
これらの所得の総収入金額に係る
売上原価その他当該総収入金額を
得るため直接に要した費用の額
及びその年における販売費、
一般管理費その他これらの所得を
生ずべき業務について生じた費用
(償却費以外の費用で
その年において債務の確定
しないものを除く。)の額とする。
(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)
所得税法基本通達37−27
業務を営んでいる者が当該業務の用に
供する資産(37−28において「業務の用
に供される資産」という。)の取得のために
借り入れた資金の利子は、
当該業務に係る各種所得の金額の
計算上必要経費に算入する。
ただし、当該資産の使用開始の日までの
期間に対応する部分の金額については、
当該資産の取得価額に算入することが
できる。
(昭52直所3−33、直法6−10、直資3−15改正)
(注) 不動産所得、事業所得、山林所得
又は雑所得を生ずべき業務を
開始する前に、当該業務の用に
供する資産を取得している場合の
当該資産の取得のために
借り入れた資金の利子のうち
当該業務を開始する前の
期間に対応するものは、
この項の適用はなく、「38−8」の
適用があることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

個人で不動産の賃貸業を行っている場合
において新たに不動産の取得をするために
銀行から借入を行う際、生命保険に加入
することを付加されている場合のその
生命保険の保険料は、その不動産所得の
金額の計算上、必要経費に算入することが
できるのでしょうか?
この場合、その生命保険契約が、融資を
受けることを条件に締結したものであり、
その保険金の受取人がその銀行である
場合には、その生命保険契約に係る
保険料は、事業の遂行上必要なもの
として、不動産所得の金額の計算上
必要経費に算入することができます。
ただし、その保険金の受取人が
借入を行った本人であり、
その保険金に対して質権が
設定されているような場合、
その保険契約はあくまでもその者
個人のための生命保険契約であって、
銀行が質権を設定することにより
二次的に担保の提供を受けている
ということに過ぎないため、
不動産所得の必要経費ではなく、
生命保険料控除として
取り扱うこととなります。
**参考**
(必要経費)
所得税法第三十七条
その年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は雑所得の金額
(事業所得の金額及び雑所得の
金額のうち山林の伐採又は
譲渡に係るもの並びに雑所得の金額
のうち第三十五条第三項
(公的年金等の定義)に規定する
公的年金等に係るものを除く。)の
計算上必要経費に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
これらの所得の総収入金額に係る
売上原価その他当該総収入金額を
得るため直接に要した費用の額
及びその年における販売費、
一般管理費その他これらの所得を
生ずべき業務について生じた費用
(償却費以外の費用で
その年において債務の確定
しないものを除く。)の額とする。
(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)
所得税法基本通達37−27
業務を営んでいる者が当該業務の用に
供する資産(37−28において「業務の用
に供される資産」という。)の取得のために
借り入れた資金の利子は、
当該業務に係る各種所得の金額の
計算上必要経費に算入する。
ただし、当該資産の使用開始の日までの
期間に対応する部分の金額については、
当該資産の取得価額に算入することが
できる。
(昭52直所3−33、直法6−10、直資3−15改正)
(注) 不動産所得、事業所得、山林所得
又は雑所得を生ずべき業務を
開始する前に、当該業務の用に
供する資産を取得している場合の
当該資産の取得のために
借り入れた資金の利子のうち
当該業務を開始する前の
期間に対応するものは、
この項の適用はなく、「38−8」の
適用があることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月07日
融資を受けて新たに不動産事業を開始した場合の利息の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
銀行から融資を受けてマンションを
建設し、新たに不動産賃貸業を
始めた場合、その借入にかかる利息は、
不動産所得の必要経費となる?
初めて業務を開始した者が、
事業開始前に支払うこととなる
借入金の利息は、その取得した
マンションの取得価額に算入されます。
借入金にかかる利息は、
その業務の用に供されることが
明らかである場合には、
事業遂行上必要なものとして
原則、必要経費に算入することが
できます。
また今まで業務を営んでいた者が
あらたにマンションを取得するために
行った借入に係る利息についても
原則、必要経費に算入することが
できます。
しかし新たに業務を開始する者で、
そのマンションの貸付業務を
開始するまでの期間に対応する
部分の利息は、業務を行っていない
期間の支出になります。
そのため原則必要経費に算入する
ことはできません。
が、マンションの購入のために支出
した費用として、マンションの
取得価額に算入され、業務開始後
減価償却により、費用化されること
となります。
なお貸付業務開始の日は、
そのマンションが完成し、
実際にそのマンションの賃貸に
ついて、募集広告など客観的に
業務開始と認められる日
となります。
**参考**
(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)
所得税法基本通達37−27
業務を営んでいる者が当該業務の用に
供する資産(37−28において
「業務の用に供される資産」という。)の
取得のために借り入れた資金の利子は、
当該業務に係る各種所得の金額の
計算上必要経費に算入する。
ただし、当該資産の使用開始の日
までの期間に対応する部分の金額
については、当該資産の取得価額に
算入することができる。
(昭52直所3−33、直法6−10、
直資3−15改正)
(注) 不動産所得、事業所得、
山林所得又は雑所得を生ずべき
業務を開始する前に、
当該業務の用に供する資産を
取得している場合の当該資産の
取得のために借り入れた資金の
利子のうち当該業務を開始する
前の期間に対応するものは、
この項の適用はなく、「38−8」の
適用があることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

銀行から融資を受けてマンションを
建設し、新たに不動産賃貸業を
始めた場合、その借入にかかる利息は、
不動産所得の必要経費となる?
初めて業務を開始した者が、
事業開始前に支払うこととなる
借入金の利息は、その取得した
マンションの取得価額に算入されます。
借入金にかかる利息は、
その業務の用に供されることが
明らかである場合には、
事業遂行上必要なものとして
原則、必要経費に算入することが
できます。
また今まで業務を営んでいた者が
あらたにマンションを取得するために
行った借入に係る利息についても
原則、必要経費に算入することが
できます。
しかし新たに業務を開始する者で、
そのマンションの貸付業務を
開始するまでの期間に対応する
部分の利息は、業務を行っていない
期間の支出になります。
そのため原則必要経費に算入する
ことはできません。
が、マンションの購入のために支出
した費用として、マンションの
取得価額に算入され、業務開始後
減価償却により、費用化されること
となります。
なお貸付業務開始の日は、
そのマンションが完成し、
実際にそのマンションの賃貸に
ついて、募集広告など客観的に
業務開始と認められる日
となります。
**参考**
(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)
所得税法基本通達37−27
業務を営んでいる者が当該業務の用に
供する資産(37−28において
「業務の用に供される資産」という。)の
取得のために借り入れた資金の利子は、
当該業務に係る各種所得の金額の
計算上必要経費に算入する。
ただし、当該資産の使用開始の日
までの期間に対応する部分の金額
については、当該資産の取得価額に
算入することができる。
(昭52直所3−33、直法6−10、
直資3−15改正)
(注) 不動産所得、事業所得、
山林所得又は雑所得を生ずべき
業務を開始する前に、
当該業務の用に供する資産を
取得している場合の当該資産の
取得のために借り入れた資金の
利子のうち当該業務を開始する
前の期間に対応するものは、
この項の適用はなく、「38−8」の
適用があることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月06日
事業的規模でない不動産所得と事業所得の青色申告特別控除
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
本業として事業を行っており
副業として不動産貸付を
行っている場合、
不動産所得は通常5棟10室
(物件として最低で5棟又は
10室を貸し付けている)
の要件を満たした場合に
事業的規模とされ、
それ以外は事業的規模と
されません。
そして青色申告特別控除のうち
65万円の控除に関しては、
『事業的規模』である
不動産所得又は事業所得を
営んでいる必要があります。
(事業所得は事業所得に
該当した時点で事業的規模
となります。)
では不動産は事業的規模以外
に該当し、事業所得もある場合には
どのような取り扱いとなるのでしょう?
不動産所得、事業所得共に、
65万円の青色申告特別控除の
適用を受けることが出来る次の要件
? 不動産所得又は事業所得に
係る取引を複式簿記により記帳し
? ?に基づいて作成した
貸借対照表及び損益計算書
を確定申告書に添付し
? 控除を受ける金額を確定申告書
に記載し、
? 法定申告期限内に提出した場合
これら全て満たしている場合には、
不動産所得についても65万円の
青色申告特別控除の適用を
受けることができますので、
不動産所得の金額、事業所得の金額
の合計額から65万円を控除することが
できます。
なお控除するのは、
不動産所得、事業所得の順番で
行い、それぞれの所得において
赤字となっている場合は、
その赤字はないものとして
計算することとなります。
つまり、
? 不動産所得 80万円
? 事業所得 △15万円
の場合、事業所得は赤字となり
控除する金額はありませんが
不動産所得から65万円を控除
することができますので、
? 不動産所得 15万円
(80万円−65万円)
? 事業所得 △15万円
となります。
なお、現金主義により帳簿の作成を
おこなうことを選択している場合には
65万円の青色申告特別控除は
受けることができませんので、
注意して下さい。
**参考**
(青色申告特別控除)
租税特別措置法第二十五条の二
青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人の
その承認を受けている年分(第三項の
規定の適用を受ける年分を除く。)の
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額は、
所得税法第二十六条第二項 、
第二十七条第二項又は
第三十二条第三項の規定により
計算した不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額
から次に掲げる金額のうちいずれか
低い金額を控除した金額とする。
一 十万円
二 所得税法第二十六条第二項 、
第二十七条第二項又は
第三十二条第三項の規定により
計算した不動産所得の金額、
事業所得の金額(次条第一項の
規定の適用がある場合には、
同項に規定する社会保険診療に
つき支払を受けるべき金額に
対応する部分の金額を除く。
第三項第二号において同じ。)又は
山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額から順次控除する。
3 青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人で
不動産所得又は事業所得を生ずべき
事業を営むもの(所得税法第六十七条
の規定の適用を受ける者を除く。)が、
同法第百四十八条第一項 の
規定により、当該事業につき
帳簿書類を備え付けてこれに
その承認を受けている年分の
不動産所得の金額又は
事業所得の金額に係る取引を
記録している場合(これらの所得の
金額に係る一切の取引の内容を
詳細に記録している場合として
財務省令で定める場合に限る。)
には、その年分の不動産所得の金額
又は事業所得の金額は、
同法第二十六条第二項 又は
第二十七条第二項 の規定により
計算した不動産所得の金額又は
事業所得の金額から次に掲げる
金額のうちいずれか低い金額を
控除した金額とする。
一 六十五万円
二 所得税法第二十六条第二項又は
第二十七条第二項 の規定により
計算した不動産所得の金額又は
事業所得の金額の合計額
4 前項の規定により控除すべき金額は、
不動産所得の金額又は事業所得の
金額から順次控除する。
5 第三項の規定は、確定申告書に
同項の規定の適用を受けようとする旨
及び同項の規定による控除を受ける
金額の計算に関する事項の記載並びに
同項に規定する帳簿書類に基づき
財務省令で定めるところにより作成された
貸借対照表、損益計算書その他
不動産所得の金額又は事業所得の金額の
計算に関する明細書の添付があり、かつ、
当該確定申告書をその提出期限までに
提出した場合に限り、適用する。
(青色申告特別控除額の計算等)
租税特別措置法通達25の2−1
措置法第25条の2第1項又は第3項の
規定による青色申告特別控除額の
計算等については、次の諸点に
留意する。(平5課所4−2追加)
(1) 措置法第25条の2第1項第2号に
規定する不動産所得の金額、
事業所得の金額及び山林所得の金額
又は同条第3項第2号に規定する
不動産所得の金額及び事業所得の
金額は、損益通算をする前の
いわゆる黒字の所得金額を
いうのであるから、
これらの所得の金額の計算上
生じた損失の金額がある場合には、
その損失の金額を除外した
ところにより同条第1項第2号又は
同条第3項第2号の合計額を
計算すること。
(2) 措置法第25条の2第1項の
規定による青色申告特別控除額は、
この控除をする前のいわゆる
黒字の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は
山林所得の金額から、
これらの黒字の金額を限度として
順次控除すること。
また、同条第3項の規定による
青色申告特別控除額は、
この控除をする前のいわゆる黒字の
不動産所得の金額又は事業所得の
金額から、これらの黒字の金額を
限度として順次控除すること。
(3) 措置法第26条第1項
((社会保険診療報酬の所得計算の特例))
の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に
係る所得がある場合には、
同法第25条の2第1項第2号又は
同条第3項第2号に規定する合計額を
計算するときはこれを除外したところに
よるのであるが、同条第2項又は
第4項の控除をするときには、
当該所得を含めた事業所得の金額から
控除すること。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

本業として事業を行っており
副業として不動産貸付を
行っている場合、
不動産所得は通常5棟10室
(物件として最低で5棟又は
10室を貸し付けている)
の要件を満たした場合に
事業的規模とされ、
それ以外は事業的規模と
されません。
そして青色申告特別控除のうち
65万円の控除に関しては、
『事業的規模』である
不動産所得又は事業所得を
営んでいる必要があります。
(事業所得は事業所得に
該当した時点で事業的規模
となります。)
では不動産は事業的規模以外
に該当し、事業所得もある場合には
どのような取り扱いとなるのでしょう?
不動産所得、事業所得共に、
65万円の青色申告特別控除の
適用を受けることが出来る次の要件
? 不動産所得又は事業所得に
係る取引を複式簿記により記帳し
? ?に基づいて作成した
貸借対照表及び損益計算書
を確定申告書に添付し
? 控除を受ける金額を確定申告書
に記載し、
? 法定申告期限内に提出した場合
これら全て満たしている場合には、
不動産所得についても65万円の
青色申告特別控除の適用を
受けることができますので、
不動産所得の金額、事業所得の金額
の合計額から65万円を控除することが
できます。
なお控除するのは、
不動産所得、事業所得の順番で
行い、それぞれの所得において
赤字となっている場合は、
その赤字はないものとして
計算することとなります。
つまり、
? 不動産所得 80万円
? 事業所得 △15万円
の場合、事業所得は赤字となり
控除する金額はありませんが
不動産所得から65万円を控除
することができますので、
? 不動産所得 15万円
(80万円−65万円)
? 事業所得 △15万円
となります。
なお、現金主義により帳簿の作成を
おこなうことを選択している場合には
65万円の青色申告特別控除は
受けることができませんので、
注意して下さい。
**参考**
(青色申告特別控除)
租税特別措置法第二十五条の二
青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人の
その承認を受けている年分(第三項の
規定の適用を受ける年分を除く。)の
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額は、
所得税法第二十六条第二項 、
第二十七条第二項又は
第三十二条第三項の規定により
計算した不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額
から次に掲げる金額のうちいずれか
低い金額を控除した金額とする。
一 十万円
二 所得税法第二十六条第二項 、
第二十七条第二項又は
第三十二条第三項の規定により
計算した不動産所得の金額、
事業所得の金額(次条第一項の
規定の適用がある場合には、
同項に規定する社会保険診療に
つき支払を受けるべき金額に
対応する部分の金額を除く。
第三項第二号において同じ。)又は
山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額から順次控除する。
3 青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人で
不動産所得又は事業所得を生ずべき
事業を営むもの(所得税法第六十七条
の規定の適用を受ける者を除く。)が、
同法第百四十八条第一項 の
規定により、当該事業につき
帳簿書類を備え付けてこれに
その承認を受けている年分の
不動産所得の金額又は
事業所得の金額に係る取引を
記録している場合(これらの所得の
金額に係る一切の取引の内容を
詳細に記録している場合として
財務省令で定める場合に限る。)
には、その年分の不動産所得の金額
又は事業所得の金額は、
同法第二十六条第二項 又は
第二十七条第二項 の規定により
計算した不動産所得の金額又は
事業所得の金額から次に掲げる
金額のうちいずれか低い金額を
控除した金額とする。
一 六十五万円
二 所得税法第二十六条第二項又は
第二十七条第二項 の規定により
計算した不動産所得の金額又は
事業所得の金額の合計額
4 前項の規定により控除すべき金額は、
不動産所得の金額又は事業所得の
金額から順次控除する。
5 第三項の規定は、確定申告書に
同項の規定の適用を受けようとする旨
及び同項の規定による控除を受ける
金額の計算に関する事項の記載並びに
同項に規定する帳簿書類に基づき
財務省令で定めるところにより作成された
貸借対照表、損益計算書その他
不動産所得の金額又は事業所得の金額の
計算に関する明細書の添付があり、かつ、
当該確定申告書をその提出期限までに
提出した場合に限り、適用する。
(青色申告特別控除額の計算等)
租税特別措置法通達25の2−1
措置法第25条の2第1項又は第3項の
規定による青色申告特別控除額の
計算等については、次の諸点に
留意する。(平5課所4−2追加)
(1) 措置法第25条の2第1項第2号に
規定する不動産所得の金額、
事業所得の金額及び山林所得の金額
又は同条第3項第2号に規定する
不動産所得の金額及び事業所得の
金額は、損益通算をする前の
いわゆる黒字の所得金額を
いうのであるから、
これらの所得の金額の計算上
生じた損失の金額がある場合には、
その損失の金額を除外した
ところにより同条第1項第2号又は
同条第3項第2号の合計額を
計算すること。
(2) 措置法第25条の2第1項の
規定による青色申告特別控除額は、
この控除をする前のいわゆる
黒字の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は
山林所得の金額から、
これらの黒字の金額を限度として
順次控除すること。
また、同条第3項の規定による
青色申告特別控除額は、
この控除をする前のいわゆる黒字の
不動産所得の金額又は事業所得の
金額から、これらの黒字の金額を
限度として順次控除すること。
(3) 措置法第26条第1項
((社会保険診療報酬の所得計算の特例))
の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に
係る所得がある場合には、
同法第25条の2第1項第2号又は
同条第3項第2号に規定する合計額を
計算するときはこれを除外したところに
よるのであるが、同条第2項又は
第4項の控除をするときには、
当該所得を含めた事業所得の金額から
控除すること。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月05日
不動産所得と事業所得の両方がある場合の青色申告特別控除
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人の所得はその所得の発生原因に
基づいて10個の所得区分に分類されます。
そのため事業を行っている人が、
不動産の賃貸もしていると言う場合
もあります。
このように事業所得と不動産所得が
ある場合、青色申告特別控除は
どのような取り扱いとなるのでしょう。
不動産所得の金額、事業所得の金額
の合計額から65万円または10万円を
控除することとなります。
青色申告特別控除とは、
所得金額から65万円または10万円を
控除すると言う制度です。
65万円の控除を受けようとする場合、
以下の全ての要件を満たす必要が
あります。
? 不動産所得又は事業所得を
生ずべき事業を営んでおり
? これらの所得に係る取引を
複式簿記により記帳し
? ?に基づいて作成した
貸借対照表及び損益計算書
を確定申告書に添付し
? 控除を受ける金額を確定申告書
に記載し、
? 法定申告期限内に提出
しなければなりません。
10万円の控除は上記の要件に
該当しない青色申告者が
受けることが出来ます。
そして複数の所得がある場合、
65万円の青色申告控除については、
不動産所得、事業所得の順番で、
10万円の青色申告控除については、
不動産所得、事業所得、山林所得
の順番により控除することとなります。
なおそれぞれの所得において
赤字となっている場合は、
その赤字はないものとして
計算することとなります。
つまり、
? 不動産所得 △20万円
? 事業所得 70万円
の場合、不動産所得から
控除する金額は0円となり、
事業所得から65万円を控除
することとなりますので、
? 不動産所得 △20万円
? 事業所得 5万円
(70万円−65万円)
となります。
なお、現金主義により帳簿の作成を
おこなうことを選択している場合には
65万円の青色申告特別控除は
受けることができませんので、
注意して下さい。
**参考**
(青色申告特別控除)
租税特別措置法第二十五条の二
青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人の
その承認を受けている年分(第三項の
規定の適用を受ける年分を除く。)の
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額は、
所得税法第二十六条第二項 、
第二十七条第二項又は
第三十二条第三項の規定により
計算した不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額
から次に掲げる金額のうちいずれか
低い金額を控除した金額とする。
一 十万円
二 所得税法第二十六条第二項 、
第二十七条第二項又は
第三十二条第三項の規定により
計算した不動産所得の金額、
事業所得の金額(次条第一項の
規定の適用がある場合には、
同項に規定する社会保険診療に
つき支払を受けるべき金額に
対応する部分の金額を除く。
第三項第二号において同じ。)又は
山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額から順次控除する。
3 青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人で
不動産所得又は事業所得を生ずべき
事業を営むもの(所得税法第六十七条
の規定の適用を受ける者を除く。)が、
同法第百四十八条第一項 の
規定により、当該事業につき
帳簿書類を備え付けてこれに
その承認を受けている年分の
不動産所得の金額又は
事業所得の金額に係る取引を
記録している場合(これらの所得の
金額に係る一切の取引の内容を
詳細に記録している場合として
財務省令で定める場合に限る。)
には、その年分の不動産所得の金額
又は事業所得の金額は、
同法第二十六条第二項 又は
第二十七条第二項 の規定により
計算した不動産所得の金額又は
事業所得の金額から次に掲げる
金額のうちいずれか低い金額を
控除した金額とする。
一 六十五万円
二 所得税法第二十六条第二項又は
第二十七条第二項 の規定により
計算した不動産所得の金額又は
事業所得の金額の合計額
4 前項の規定により控除すべき金額は、
不動産所得の金額又は事業所得の
金額から順次控除する。
5 第三項の規定は、確定申告書に
同項の規定の適用を受けようとする旨
及び同項の規定による控除を受ける
金額の計算に関する事項の記載並びに
同項に規定する帳簿書類に基づき
財務省令で定めるところにより作成された
貸借対照表、損益計算書その他
不動産所得の金額又は事業所得の金額の
計算に関する明細書の添付があり、かつ、
当該確定申告書をその提出期限までに
提出した場合に限り、適用する。
(青色申告特別控除額の計算等)
租税特別措置法通達25の2−1
措置法第25条の2第1項又は第3項の
規定による青色申告特別控除額の
計算等については、次の諸点に
留意する。(平5課所4−2追加)
(1) 措置法第25条の2第1項第2号に
規定する不動産所得の金額、
事業所得の金額及び山林所得の金額
又は同条第3項第2号に規定する
不動産所得の金額及び事業所得の
金額は、損益通算をする前の
いわゆる黒字の所得金額を
いうのであるから、
これらの所得の金額の計算上
生じた損失の金額がある場合には、
その損失の金額を除外した
ところにより同条第1項第2号又は
同条第3項第2号の合計額を
計算すること。
(2) 措置法第25条の2第1項の
規定による青色申告特別控除額は、
この控除をする前のいわゆる
黒字の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は
山林所得の金額から、
これらの黒字の金額を限度として
順次控除すること。
また、同条第3項の規定による
青色申告特別控除額は、
この控除をする前のいわゆる黒字の
不動産所得の金額又は事業所得の
金額から、これらの黒字の金額を
限度として順次控除すること。
(3) 措置法第26条第1項
((社会保険診療報酬の所得計算の特例))
の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に
係る所得がある場合には、
同法第25条の2第1項第2号又は
同条第3項第2号に規定する合計額を
計算するときはこれを除外したところに
よるのであるが、同条第2項又は
第4項の控除をするときには、
当該所得を含めた事業所得の金額から
控除すること。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

個人の所得はその所得の発生原因に
基づいて10個の所得区分に分類されます。
そのため事業を行っている人が、
不動産の賃貸もしていると言う場合
もあります。
このように事業所得と不動産所得が
ある場合、青色申告特別控除は
どのような取り扱いとなるのでしょう。
不動産所得の金額、事業所得の金額
の合計額から65万円または10万円を
控除することとなります。
青色申告特別控除とは、
所得金額から65万円または10万円を
控除すると言う制度です。
65万円の控除を受けようとする場合、
以下の全ての要件を満たす必要が
あります。
? 不動産所得又は事業所得を
生ずべき事業を営んでおり
? これらの所得に係る取引を
複式簿記により記帳し
? ?に基づいて作成した
貸借対照表及び損益計算書
を確定申告書に添付し
? 控除を受ける金額を確定申告書
に記載し、
? 法定申告期限内に提出
しなければなりません。
10万円の控除は上記の要件に
該当しない青色申告者が
受けることが出来ます。
そして複数の所得がある場合、
65万円の青色申告控除については、
不動産所得、事業所得の順番で、
10万円の青色申告控除については、
不動産所得、事業所得、山林所得
の順番により控除することとなります。
なおそれぞれの所得において
赤字となっている場合は、
その赤字はないものとして
計算することとなります。
つまり、
? 不動産所得 △20万円
? 事業所得 70万円
の場合、不動産所得から
控除する金額は0円となり、
事業所得から65万円を控除
することとなりますので、
? 不動産所得 △20万円
? 事業所得 5万円
(70万円−65万円)
となります。
なお、現金主義により帳簿の作成を
おこなうことを選択している場合には
65万円の青色申告特別控除は
受けることができませんので、
注意して下さい。
**参考**
(青色申告特別控除)
租税特別措置法第二十五条の二
青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人の
その承認を受けている年分(第三項の
規定の適用を受ける年分を除く。)の
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額は、
所得税法第二十六条第二項 、
第二十七条第二項又は
第三十二条第三項の規定により
計算した不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額
から次に掲げる金額のうちいずれか
低い金額を控除した金額とする。
一 十万円
二 所得税法第二十六条第二項 、
第二十七条第二項又は
第三十二条第三項の規定により
計算した不動産所得の金額、
事業所得の金額(次条第一項の
規定の適用がある場合には、
同項に規定する社会保険診療に
つき支払を受けるべき金額に
対応する部分の金額を除く。
第三項第二号において同じ。)又は
山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、
不動産所得の金額、事業所得の金額
又は山林所得の金額から順次控除する。
3 青色申告書を提出することにつき
税務署長の承認を受けている個人で
不動産所得又は事業所得を生ずべき
事業を営むもの(所得税法第六十七条
の規定の適用を受ける者を除く。)が、
同法第百四十八条第一項 の
規定により、当該事業につき
帳簿書類を備え付けてこれに
その承認を受けている年分の
不動産所得の金額又は
事業所得の金額に係る取引を
記録している場合(これらの所得の
金額に係る一切の取引の内容を
詳細に記録している場合として
財務省令で定める場合に限る。)
には、その年分の不動産所得の金額
又は事業所得の金額は、
同法第二十六条第二項 又は
第二十七条第二項 の規定により
計算した不動産所得の金額又は
事業所得の金額から次に掲げる
金額のうちいずれか低い金額を
控除した金額とする。
一 六十五万円
二 所得税法第二十六条第二項又は
第二十七条第二項 の規定により
計算した不動産所得の金額又は
事業所得の金額の合計額
4 前項の規定により控除すべき金額は、
不動産所得の金額又は事業所得の
金額から順次控除する。
5 第三項の規定は、確定申告書に
同項の規定の適用を受けようとする旨
及び同項の規定による控除を受ける
金額の計算に関する事項の記載並びに
同項に規定する帳簿書類に基づき
財務省令で定めるところにより作成された
貸借対照表、損益計算書その他
不動産所得の金額又は事業所得の金額の
計算に関する明細書の添付があり、かつ、
当該確定申告書をその提出期限までに
提出した場合に限り、適用する。
(青色申告特別控除額の計算等)
租税特別措置法通達25の2−1
措置法第25条の2第1項又は第3項の
規定による青色申告特別控除額の
計算等については、次の諸点に
留意する。(平5課所4−2追加)
(1) 措置法第25条の2第1項第2号に
規定する不動産所得の金額、
事業所得の金額及び山林所得の金額
又は同条第3項第2号に規定する
不動産所得の金額及び事業所得の
金額は、損益通算をする前の
いわゆる黒字の所得金額を
いうのであるから、
これらの所得の金額の計算上
生じた損失の金額がある場合には、
その損失の金額を除外した
ところにより同条第1項第2号又は
同条第3項第2号の合計額を
計算すること。
(2) 措置法第25条の2第1項の
規定による青色申告特別控除額は、
この控除をする前のいわゆる
黒字の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は
山林所得の金額から、
これらの黒字の金額を限度として
順次控除すること。
また、同条第3項の規定による
青色申告特別控除額は、
この控除をする前のいわゆる黒字の
不動産所得の金額又は事業所得の
金額から、これらの黒字の金額を
限度として順次控除すること。
(3) 措置法第26条第1項
((社会保険診療報酬の所得計算の特例))
の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に
係る所得がある場合には、
同法第25条の2第1項第2号又は
同条第3項第2号に規定する合計額を
計算するときはこれを除外したところに
よるのであるが、同条第2項又は
第4項の控除をするときには、
当該所得を含めた事業所得の金額から
控除すること。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月04日
離婚後養育費を渡している子は扶養控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
離婚により子供の親権が相手方にあり
一緒には住んでいないけど、
養育費の支払をしている場合、
この一緒に住んでいない子供を
扶養親族として、扶養控除の対象と
することができるのでしょうか?
このような場合、扶養控除の対象と
なります。
扶養控除の要件は、『生計一』であり
『同居』ではありません。
そのため、たとえ離婚をし、
別々の場所に住んでいたとしても、
養育費の支払を行い、
その養育費により子が生活を
営んでいる場合には、
『生計一』に該当しますので、
その子は、扶養控除の対象となります。
ただし、扶養控除は
養育費を支払っている方か、
親権を持ち、一緒に暮らしている方か、
どちらか一方しか受けることが
できませんので、注意して下さい。
**参考**
(生計を一にするの意義)
所得税法基本通達2−47
法に規定する「生計を一にする」とは、
必ずしも同一の家屋に起居している
ことをいうものではないから、
次のような場合には、
それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上
他の親族と日常の起居を共に
していない親族がいる場合で
あっても、次に掲げる場合に
該当するときは、これらの親族は
生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を
共にしていない親族が、勤務、
修学等の余暇には当該他の親族
のもとで起居を共にすることを
常例としている場合
ロ これらの親族間において、
常に生活費、学資金、療養費等の
送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している
場合には、明らかに互いに独立した
生活を営んでいると認められる
場合を除き、これらの親族は生計を
一にするものとする。
(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
所得税法施行令第二百十九条
法第八十五条第五項 (扶養親族等の判定の
時期等)の場合において、同項 に規定する
二以上の居住者の扶養親族に該当する者を
いずれの居住者の扶養親族とするかは、
これらの居住者の提出するその年分の
前条第一項に規定する申告書等(以下
この条において「申告書等」という。)に
記載されたところによる。ただし、
本文又は次項の規定により、
その扶養親族がいずれか一の居住者の
扶養親族に該当するものとされた
後において、これらの居住者が提出する
申告書等にこれと異なる記載を
することにより、他のいずれか一の
居住者の扶養親族とすることを妨げない。
2 前項の場合において、二以上の
居住者が同一人をそれぞれ自己の
扶養親族として申告書等に記載したとき、
その他同項の規定によりいずれの
居住者の扶養親族とするかを
定められないときは、
次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が
申告書等の記載により
その扶養親族としている場合には、
当該親族は、当該居住者の
扶養親族とする。
二 前号の規定によつてもいずれの
居住者の扶養親族とするかが
定められない扶養親族は、
居住者のうち総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の
合計額又は当該親族がいずれの
居住者の扶養親族とするかを
判定すべき時における当該合計額の
見積額が最も大きい居住者の
扶養親族とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

離婚により子供の親権が相手方にあり
一緒には住んでいないけど、
養育費の支払をしている場合、
この一緒に住んでいない子供を
扶養親族として、扶養控除の対象と
することができるのでしょうか?
このような場合、扶養控除の対象と
なります。
扶養控除の要件は、『生計一』であり
『同居』ではありません。
そのため、たとえ離婚をし、
別々の場所に住んでいたとしても、
養育費の支払を行い、
その養育費により子が生活を
営んでいる場合には、
『生計一』に該当しますので、
その子は、扶養控除の対象となります。
ただし、扶養控除は
養育費を支払っている方か、
親権を持ち、一緒に暮らしている方か、
どちらか一方しか受けることが
できませんので、注意して下さい。
**参考**
(生計を一にするの意義)
所得税法基本通達2−47
法に規定する「生計を一にする」とは、
必ずしも同一の家屋に起居している
ことをいうものではないから、
次のような場合には、
それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上
他の親族と日常の起居を共に
していない親族がいる場合で
あっても、次に掲げる場合に
該当するときは、これらの親族は
生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を
共にしていない親族が、勤務、
修学等の余暇には当該他の親族
のもとで起居を共にすることを
常例としている場合
ロ これらの親族間において、
常に生活費、学資金、療養費等の
送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している
場合には、明らかに互いに独立した
生活を営んでいると認められる
場合を除き、これらの親族は生計を
一にするものとする。
(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
所得税法施行令第二百十九条
法第八十五条第五項 (扶養親族等の判定の
時期等)の場合において、同項 に規定する
二以上の居住者の扶養親族に該当する者を
いずれの居住者の扶養親族とするかは、
これらの居住者の提出するその年分の
前条第一項に規定する申告書等(以下
この条において「申告書等」という。)に
記載されたところによる。ただし、
本文又は次項の規定により、
その扶養親族がいずれか一の居住者の
扶養親族に該当するものとされた
後において、これらの居住者が提出する
申告書等にこれと異なる記載を
することにより、他のいずれか一の
居住者の扶養親族とすることを妨げない。
2 前項の場合において、二以上の
居住者が同一人をそれぞれ自己の
扶養親族として申告書等に記載したとき、
その他同項の規定によりいずれの
居住者の扶養親族とするかを
定められないときは、
次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が
申告書等の記載により
その扶養親族としている場合には、
当該親族は、当該居住者の
扶養親族とする。
二 前号の規定によつてもいずれの
居住者の扶養親族とするかが
定められない扶養親族は、
居住者のうち総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の
合計額又は当該親族がいずれの
居住者の扶養親族とするかを
判定すべき時における当該合計額の
見積額が最も大きい居住者の
扶養親族とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2013年03月01日
定期購入の水の代金1年分をまとめて支払った場合経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
福利厚生の一環として社内に
ウォーターサーバーを設置
している会社も多いと思います。
ではウォーターボトルを
毎月継続購入している場合、
決算期において来年分の
ウォーターボトル代を
前払いした場合、
短期前払費用として
支払った時において経費として
処理することが出来るでしょうか?
この場合、その支払った1年分の
代金は前払費用ではなく、
前払金であるため、経費として
処理することはできません。
短期前払費用とは、
法人が一定の契約により
継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち、
その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、
その支払った金額を継続して
その事業年度の損金の額に
算入しているときは、
その支払時点で損金の額に
算入することが認められる
という制度です。
つまりあくまでも、
『継続的に役務の提供を受けるために』
であり、物品の購入は原則対象と
なりませんので、注意して下さい。
**参考**
(短期の前払費用)
法人税法基本通達2−2−14
前払費用(一定の契約に基づき
継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち当該事業年度
終了の時においてまだ提供を
受けていない役務に
対応するものをいう。
以下2−2−14において同じ。)の額は、
当該事業年度の損金の額に
算入されないのであるが、
法人が、前払費用の額で
その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を
継続してその支払った日の属する
事業年度の損金の額に
算入しているときは、これを認める。
(昭55年直法2−8「七」により追加、
昭61年直法2−12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、
有価証券等に運用する場合の
その借入金に係る支払利子の
ように、収益の計上と対応させる
必要があるものについては、
後段の取扱いの適用は
ないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

福利厚生の一環として社内に
ウォーターサーバーを設置
している会社も多いと思います。
ではウォーターボトルを
毎月継続購入している場合、
決算期において来年分の
ウォーターボトル代を
前払いした場合、
短期前払費用として
支払った時において経費として
処理することが出来るでしょうか?
この場合、その支払った1年分の
代金は前払費用ではなく、
前払金であるため、経費として
処理することはできません。
短期前払費用とは、
法人が一定の契約により
継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち、
その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、
その支払った金額を継続して
その事業年度の損金の額に
算入しているときは、
その支払時点で損金の額に
算入することが認められる
という制度です。
つまりあくまでも、
『継続的に役務の提供を受けるために』
であり、物品の購入は原則対象と
なりませんので、注意して下さい。
**参考**
(短期の前払費用)
法人税法基本通達2−2−14
前払費用(一定の契約に基づき
継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち当該事業年度
終了の時においてまだ提供を
受けていない役務に
対応するものをいう。
以下2−2−14において同じ。)の額は、
当該事業年度の損金の額に
算入されないのであるが、
法人が、前払費用の額で
その支払った日から1年以内に
提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を
継続してその支払った日の属する
事業年度の損金の額に
算入しているときは、これを認める。
(昭55年直法2−8「七」により追加、
昭61年直法2−12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、
有価証券等に運用する場合の
その借入金に係る支払利子の
ように、収益の計上と対応させる
必要があるものについては、
後段の取扱いの適用は
ないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。



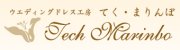


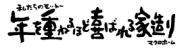




 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン





