2012年08月31日
報酬を金銭でなく自社商品等現物で支払った場合の源泉は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
自社専属のセールスマンに金銭による報酬のうち
一部を自社商品により支払った場合、
その支払いの源泉徴収については、
金銭で支払った部分だけでいいのでしょうか?
上記のような場合、金銭で支払った部分のみならず、
現物で支給した部分についても源泉徴収は
必要となります。
職業野球の選手、外交員、集金人、ホステス等のように
一定の者に専属して役務を提供する者が
その役務の提供先から受ける経済的利益については、
給与等とされる経済的利益の取扱いに準ずる。
とされています。
給与等とされる経済的利益の取り扱いは、
使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、
製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、
その支給時における次に掲げる価額により評価する。
(1) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
である場合には、当該使用者の通常の販売価額
(2) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
でない場合には、当該物の通常売買される価額。
ただし、当該物が、役員又は使用人に
支給するため使用者が購入したものであり、かつ、
その購入時からその支給時までの間にその価額に
さして変動がないものであるときは、
その購入価額によることができる。
となりますので、金銭以外で支給した部分は、
通常の販売価格をもって、源泉徴収税額の
計算を行うこととなります。
**参考**
(商品、製品等の評価)
所得税法基本通達36−39
使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、
製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、
その支給時における次に掲げる価額により評価する。
(1) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
である場合には、当該使用者の通常の販売価額
(2) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
でない場合には、当該物の通常売買される価額。
ただし、当該物が、役員又は使用人に
支給するため使用者が購入したものであり、かつ、
その購入時からその支給時までの間にその価額に
さして変動がないものであるときは、
その購入価額によることができる。
(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)
所得税法基本通達204−3
法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに
掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有する経済的利益
(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をいう。
以下この項において同じ。)については、次によるものとする。
(1) 職業野球の選手、外交員、集金人、ホステス等のように
一定の者に専属して役務を提供する者がその役務の
提供先から受ける経済的利益については、
給与等とされる経済的利益の取扱いに準ずる。
(2) (1)以外の経済的利益については、令第321条
《金銭以外のもので支払われる賞金の価額》の規定に
準じて評価し、その評価した金額が少額なものについては、
源泉徴収をしなくて差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

自社専属のセールスマンに金銭による報酬のうち
一部を自社商品により支払った場合、
その支払いの源泉徴収については、
金銭で支払った部分だけでいいのでしょうか?
上記のような場合、金銭で支払った部分のみならず、
現物で支給した部分についても源泉徴収は
必要となります。
職業野球の選手、外交員、集金人、ホステス等のように
一定の者に専属して役務を提供する者が
その役務の提供先から受ける経済的利益については、
給与等とされる経済的利益の取扱いに準ずる。
とされています。
給与等とされる経済的利益の取り扱いは、
使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、
製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、
その支給時における次に掲げる価額により評価する。
(1) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
である場合には、当該使用者の通常の販売価額
(2) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
でない場合には、当該物の通常売買される価額。
ただし、当該物が、役員又は使用人に
支給するため使用者が購入したものであり、かつ、
その購入時からその支給時までの間にその価額に
さして変動がないものであるときは、
その購入価額によることができる。
となりますので、金銭以外で支給した部分は、
通常の販売価格をもって、源泉徴収税額の
計算を行うこととなります。
**参考**
(商品、製品等の評価)
所得税法基本通達36−39
使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、
製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、
その支給時における次に掲げる価額により評価する。
(1) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
である場合には、当該使用者の通常の販売価額
(2) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
でない場合には、当該物の通常売買される価額。
ただし、当該物が、役員又は使用人に
支給するため使用者が購入したものであり、かつ、
その購入時からその支給時までの間にその価額に
さして変動がないものであるときは、
その購入価額によることができる。
(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)
所得税法基本通達204−3
法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに
掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有する経済的利益
(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をいう。
以下この項において同じ。)については、次によるものとする。
(1) 職業野球の選手、外交員、集金人、ホステス等のように
一定の者に専属して役務を提供する者がその役務の
提供先から受ける経済的利益については、
給与等とされる経済的利益の取扱いに準ずる。
(2) (1)以外の経済的利益については、令第321条
《金銭以外のもので支払われる賞金の価額》の規定に
準じて評価し、その評価した金額が少額なものについては、
源泉徴収をしなくて差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月30日
代表取締役の結婚披露宴費用を法人が負担した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人の代表者が結婚をする場合に、
結婚披露宴に取引先を招待すれば、
法人でその費用を負担しても、
接待行為であり交際費として
処理することができるのでしょうか?
法人が事業関係者に対して、
接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出するものは
交際費として処理することとされています。
では代表取締役の結婚披露宴に、
取引先を招待し、その費用を法人が
負担した場合には、接待等として
交際費として処理することが
できるのでしょうか?
交際費として認められるためには、
会社が取引関係の円滑な進行を
図るために支出し、その支出によって
接待等の利益を受ける者が
会社からの支出によってその利益を
受けていると認識できるような
客観的状況の下に接待行為が
行われている場合と解されます。
そのためたとえその結婚披露宴に
取引先を招待したとしても、
その取引先は接待等を受けているという
認識はなく、かつ、結婚披露宴に招待
することが、法人の業務との関連性を
認められないため、その支出は
交際費ではなく、その代表取締役に対する
賞与として取り扱われることとなります。
**参考**
交際費等の範囲と定額控除限度額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

法人の代表者が結婚をする場合に、
結婚披露宴に取引先を招待すれば、
法人でその費用を負担しても、
接待行為であり交際費として
処理することができるのでしょうか?
法人が事業関係者に対して、
接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出するものは
交際費として処理することとされています。
では代表取締役の結婚披露宴に、
取引先を招待し、その費用を法人が
負担した場合には、接待等として
交際費として処理することが
できるのでしょうか?
交際費として認められるためには、
会社が取引関係の円滑な進行を
図るために支出し、その支出によって
接待等の利益を受ける者が
会社からの支出によってその利益を
受けていると認識できるような
客観的状況の下に接待行為が
行われている場合と解されます。
そのためたとえその結婚披露宴に
取引先を招待したとしても、
その取引先は接待等を受けているという
認識はなく、かつ、結婚披露宴に招待
することが、法人の業務との関連性を
認められないため、その支出は
交際費ではなく、その代表取締役に対する
賞与として取り扱われることとなります。
**参考**
交際費等の範囲と定額控除限度額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月29日
役員だけで慰安旅行に行った費用は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
決算で計画以上の利益が出たり、
役員相互間の意思疎通を図ることを
目的としたり、という理由で
役員のみを対象に慰安旅行に
行った場合には、その費用は
どのように取り扱われるでしょう?
この場合、役員賞与として
取り扱われる可能性が高いと思われます。
そもそも慰安旅行の費用が、福利厚生費
として認められるためには原則として、
(1) 旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、
目的地における滞在日数によります。)
以内のものであること
(2) 旅行に参加する従業員の数が、全従業員の数
(工場、支店等で行う場合は、その工場、支店等の
従業員等)の50%以上であること
(3) 支出する金額が社会通念上妥当なものであること
(4) 会社主催のものであること
などの要件を満たす必要があります。
今回の場合には役員のみが対象なので、
福利厚生費からは外れてしまいます。
ではどのように取り扱うのかというと、
原則的には役員賞与とみなされてしまいます。
役員賞与とみなされた場合には、
法人税法上は損金不算入となり、かつ、
所得税の源泉徴収が必要となります。
ただし、その慰安旅行の実行が、
社会通念上一般的に行われており、
会社の業務遂行上必要であり、
役員のみを対象とする接待、慰安
のための旅行であると認められた
場合には、交際費として取り扱う
こととなります。
が、役員のみの慰安旅行が
社会通念上一般的に行われている
とは言いがたいため、
交際費処理は難しいと思われます。
**参考**
(課税しない経済的利益
……使用者が負担するレクリエーションの費用)
所得税法基本通達36−30
使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために
社会通念上一般的に行われていると認められる会食、
旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を
負担することにより、これらの行事に参加した役員又は
使用人が受ける経済的利益については、使用者が、
当該行事に参加しなかった役員又は使用人
(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)
に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は
役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、
課税しなくて差し支えない。
(注) 上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の
必要に基づき参加できなかった者を含む。)に
支給する金銭については、給与等として
課税することに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

決算で計画以上の利益が出たり、
役員相互間の意思疎通を図ることを
目的としたり、という理由で
役員のみを対象に慰安旅行に
行った場合には、その費用は
どのように取り扱われるでしょう?
この場合、役員賞与として
取り扱われる可能性が高いと思われます。
そもそも慰安旅行の費用が、福利厚生費
として認められるためには原則として、
(1) 旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、
目的地における滞在日数によります。)
以内のものであること
(2) 旅行に参加する従業員の数が、全従業員の数
(工場、支店等で行う場合は、その工場、支店等の
従業員等)の50%以上であること
(3) 支出する金額が社会通念上妥当なものであること
(4) 会社主催のものであること
などの要件を満たす必要があります。
今回の場合には役員のみが対象なので、
福利厚生費からは外れてしまいます。
ではどのように取り扱うのかというと、
原則的には役員賞与とみなされてしまいます。
役員賞与とみなされた場合には、
法人税法上は損金不算入となり、かつ、
所得税の源泉徴収が必要となります。
ただし、その慰安旅行の実行が、
社会通念上一般的に行われており、
会社の業務遂行上必要であり、
役員のみを対象とする接待、慰安
のための旅行であると認められた
場合には、交際費として取り扱う
こととなります。
が、役員のみの慰安旅行が
社会通念上一般的に行われている
とは言いがたいため、
交際費処理は難しいと思われます。
**参考**
(課税しない経済的利益
……使用者が負担するレクリエーションの費用)
所得税法基本通達36−30
使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために
社会通念上一般的に行われていると認められる会食、
旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を
負担することにより、これらの行事に参加した役員又は
使用人が受ける経済的利益については、使用者が、
当該行事に参加しなかった役員又は使用人
(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)
に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は
役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、
課税しなくて差し支えない。
(注) 上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の
必要に基づき参加できなかった者を含む。)に
支給する金銭については、給与等として
課税することに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月28日
接待旅行がキャンセルになった場合のキャンセル料は交際費?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
取引先を接待する目的で旅行をくみ、
手付けの支払いを済ました後に、
取引先の都合によりその接待旅行を
キャンセルした場合、
そのキャンセルにより発生したキャンセル料は
接待旅行に付随するものとして、
交際費となるのでしょうか?
たとえ接待旅行がキャンセルになり
キャンセル料が発生したとしても、
交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出する
費用とされています。
このキャンセル料は接待を目的とは
していましたが、その接待は行われて
いないので、交際費には該当せず、
通常の損金として処理することとなります。
**参考**
交際費等の範囲と定額控除限度額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

取引先を接待する目的で旅行をくみ、
手付けの支払いを済ました後に、
取引先の都合によりその接待旅行を
キャンセルした場合、
そのキャンセルにより発生したキャンセル料は
接待旅行に付随するものとして、
交際費となるのでしょうか?
たとえ接待旅行がキャンセルになり
キャンセル料が発生したとしても、
交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出する
費用とされています。
このキャンセル料は接待を目的とは
していましたが、その接待は行われて
いないので、交際費には該当せず、
通常の損金として処理することとなります。
**参考**
交際費等の範囲と定額控除限度額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月27日
復興特別税とは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
東日本大震災からの復興のための施策を
実施するために必要な財源の確保のため、
復興特別所得税と復興特別法人税が創設されました。
復興特別所得税は、
所得税を納める義務のある個人に対して、
平成25年から平成49年までの各年分の
基準所得税額に、2.1%の税率を乗じて
計算した復興特別所得税が通常の所得税に
加算されます。
復興特別法人税は、
法人に対して、平成24年4月1日から
平成27年3月31日までの期間内に最初に
開始する事業年度開始の日から同日以後
3年を経過する日までの期間内の日の属する
事業年度における、各事業年度の所得の
金額に対する法人税の額に10%の
税率を乗じて計算した復興特別法人税を
通常の法人税に加算されます。
なお、これに伴い源泉所得税額も
変更となりますので、平成25年1月1日以降は
注意をしてください。
**参考**
復興特別法人税
復興特別所得税
源泉所得税額(あらまし)
源泉所得税額(Q&A)
源泉所得税率表
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

東日本大震災からの復興のための施策を
実施するために必要な財源の確保のため、
復興特別所得税と復興特別法人税が創設されました。
復興特別所得税は、
所得税を納める義務のある個人に対して、
平成25年から平成49年までの各年分の
基準所得税額に、2.1%の税率を乗じて
計算した復興特別所得税が通常の所得税に
加算されます。
復興特別法人税は、
法人に対して、平成24年4月1日から
平成27年3月31日までの期間内に最初に
開始する事業年度開始の日から同日以後
3年を経過する日までの期間内の日の属する
事業年度における、各事業年度の所得の
金額に対する法人税の額に10%の
税率を乗じて計算した復興特別法人税を
通常の法人税に加算されます。
なお、これに伴い源泉所得税額も
変更となりますので、平成25年1月1日以降は
注意をしてください。
**参考**
復興特別法人税
復興特別所得税
源泉所得税額(あらまし)
源泉所得税額(Q&A)
源泉所得税率表
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月24日
取引先ごとで異なる収益の計上基準は採用できる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
売上は何時の時点で認識されるかというと、
原則的には商品、製品を引き渡した時とされています。
そしてその引き渡した時とは?
というと、例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日によるとされています。
**参考**
では例えば出荷した日を引渡しの日として処理をしていたが、
取引先の都合により出荷した日ではなく、
その取引先が検収した後でなければ処理ができない場合、
その取引先のみ検収した日を引き渡した日と
することができるのでしょうか?
収益の計上基準は、当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日とされていますので、
それぞれ異なる収益計上基準を採用することに
合理性があり、かつ、継続して適用すれば
認められると思われます。
**参考**
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
法人税法基本通達2−1−1
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する
事業年度の益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
法人税法基本通達2−1−2
2−1−1の場合において、
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る
契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が
継続してその収益計上を行うこととしている日
によるものとする。
この場合において、当該棚卸資産が土地又は
土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。
(昭55年直法2−8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

売上は何時の時点で認識されるかというと、
原則的には商品、製品を引き渡した時とされています。
そしてその引き渡した時とは?
というと、例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日によるとされています。
**参考**
では例えば出荷した日を引渡しの日として処理をしていたが、
取引先の都合により出荷した日ではなく、
その取引先が検収した後でなければ処理ができない場合、
その取引先のみ検収した日を引き渡した日と
することができるのでしょうか?
収益の計上基準は、当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日とされていますので、
それぞれ異なる収益計上基準を採用することに
合理性があり、かつ、継続して適用すれば
認められると思われます。
**参考**
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
法人税法基本通達2−1−1
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する
事業年度の益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
法人税法基本通達2−1−2
2−1−1の場合において、
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る
契約の内容等に応じその引渡しの日として
合理的であると認められる日のうち法人が
継続してその収益計上を行うこととしている日
によるものとする。
この場合において、当該棚卸資産が土地又は
土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。
(昭55年直法2−8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月23日
拾得物に税金はかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
たまにTVで『100万円を拾った』とか、
『ゴミ捨て場に1,000万円落ちていた』とか、
見かけますが、もし実際にお金を拾った場合、
落とし主が見つからないままそのお金を
もらうこととなった場合、
税金はかかるのでしょうか?
遺失物の取得や埋蔵物の発見などにより
所有権を取得した場合には、
その拾得物や埋蔵物には一時所得として、
所得税がかかります。
なお、落とし主が発見されて、謝礼として
金銭等を受取った場合にも、
その謝礼金は一時所得として、
所得税がかかりますので、注意してください。
**参考**
(一時所得の例示)
所得税法基本通達34−1
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(昭49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、
平11課所4−1、平17課個2−23、課資3−5、課法8−6、
課審4−113、平18課個2−18、課資3−10、課審4−114、
平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
(11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により
新たに所有権を取得する資産
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

たまにTVで『100万円を拾った』とか、
『ゴミ捨て場に1,000万円落ちていた』とか、
見かけますが、もし実際にお金を拾った場合、
落とし主が見つからないままそのお金を
もらうこととなった場合、
税金はかかるのでしょうか?
遺失物の取得や埋蔵物の発見などにより
所有権を取得した場合には、
その拾得物や埋蔵物には一時所得として、
所得税がかかります。
なお、落とし主が発見されて、謝礼として
金銭等を受取った場合にも、
その謝礼金は一時所得として、
所得税がかかりますので、注意してください。
**参考**
(一時所得の例示)
所得税法基本通達34−1
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(昭49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、
平11課所4−1、平17課個2−23、課資3−5、課法8−6、
課審4−113、平18課個2−18、課資3−10、課審4−114、
平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
(11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により
新たに所有権を取得する資産
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月22日
還付加算金の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
税金を多く納めすぎていた場合に、
還付金とあわせて支払われる還付加算金。
この還付加算金を受取った場合には、
どのように取り扱うこととなるのでしょうか?
納税が遅れた場合、延滞税や加算税が
遅れた期間に対応する利子的なものとして
徴収されます。
これとは逆に、収めすぎていた場合に
受取るものが還付加算金となりますので、
利子的要素が多くありますので、
非営業貸金利子と同様に、
雑所得に該当することとなります。
**参考**
(雑所得の例示)
所得税法基本通達35−1
次に掲げるようなものに係る所得は、
雑所得に該当する。
(平8課法8−2、課所4−5、平11課所4−1、
平22課個2−25、課審4−45、平23課個2−33、
課法9−9、課審4−46改正)
(5) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は
地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に
規定する還付加算金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

税金を多く納めすぎていた場合に、
還付金とあわせて支払われる還付加算金。
この還付加算金を受取った場合には、
どのように取り扱うこととなるのでしょうか?
納税が遅れた場合、延滞税や加算税が
遅れた期間に対応する利子的なものとして
徴収されます。
これとは逆に、収めすぎていた場合に
受取るものが還付加算金となりますので、
利子的要素が多くありますので、
非営業貸金利子と同様に、
雑所得に該当することとなります。
**参考**
(雑所得の例示)
所得税法基本通達35−1
次に掲げるようなものに係る所得は、
雑所得に該当する。
(平8課法8−2、課所4−5、平11課所4−1、
平22課個2−25、課審4−45、平23課個2−33、
課法9−9、課審4−46改正)
(5) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は
地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に
規定する還付加算金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月21日
受託販売を行っている事業者の消費税簡易課税の区分は何種?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
消費税には原則課税と呼ばれるものと、
簡易課税と呼ばれるものと2つの
課税方式が存在します。
これらの詳しい話は省略しますが、
簡易課税を選択する場合、
その営む業種の区分に応じて、
第1種から第5種に振り分けられ、
それぞれに定めるみなし仕入率が
適用されることとなります。
第1種は卸売業
第2種は小売業
第3種は製造業
第4種はその他の事業
第5種はサービス業
というように区分されます。
では商品の受託販売を行っている場合は
第何種に該当するのでしょう?
商品を事業者に販売しているから卸売り?
商品を消費者に販売しているから小売り?
それとも受託販売というサービス業?
実は受託販売は第4種に該当します。
まず、第3種は製造業なのでこれには該当しないと
わかりますね。
では次に卸売業・小売業についてですが、
この定義は、『他から購入した商品を・・・』
そう、受託販売は商品を他から購入したわけではないので
どちらにも該当しないこととなります。
では第5種のサービス業かと言うと、
実はサービス業には定義があり、
おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる
事業とされています。
そしてその中には受託販売は含まれておらず、
最終的に残った第4種に該当するということです。
簡易課税の場合、事業区分の判定を間違うと
大きなミスとなりうるので、判定は慎重に
行うようにしてください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

消費税には原則課税と呼ばれるものと、
簡易課税と呼ばれるものと2つの
課税方式が存在します。
これらの詳しい話は省略しますが、
簡易課税を選択する場合、
その営む業種の区分に応じて、
第1種から第5種に振り分けられ、
それぞれに定めるみなし仕入率が
適用されることとなります。
第1種は卸売業
第2種は小売業
第3種は製造業
第4種はその他の事業
第5種はサービス業
というように区分されます。
では商品の受託販売を行っている場合は
第何種に該当するのでしょう?
商品を事業者に販売しているから卸売り?
商品を消費者に販売しているから小売り?
それとも受託販売というサービス業?
実は受託販売は第4種に該当します。
まず、第3種は製造業なのでこれには該当しないと
わかりますね。
では次に卸売業・小売業についてですが、
この定義は、『他から購入した商品を・・・』
そう、受託販売は商品を他から購入したわけではないので
どちらにも該当しないこととなります。
では第5種のサービス業かと言うと、
実はサービス業には定義があり、
おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる
事業とされています。
そしてその中には受託販売は含まれておらず、
最終的に残った第4種に該当するということです。
簡易課税の場合、事業区分の判定を間違うと
大きなミスとなりうるので、判定は慎重に
行うようにしてください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月20日
複数人で購入した宝くじが当たった場合、贈与税がかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
家族や友人、会社の同僚などと一緒に資金を出し合い
宝くじを購入するという場面をたまに見かけますが、
もしこの共同購入した宝くじが当たった場合、
購入した人たちで山分けした場合、
贈与税はかからないのでしょうか?
宝くじは所得税法上において非課税とされています。
しかしこれは当選した人が当選金を受取った場合です。
実は共同購入した当選金を分配する場合には
注意が必要になります。
たとえば当選金を代表者が受け取り、
代表者が分配を行った場合には贈与税が
課税されてしまう可能性があるのです。
これは当選金を贈与により分配したと
みなされてしまうためです。
贈与税を課税されないようにするためには、
たとえ代表者が受け取りに行ったとしても、
全員の委任状を持参し、それぞれの口座に
振り込んでもらうことがポイントです。
また更に用心をするのであれば、
各々の出資額、分配率を記載した
契約書又は覚書を作成しておくと良いと思います。
**参考**
(贈与税の課税)
相続税法第二十一条
贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、
贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として
計算した金額により、課する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

家族や友人、会社の同僚などと一緒に資金を出し合い
宝くじを購入するという場面をたまに見かけますが、
もしこの共同購入した宝くじが当たった場合、
購入した人たちで山分けした場合、
贈与税はかからないのでしょうか?
宝くじは所得税法上において非課税とされています。
しかしこれは当選した人が当選金を受取った場合です。
実は共同購入した当選金を分配する場合には
注意が必要になります。
たとえば当選金を代表者が受け取り、
代表者が分配を行った場合には贈与税が
課税されてしまう可能性があるのです。
これは当選金を贈与により分配したと
みなされてしまうためです。
贈与税を課税されないようにするためには、
たとえ代表者が受け取りに行ったとしても、
全員の委任状を持参し、それぞれの口座に
振り込んでもらうことがポイントです。
また更に用心をするのであれば、
各々の出資額、分配率を記載した
契約書又は覚書を作成しておくと良いと思います。
**参考**
(贈与税の課税)
相続税法第二十一条
贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、
贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として
計算した金額により、課する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月17日
親兄弟からの借入は贈与税が課税されることがある?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
マイホームを購入する際に親から
住宅資金を贈与により受取ることが
できる人もいると思いますが、
親兄弟から住宅資金を借りて
マイホームを購入するという場合も
多いと思います。
しかし、この親兄弟からの借入について
『ある時払いの催促なし、利息もなし、契約書もなし』
としている場合、この借入は贈与とみなされ
贈与税が課税される可能性があります。
これは実質的に『ある時払い〜』ということは、
返済資金がなければ返済しなくてもいい
ということになり、贈与をしたのと変わらないためです。
そうなると贈与税は、
贈与金額から基礎控除額(110万円/年)を控除
した金額に対して以下の金額の区分に応じた税率が
課税されることとなります。
基礎控除後金額 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
つまり、1,000万円の贈与とみなされると、
1,000万円−110万円=890万円
890万円×40%−125万円=231万円
となり231万円の贈与税の納税が発生します。
親兄弟間での金銭の貸し借りに対しても、
『ある時払いの催促なし、利息なし、契約書なし』
ではなく、返済計画をしっかり立てて、
金銭消費貸借契約書を作成し、
利息の支払いに対して領収書を作成し、
保管するといった防衛策をとっておくことを
おすすめします。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二
贈与により財産を取得した者がその年中における
贈与による財産の取得について第一条の四第一号
又は第二号の規定に該当する者である場合においては、
その者については、その年中において贈与により
取得した財産の価額の合計額をもつて、
贈与税の課税価格とする。
2 贈与により財産を取得した者が
その年中における贈与による財産の取得について
第一条の四第三号の規定に該当する者である
場合においては、その者については、
その年中において贈与により取得した財産で
この法律の施行地にあるものの価額の
合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
3 贈与により財産を取得した者がその年中における
贈与による財産の取得について第一条の四第一号の
規定に該当し、かつ、同条第三号の規定に該当する者
又は同条第二号の規定に該当し、かつ、
同条第三号の規定に該当する者である場合においては、
その者については、その者がこの法律の施行地に
住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の
価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた
期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの
価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から
受けた贈与により取得した財産の価額で
第十九条の規定により相続税の課税価格に
加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、
贈与税の課税価格に算入しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

マイホームを購入する際に親から
住宅資金を贈与により受取ることが
できる人もいると思いますが、
親兄弟から住宅資金を借りて
マイホームを購入するという場合も
多いと思います。
しかし、この親兄弟からの借入について
『ある時払いの催促なし、利息もなし、契約書もなし』
としている場合、この借入は贈与とみなされ
贈与税が課税される可能性があります。
これは実質的に『ある時払い〜』ということは、
返済資金がなければ返済しなくてもいい
ということになり、贈与をしたのと変わらないためです。
そうなると贈与税は、
贈与金額から基礎控除額(110万円/年)を控除
した金額に対して以下の金額の区分に応じた税率が
課税されることとなります。
基礎控除後金額 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
つまり、1,000万円の贈与とみなされると、
1,000万円−110万円=890万円
890万円×40%−125万円=231万円
となり231万円の贈与税の納税が発生します。
親兄弟間での金銭の貸し借りに対しても、
『ある時払いの催促なし、利息なし、契約書なし』
ではなく、返済計画をしっかり立てて、
金銭消費貸借契約書を作成し、
利息の支払いに対して領収書を作成し、
保管するといった防衛策をとっておくことを
おすすめします。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二
贈与により財産を取得した者がその年中における
贈与による財産の取得について第一条の四第一号
又は第二号の規定に該当する者である場合においては、
その者については、その年中において贈与により
取得した財産の価額の合計額をもつて、
贈与税の課税価格とする。
2 贈与により財産を取得した者が
その年中における贈与による財産の取得について
第一条の四第三号の規定に該当する者である
場合においては、その者については、
その年中において贈与により取得した財産で
この法律の施行地にあるものの価額の
合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
3 贈与により財産を取得した者がその年中における
贈与による財産の取得について第一条の四第一号の
規定に該当し、かつ、同条第三号の規定に該当する者
又は同条第二号の規定に該当し、かつ、
同条第三号の規定に該当する者である場合においては、
その者については、その者がこの法律の施行地に
住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の
価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた
期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの
価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から
受けた贈与により取得した財産の価額で
第十九条の規定により相続税の課税価格に
加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、
贈与税の課税価格に算入しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月16日
取引先に金銭を無利息で貸し付けた場合
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業を行っていると取引先から資金の借入を
申し込まれることもあると思います。
そしてその際にお付き合いのある取引先であるため、
無利息や低利率で貸す場合があると思います。
このような無利息や低利率での金銭の融資は
税務上問題とならないのでしょうか?
無利息や低利率で融資を行うと、
通常収受すべき利息の金額と、実際に受けた
利息の金額との差額は経済的利益とみなされ、
その差額部分を贈与したものとして取り扱われます。
つまり、その差額を受取利息として収益計上し
そしてその差額を贈与したということで寄付金として
費用計上を行います。
寄付金は法人税法上損金算入に一定の制限が
あるため、金銭の収受を行っていませんが、
利益として税金が課税される可能性があります。
ただし、子会社や関連会社などの倒産を防止するために
やむを得ず行われるもので合理的な再建計画に
基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて
相当な理由があると認められるときは、
その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、
寄附金の額に該当しません。
**参考**
(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)
法人税法基本通達9−4−2
法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは
通常の利率よりも低い利率での貸付け又は
債権放棄等(以下9−4−2において「無利息貸付け等」
という。)をした場合において、
その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の
倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので
合理的な再建計画に基づくものである等
その無利息貸付け等をしたことについて
相当な理由があると認められるときは、
その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、
寄附金の額に該当しないものとする。
(昭55年直法2−8「三十三」により追加、平10年課法2−6により改正)
(注) 合理的な再建計画かどうかについては、
支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、
支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、
個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、
例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により
策定されたものと認められる再建計画は、
原則として、合理的なものと取り扱う。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

事業を行っていると取引先から資金の借入を
申し込まれることもあると思います。
そしてその際にお付き合いのある取引先であるため、
無利息や低利率で貸す場合があると思います。
このような無利息や低利率での金銭の融資は
税務上問題とならないのでしょうか?
無利息や低利率で融資を行うと、
通常収受すべき利息の金額と、実際に受けた
利息の金額との差額は経済的利益とみなされ、
その差額部分を贈与したものとして取り扱われます。
つまり、その差額を受取利息として収益計上し
そしてその差額を贈与したということで寄付金として
費用計上を行います。
寄付金は法人税法上損金算入に一定の制限が
あるため、金銭の収受を行っていませんが、
利益として税金が課税される可能性があります。
ただし、子会社や関連会社などの倒産を防止するために
やむを得ず行われるもので合理的な再建計画に
基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて
相当な理由があると認められるときは、
その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、
寄附金の額に該当しません。
**参考**
(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)
法人税法基本通達9−4−2
法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは
通常の利率よりも低い利率での貸付け又は
債権放棄等(以下9−4−2において「無利息貸付け等」
という。)をした場合において、
その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の
倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので
合理的な再建計画に基づくものである等
その無利息貸付け等をしたことについて
相当な理由があると認められるときは、
その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、
寄附金の額に該当しないものとする。
(昭55年直法2−8「三十三」により追加、平10年課法2−6により改正)
(注) 合理的な再建計画かどうかについては、
支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、
支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、
個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、
例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により
策定されたものと認められる再建計画は、
原則として、合理的なものと取り扱う。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月15日
日照権の補償金を支払った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
高層ビルや高層マンション等を建築する際、
地域住民からの反対運動などにより、
日照権の侵害に対する補償金を支払う場合が
あります。
この日照権の侵害に対する補償金を支払った場合、
この支払い金額は損害賠償金として
支払時に一括して費用処理してもいいのでしょうか?
建物の建設について当初からその支出が予定されている
日照権の侵害にかかる補償金は、建物の取得に
要するものであるため、建物の取得価額に
算入しなければなりません。
**参考**
(事後的に支出する費用)
法人税法基本通達7−3−7
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
記念費用等のように減価償却資産の取得後に
生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の
取得価額に算入しないことができるものとするが、
工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
住民対策費、公害補償費等の費用
(7−3−11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)
の額で当初からその支出が予定されているもの
(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(昭55年直法2−8「二十一」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

高層ビルや高層マンション等を建築する際、
地域住民からの反対運動などにより、
日照権の侵害に対する補償金を支払う場合が
あります。
この日照権の侵害に対する補償金を支払った場合、
この支払い金額は損害賠償金として
支払時に一括して費用処理してもいいのでしょうか?
建物の建設について当初からその支出が予定されている
日照権の侵害にかかる補償金は、建物の取得に
要するものであるため、建物の取得価額に
算入しなければなりません。
**参考**
(事後的に支出する費用)
法人税法基本通達7−3−7
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
記念費用等のように減価償却資産の取得後に
生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の
取得価額に算入しないことができるものとするが、
工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
住民対策費、公害補償費等の費用
(7−3−11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)
の額で当初からその支出が予定されているもの
(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(昭55年直法2−8「二十一」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月14日
源泉所得税の金額の計算に消費税は含める?含めない?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
源泉徴収の対象となる報酬の
支払いを行った場合には、
源泉徴収を控除した金額を
先方に支払うこととなります。
このように源泉所得税が徴収される場合、
源泉所得税の金額の計算に消費税は
含めるのでしょうか?
それとも含めないのでしょうか?
結論から言うと、
原則として、報酬の金額のみならず、
消費税等の金額も含めた金額に対して
源泉所得税の金額を計算することとなります。
つまり報酬の金額が、10,000円(税抜)の場合、
源泉所得税の金額は、
10,000円×10%=1,000円ではなく、
(10,000円+10,000円×5%)×10%=1,050円
となります。
ただし、請求書等において、報酬料金と
消費税等の金額が明確に区分して
記載してある場合には、
源泉所得税の金額は消費税を含めないで
計算することも認められます。
**参考**
国税庁HP
消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

源泉徴収の対象となる報酬の
支払いを行った場合には、
源泉徴収を控除した金額を
先方に支払うこととなります。
このように源泉所得税が徴収される場合、
源泉所得税の金額の計算に消費税は
含めるのでしょうか?
それとも含めないのでしょうか?
結論から言うと、
原則として、報酬の金額のみならず、
消費税等の金額も含めた金額に対して
源泉所得税の金額を計算することとなります。
つまり報酬の金額が、10,000円(税抜)の場合、
源泉所得税の金額は、
10,000円×10%=1,000円ではなく、
(10,000円+10,000円×5%)×10%=1,050円
となります。
ただし、請求書等において、報酬料金と
消費税等の金額が明確に区分して
記載してある場合には、
源泉所得税の金額は消費税を含めないで
計算することも認められます。
**参考**
国税庁HP
消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月13日
特定役員退職手当等にかかる退職所得の金額の計算方法は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
退職所得に該当した場合、
一般的に、過去から長期間にわたる労働の対価の
後払いという性格を持っていることや、
退職後の老後の生活の原資に当てるべきもの
という性質のため、退職所得の金額は
他の所得とは分けて
(退職所得の金額−(※)退職所得控除額)×1/2
(※)退職所得控除額
勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合 800万円+70万円
×(勤続年数−20年)
という計算式により算出されていました。
しかし今回の税制改正により、
平成25年分以後の退職所得のうち、
特定役員退職手当等に該当するものの、
計算式は以下のようになります。
退職所得の金額−退職所得控除額
つまり、2分の1課税の制度が廃止されました。
ここにいう特定役員退職手当等とは、
退職手当等のうち、役員等勤続年数が
5年以下の
?法人税法に規定する役員
?国会議員及び地方公共団体の議会の議員
?国家公務員及び地方公務員
が支払いを受けるものを言います。
**参考**
(退職所得)
所得税法第三十条
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により
一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与
(以下この条において「退職手当等」という。)に
係る所得をいう。
2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の
収入金額から退職所得控除額を控除した残額の
二分の一に相当する金額とする。
3 前項に規定する退職所得控除額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に掲げる金額とする。
一 政令で定める勤続年数(以下この項において
「勤続年数」という。)が二十年以下である場合
四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
二 勤続年数が二十年を超える場合
八百万円と七十万円に当該勤続年数から
二十年を控除した年数を乗じて計算した金額
との合計額
4 次の各号に掲げる場合に該当するときは、
第二項に規定する退職所得控除額は、
前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 その年の前年以前に他の退職手当等の
支払を受けている場合で政令で定める場合
前項の規定により計算した金額から、
当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより
同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
二 前項及び前号の規定により計算した金額が
八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。)
八十万円
三 障害者になつたことに直接基因して退職したと
認められる場合で政令で定める場合
前項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が
八十万円に満たない場合には、八十万円)に
百万円を加算した金額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

退職所得に該当した場合、
一般的に、過去から長期間にわたる労働の対価の
後払いという性格を持っていることや、
退職後の老後の生活の原資に当てるべきもの
という性質のため、退職所得の金額は
他の所得とは分けて
(退職所得の金額−(※)退職所得控除額)×1/2
(※)退職所得控除額
勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合 800万円+70万円
×(勤続年数−20年)
という計算式により算出されていました。
しかし今回の税制改正により、
平成25年分以後の退職所得のうち、
特定役員退職手当等に該当するものの、
計算式は以下のようになります。
退職所得の金額−退職所得控除額
つまり、2分の1課税の制度が廃止されました。
ここにいう特定役員退職手当等とは、
退職手当等のうち、役員等勤続年数が
5年以下の
?法人税法に規定する役員
?国会議員及び地方公共団体の議会の議員
?国家公務員及び地方公務員
が支払いを受けるものを言います。
**参考**
(退職所得)
所得税法第三十条
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により
一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与
(以下この条において「退職手当等」という。)に
係る所得をいう。
2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の
収入金額から退職所得控除額を控除した残額の
二分の一に相当する金額とする。
3 前項に規定する退職所得控除額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に掲げる金額とする。
一 政令で定める勤続年数(以下この項において
「勤続年数」という。)が二十年以下である場合
四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
二 勤続年数が二十年を超える場合
八百万円と七十万円に当該勤続年数から
二十年を控除した年数を乗じて計算した金額
との合計額
4 次の各号に掲げる場合に該当するときは、
第二項に規定する退職所得控除額は、
前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
一 その年の前年以前に他の退職手当等の
支払を受けている場合で政令で定める場合
前項の規定により計算した金額から、
当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより
同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
二 前項及び前号の規定により計算した金額が
八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。)
八十万円
三 障害者になつたことに直接基因して退職したと
認められる場合で政令で定める場合
前項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が
八十万円に満たない場合には、八十万円)に
百万円を加算した金額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月10日
源泉所得税がある場合の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
例えば税理士に報酬を支払う場合、
対価の額から源泉所得税を控除して、
控除後の金額を税理士へ、
源泉徴収した金額を国へ納付することとなりますが、
この場合、消費税は源泉所得税を控除する前の
金額に対して計算するのでしょうか?
それとも源泉所得税を控除した後の金額に
対して計算するのでしょうか?
結論から言うと、源泉所得税を控除
する前の金額に対して消費税の計算を
行うこととなります。
これは源泉所得税は、その役務の対価の
一部に過ぎず、その対価としての金額は
源泉所得税控除前の金額であるため、
役務の対価全体に対して消費税の計算を
行うためです。
**参考**
(源泉所得税がある場合の課税標準)
消費税法基本通達10−1−13
事業者が課税資産の譲渡等に際して
収受する金額が、源泉所得税に
相当する金額を控除した残額
である場合であっても、源泉徴収前の
金額によって消費税の課税関係を
判定するのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

例えば税理士に報酬を支払う場合、
対価の額から源泉所得税を控除して、
控除後の金額を税理士へ、
源泉徴収した金額を国へ納付することとなりますが、
この場合、消費税は源泉所得税を控除する前の
金額に対して計算するのでしょうか?
それとも源泉所得税を控除した後の金額に
対して計算するのでしょうか?
結論から言うと、源泉所得税を控除
する前の金額に対して消費税の計算を
行うこととなります。
これは源泉所得税は、その役務の対価の
一部に過ぎず、その対価としての金額は
源泉所得税控除前の金額であるため、
役務の対価全体に対して消費税の計算を
行うためです。
**参考**
(源泉所得税がある場合の課税標準)
消費税法基本通達10−1−13
事業者が課税資産の譲渡等に際して
収受する金額が、源泉所得税に
相当する金額を控除した残額
である場合であっても、源泉徴収前の
金額によって消費税の課税関係を
判定するのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月09日
配送料を別途収受した場合、消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
通信販売や、お客さんからの注文により
販売した商品の発送代行を行う商売を
行っている人も多いと思いますが、
このような場合に、商品代とは別に配送料を
もらう場合、この配送料は消費税の課税対象と
なるのでしょうか?
例えば、母の日に花屋さんが花を販売し、
母の日にその販売した花を届けてくれる
というサービスを行った場合、
その配送料を別途もらった場合、
その配送という業務を自社で行うのか、
宅配業者等に依頼するのかにより
異なります。
もしこの配送を自社で行っている場合、
別途収受した配送料も、配送という
役務の提供に対する対価となりますので、
消費税の課税対象となります。
しかし、配送は自社で行わず、専門業者等へ
配送を依頼し、購入者から預る配送料は実費のみを
預り(税込み)、帳簿上も預った配送料を仮受金等と
処理し、配送料支払いの際には仮受金等から
支払うという処理を行い、損益に影響を
与えていない場合には、
その配送料は単に預ったものとして、
消費税の課税対象としなくてもOKです。
配送を誰が行うのか、
配送料を実費でいただき、処理も仮受金等で
処理をしている等により、
取り扱いが異なりますので、注意してください。
**参考**
(別途収受する配送料等)
消費税法基本通達10−1−16
事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、
他の者に委託する配送等に係る料金を
課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、
当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、
当該料金は、当該事業者における
課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして
差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

通信販売や、お客さんからの注文により
販売した商品の発送代行を行う商売を
行っている人も多いと思いますが、
このような場合に、商品代とは別に配送料を
もらう場合、この配送料は消費税の課税対象と
なるのでしょうか?
例えば、母の日に花屋さんが花を販売し、
母の日にその販売した花を届けてくれる
というサービスを行った場合、
その配送料を別途もらった場合、
その配送という業務を自社で行うのか、
宅配業者等に依頼するのかにより
異なります。
もしこの配送を自社で行っている場合、
別途収受した配送料も、配送という
役務の提供に対する対価となりますので、
消費税の課税対象となります。
しかし、配送は自社で行わず、専門業者等へ
配送を依頼し、購入者から預る配送料は実費のみを
預り(税込み)、帳簿上も預った配送料を仮受金等と
処理し、配送料支払いの際には仮受金等から
支払うという処理を行い、損益に影響を
与えていない場合には、
その配送料は単に預ったものとして、
消費税の課税対象としなくてもOKです。
配送を誰が行うのか、
配送料を実費でいただき、処理も仮受金等で
処理をしている等により、
取り扱いが異なりますので、注意してください。
**参考**
(別途収受する配送料等)
消費税法基本通達10−1−16
事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、
他の者に委託する配送等に係る料金を
課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、
当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、
当該料金は、当該事業者における
課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして
差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月08日
寄付金に対する消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業者が金銭の寄付を行った場合には
その支出に対して反対給付がない等の
理由により、消費税は課税されません。
ではこの寄付が金銭以外のものによる
寄付の場合、消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょう?
例えば車両を購入し、その車両を寄付した場合、
その車両の寄付については金銭の場合と同様に、
反対給付がない等の理由により、
消費税法施行令2条1項1号に規定する
負担付贈与による資産の譲渡に該当し無い限り
消費税は課税されません。
しかし、その車両を購入してきた際には、
消費税法上における「仕入」に該当するため、
消費税の仕入税額控除に該当することとなります。
**参考**
(資産の譲渡等の範囲)
消費税法施行令第二条
法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 負担付き贈与による資産の譲渡
(寄附金、祝金、見舞金等)
消費税法基本通達5−2−14
寄附金、祝金、見舞金等は原則として
資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
その譲渡等に係る対価を受領するとともに
別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと
認められるときは、その受領した金銭は
その資産の譲渡等の対価に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

事業者が金銭の寄付を行った場合には
その支出に対して反対給付がない等の
理由により、消費税は課税されません。
ではこの寄付が金銭以外のものによる
寄付の場合、消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょう?
例えば車両を購入し、その車両を寄付した場合、
その車両の寄付については金銭の場合と同様に、
反対給付がない等の理由により、
消費税法施行令2条1項1号に規定する
負担付贈与による資産の譲渡に該当し無い限り
消費税は課税されません。
しかし、その車両を購入してきた際には、
消費税法上における「仕入」に該当するため、
消費税の仕入税額控除に該当することとなります。
**参考**
(資産の譲渡等の範囲)
消費税法施行令第二条
法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 負担付き贈与による資産の譲渡
(寄附金、祝金、見舞金等)
消費税法基本通達5−2−14
寄附金、祝金、見舞金等は原則として
資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
その譲渡等に係る対価を受領するとともに
別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと
認められるときは、その受領した金銭は
その資産の譲渡等の対価に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月07日
給与所得控除の上限設定とは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
平成25年分以後の所得税について、
給与所得控除額に上限が設定されることと
なりました。
今までは、給与の収入金額の区分に応じそれぞれ
以下のように定められていました。
180万円以下
→ 給与の収入金額×40%
その金額が65万円以下の場合には65万円
180万円超 360万円以下
→ 給与の収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下
→ 給与の収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下
→ 給与の収入金額×10%+120万円
1,000万円超
→ 給与の収入金額×5%+170万円
と今までは上限無く収入金額が増えれば
それに伴い給与所得控除額も増える
仕組みになっていましたが、
給与所得が1,500万円を超える場合には
給与所得控除額が245万円の上限が
設けられることとなりました。
これに伴い、上記の表は以下のようになります。
180万円以下
→ 給与の収入金額×40%
その金額が65万円以下の場合には65万円
180万円超 360万円以下
→ 給与の収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下
→ 給与の収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下
→ 給与の収入金額×10%+120万円
1,000万円超 1,500万円以下
→ 給与の収入金額×5%+170万円
1,500万円超
→ 245万円
年間で1,500万円以上の給与所得がある方は
注意してください。
**参考**
(給与所得)
所得税法第二十八条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びに
これらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」
という。)に係る所得をいう。
2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から
給与所得控除額を控除した残額とする。
3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に
掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合
当該収入金額の百分の四十に相当する金額
(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円)
二 前項に規定する収入金額が百八十万円を超え
三百六十万円以下である場合
七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の
百分の三十に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え
六百六十万円以下である場合
百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を
控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え
千万円以下である場合
百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を
控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
五 前項に規定する収入金額が千万円を超え
千五百万円以下である場合
二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した
金額の百分の五に相当する金額との合計額
六 前項に規定する収入金額が千五百万円を超える場合
二百四十五万円
4 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満
である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、
前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を
別表第五の給与等の金額として、同表により
当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の
給与等の金額に相当する金額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

平成25年分以後の所得税について、
給与所得控除額に上限が設定されることと
なりました。
今までは、給与の収入金額の区分に応じそれぞれ
以下のように定められていました。
180万円以下
→ 給与の収入金額×40%
その金額が65万円以下の場合には65万円
180万円超 360万円以下
→ 給与の収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下
→ 給与の収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下
→ 給与の収入金額×10%+120万円
1,000万円超
→ 給与の収入金額×5%+170万円
と今までは上限無く収入金額が増えれば
それに伴い給与所得控除額も増える
仕組みになっていましたが、
給与所得が1,500万円を超える場合には
給与所得控除額が245万円の上限が
設けられることとなりました。
これに伴い、上記の表は以下のようになります。
180万円以下
→ 給与の収入金額×40%
その金額が65万円以下の場合には65万円
180万円超 360万円以下
→ 給与の収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下
→ 給与の収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下
→ 給与の収入金額×10%+120万円
1,000万円超 1,500万円以下
→ 給与の収入金額×5%+170万円
1,500万円超
→ 245万円
年間で1,500万円以上の給与所得がある方は
注意してください。
**参考**
(給与所得)
所得税法第二十八条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びに
これらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」
という。)に係る所得をいう。
2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から
給与所得控除額を控除した残額とする。
3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に
掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合
当該収入金額の百分の四十に相当する金額
(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円)
二 前項に規定する収入金額が百八十万円を超え
三百六十万円以下である場合
七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の
百分の三十に相当する金額との合計額
三 前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え
六百六十万円以下である場合
百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を
控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
四 前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え
千万円以下である場合
百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を
控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
五 前項に規定する収入金額が千万円を超え
千五百万円以下である場合
二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した
金額の百分の五に相当する金額との合計額
六 前項に規定する収入金額が千五百万円を超える場合
二百四十五万円
4 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満
である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、
前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を
別表第五の給与等の金額として、同表により
当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の
給与等の金額に相当する金額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年08月06日
遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
働き盛りでバリバリ働いている方が、
不幸にも亡くなるということがあります。
その場合、その無くなるまでの期間の
労働に対する対価として、
給与が支払われたり、退職金が支払われたり
した場合、この給与や退職金等は
税務上どのように取り扱われるのでしょうか?
亡くなった方にかかる給与等、公的年金等及び
退職手当等で亡くなった後に支給期が到来する
ものについては、
相続税法の規定により相続税の課税価額計算の
基礎に算入されるものは所得税は非課税となり、
それ以外のものはその支払いを受ける遺族の
一時所得として、所得税が課税されます。
相続財産となるものとしては、被相続人の死亡後
3年以内に支給が確定した退職手当等が該当します。
**参考**
(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
所得税法基本通達9−17
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等
(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、
その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により
相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
課税しないものとする。
(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、
直法6−9、直資3−8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の
支給期については、36−9、36−10及び36−14の(1)に
定めるところによる。
(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
所得税法基本通達34−2
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、
その死亡後に支給期の到来するもののうち9−17により
課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、
その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。
(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、
直法6−9、直資3−8改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

働き盛りでバリバリ働いている方が、
不幸にも亡くなるということがあります。
その場合、その無くなるまでの期間の
労働に対する対価として、
給与が支払われたり、退職金が支払われたり
した場合、この給与や退職金等は
税務上どのように取り扱われるのでしょうか?
亡くなった方にかかる給与等、公的年金等及び
退職手当等で亡くなった後に支給期が到来する
ものについては、
相続税法の規定により相続税の課税価額計算の
基礎に算入されるものは所得税は非課税となり、
それ以外のものはその支払いを受ける遺族の
一時所得として、所得税が課税されます。
相続財産となるものとしては、被相続人の死亡後
3年以内に支給が確定した退職手当等が該当します。
**参考**
(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
所得税法基本通達9−17
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等
(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、
その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により
相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
課税しないものとする。
(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、
直法6−9、直資3−8改正)
(注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の
支給期については、36−9、36−10及び36−14の(1)に
定めるところによる。
(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
所得税法基本通達34−2
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、
その死亡後に支給期の到来するもののうち9−17により
課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、
その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。
(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、
直法6−9、直資3−8改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました




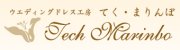


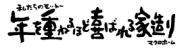




 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン





