2011年04月28日
使途を明らかに出来ない金銭の支出を行った場合
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人が金銭などの支出を行う場合において、
その支出した相手方を明らかに出来ない
と言う場合があるかと思います。
そのような場合、
この相手方を明らかに出来ない支払は
どのように取り扱われるのでしょう?
このような使途を明らかに出来ない支出
については、違法支出や不正支出となり
易く、公正な取引を阻害する結果となります。
そこで税務上では、このような取引を
排除することを目的として、
使途秘匿金の支出については、
追加課税制度を採用しています。
これはどのような制度かというと、
法人が平成6年4月1日から平成24年3月31日
までの間に使途秘匿金を支出した場合には、
その支出をした事業年度の法人税の額に、
その支出をした使途秘匿金の額の40%相当額を
加算すると言う制度です。
**参考**
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
租税特別措置法第六十二条
法人(法人税法第二条第五号 に規定する
公共法人を除く。以下この項において同じ。)
は、その使途秘匿金の支出について
法人税を納める義務があるものとし、
法人が平成六年四月一日から
平成二十四年三月三十一日までの間に
使途秘匿金の支出をした場合には、
当該法人に対して課する各事業年度の
所得に対する法人税の額は、
同法第六十六条第一項 から第三項 まで
並びに第百四十三条第一項 及び第二項
並びに第四十二条の四第十一項
(第四十二条の四の二第七項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。)、
第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、
第四十二条の十第五項、第六十二条の三第一項
及び第八項、第六十三条第一項、
第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項
その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を
乗じて計算した金額を加算した金額とする。
また使途秘匿金の支出は、法人税法上
損金の額に含まれませんので
その使途秘匿金に関しては、
通常の法人税等と追加分の税金が
発生するようになります。
これの税率を見てみると、
法人税率を30%と仮定すると、
約87.8%の税金がかかることとなります。
**参考**
(費途不明の交際費等)
法人税法基本通達9−7−20
法人が交際費、機密費、接待費等の
名義をもって支出した金銭で
その費途が明らかでないものは、
損金の額に算入しない。
(昭46年直審(法)20「9」、
昭55年直法2−15「十六」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

法人が金銭などの支出を行う場合において、
その支出した相手方を明らかに出来ない
と言う場合があるかと思います。
そのような場合、
この相手方を明らかに出来ない支払は
どのように取り扱われるのでしょう?
このような使途を明らかに出来ない支出
については、違法支出や不正支出となり
易く、公正な取引を阻害する結果となります。
そこで税務上では、このような取引を
排除することを目的として、
使途秘匿金の支出については、
追加課税制度を採用しています。
これはどのような制度かというと、
法人が平成6年4月1日から平成24年3月31日
までの間に使途秘匿金を支出した場合には、
その支出をした事業年度の法人税の額に、
その支出をした使途秘匿金の額の40%相当額を
加算すると言う制度です。
**参考**
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
租税特別措置法第六十二条
法人(法人税法第二条第五号 に規定する
公共法人を除く。以下この項において同じ。)
は、その使途秘匿金の支出について
法人税を納める義務があるものとし、
法人が平成六年四月一日から
平成二十四年三月三十一日までの間に
使途秘匿金の支出をした場合には、
当該法人に対して課する各事業年度の
所得に対する法人税の額は、
同法第六十六条第一項 から第三項 まで
並びに第百四十三条第一項 及び第二項
並びに第四十二条の四第十一項
(第四十二条の四の二第七項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。)、
第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、
第四十二条の十第五項、第六十二条の三第一項
及び第八項、第六十三条第一項、
第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項
その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、
これらの規定により計算した法人税の額に、
当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を
乗じて計算した金額を加算した金額とする。
また使途秘匿金の支出は、法人税法上
損金の額に含まれませんので
その使途秘匿金に関しては、
通常の法人税等と追加分の税金が
発生するようになります。
これの税率を見てみると、
法人税率を30%と仮定すると、
約87.8%の税金がかかることとなります。
**参考**
(費途不明の交際費等)
法人税法基本通達9−7−20
法人が交際費、機密費、接待費等の
名義をもって支出した金銭で
その費途が明らかでないものは、
損金の額に算入しない。
(昭46年直審(法)20「9」、
昭55年直法2−15「十六」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月27日
未使用の減価償却資産は償却できる?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
新たな商品の製造に取り掛かるため
工場で使用する機械を購入した場合に
突発的に理由などにより
生産を延期しなければならなくなった場合、
まだ使用していないこの機械は
減価償却することが出来るのでしょうか?
減価償却資産の償却開始時期は、
『事業の用に供した時』となります。
つまり、この機械であれば、
新製品を作る為に稼動しだして
初めて減価償却を行うことができます。
そのため今回のような未使用の場合、
減価償却資産は償却が出来ませんので
ご注意下さい。
この要件は、
『少額減価償却資産の取得価額の損金算入』
『中小企業者に対する少額減価償却資産の特例』
『一括償却資産』
についても同様となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

新たな商品の製造に取り掛かるため
工場で使用する機械を購入した場合に
突発的に理由などにより
生産を延期しなければならなくなった場合、
まだ使用していないこの機械は
減価償却することが出来るのでしょうか?
減価償却資産の償却開始時期は、
『事業の用に供した時』となります。
つまり、この機械であれば、
新製品を作る為に稼動しだして
初めて減価償却を行うことができます。
そのため今回のような未使用の場合、
減価償却資産は償却が出来ませんので
ご注意下さい。
この要件は、
『少額減価償却資産の取得価額の損金算入』
『中小企業者に対する少額減価償却資産の特例』
『一括償却資産』
についても同様となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月26日
損害賠償金の会社負担について
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社の役員や使用人が行った行為により、
他人に損害を与えた場合、
損害賠償を請求されることがあります。
こういった場合に、会社がその役員や使用人の
損害賠償金を負担した場合には税務上
どのように取り扱われるのでしょう?
こういった場合、その行為などの状況により
取扱は異なります。
それではそれぞれのケースによって
見て行きましょう。
?その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合。
この場合には法人の負担した損害賠償金は
給与以外の経費として損金算入することが
できます。
?その損害賠償金の対象となった行為等が、
法人の業務の遂行に関連するものであるが
故意又は重過失に基づくものである場合
又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合。
この場合にはその支出した損害賠償金に
相当する金額は当該役員又は使用人に
対する債権として取り扱われます。
そしてこの場合、その行為等を行った
役員又は使用人の支払い能力などからみて
この債権をその役員又は使用人から
求償することができない事情にあるときは、
その債権の全部又は一部に相当する金額を
貸倒等として損金の額に算入することが
できます。
ただし、その貸倒等として処理した金額のうち
その役員又は使用人から回収が出来ると
認められる金額がある場合には、
その部分は給与として取り扱うこととなります。
**参考**
(法人が支出した役員等の損害賠償金)
法人税法基本通達9−7−16
法人の役員又は使用人がした行為等によって
他人に与えた損害につき法人が
その損害賠償金を支出した場合には、次による。
(1) その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかないもの
である場合には、その支出した
損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。
(2) その損害賠償金の対象となった行為等が、
法人の業務の遂行に関連するものであるが
故意又は重過失に基づくものである場合
又は法人の業務の遂行に関連しないもの
である場合には、その支出した損害賠償金に
相当する金額は当該役員又は使用人に対する債権とする。
(損害賠償金に係る債権の処理)
法人税法基本通達9−7−17
法人が、9−7−16(2)に定める債権につき、
その役員又は使用人の支払能力等からみて
求償できない事情にあるため、
その全部又は一部に相当する金額を
貸倒れとして損金経理をした場合
(9−7−16(2)の損害賠償金相当額を債権として
計上しないで損金の額に算入した場合を含む。)
には、これを認める。
ただし、当該貸倒れ等とした金額のうち
その役員又は使用人の支払能力等からみて
回収が確実であると認められる部分の金額については、
これを当該役員又は使用人に対する給与とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

会社の役員や使用人が行った行為により、
他人に損害を与えた場合、
損害賠償を請求されることがあります。
こういった場合に、会社がその役員や使用人の
損害賠償金を負担した場合には税務上
どのように取り扱われるのでしょう?
こういった場合、その行為などの状況により
取扱は異なります。
それではそれぞれのケースによって
見て行きましょう。
?その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかないものである場合。
この場合には法人の負担した損害賠償金は
給与以外の経費として損金算入することが
できます。
?その損害賠償金の対象となった行為等が、
法人の業務の遂行に関連するものであるが
故意又は重過失に基づくものである場合
又は法人の業務の遂行に関連しないものである場合。
この場合にはその支出した損害賠償金に
相当する金額は当該役員又は使用人に
対する債権として取り扱われます。
そしてこの場合、その行為等を行った
役員又は使用人の支払い能力などからみて
この債権をその役員又は使用人から
求償することができない事情にあるときは、
その債権の全部又は一部に相当する金額を
貸倒等として損金の額に算入することが
できます。
ただし、その貸倒等として処理した金額のうち
その役員又は使用人から回収が出来ると
認められる金額がある場合には、
その部分は給与として取り扱うこととなります。
**参考**
(法人が支出した役員等の損害賠償金)
法人税法基本通達9−7−16
法人の役員又は使用人がした行為等によって
他人に与えた損害につき法人が
その損害賠償金を支出した場合には、次による。
(1) その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかないもの
である場合には、その支出した
損害賠償金の額は給与以外の損金の額に算入する。
(2) その損害賠償金の対象となった行為等が、
法人の業務の遂行に関連するものであるが
故意又は重過失に基づくものである場合
又は法人の業務の遂行に関連しないもの
である場合には、その支出した損害賠償金に
相当する金額は当該役員又は使用人に対する債権とする。
(損害賠償金に係る債権の処理)
法人税法基本通達9−7−17
法人が、9−7−16(2)に定める債権につき、
その役員又は使用人の支払能力等からみて
求償できない事情にあるため、
その全部又は一部に相当する金額を
貸倒れとして損金経理をした場合
(9−7−16(2)の損害賠償金相当額を債権として
計上しないで損金の額に算入した場合を含む。)
には、これを認める。
ただし、当該貸倒れ等とした金額のうち
その役員又は使用人の支払能力等からみて
回収が確実であると認められる部分の金額については、
これを当該役員又は使用人に対する給与とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月25日
リクエストにお答えします!!
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
本日は金曜日にコメントでリクエストを
寄せていただきましたので、
その内容についてお答えしたいと思います。
Q:「同族会社の社長の息子
(役員をしているものとします)
が会社の金で株式投資をして、
それで大穴を開けた時の財務処理」
はどのような処理になるのですか?
A:その株式投資の状況が詳しく分かりませんので、
想定できる状況に応じて、基本的な取扱を
回答していきます。
?会社の経営方針に則り株式投資を行い
失敗した場合には、その損失部分は
会社の経費として処理できるものと思われます。
?会社の経営方針に則らない、または、
個人的な株式投資を会社のお金で
行ったと認められる場合には、
その後の会社の取る方法により
損害賠償をとして請求する場合、
その役員に対する貸付となる場合、
その役員の賞与となる場合の
3パターンに分かれると思われます。
株式投資は通常、会社が行う業務とは異なり、
会社の余裕資金であったりを有利に運用し
会社に利益をもたらそうとするものと
考えられます。
そのため、通常は株式投資などは
取締役会の決議などの経営方針会議を行い
会社の経営方針として行って行く物で
あるため、同族会社の社長の息子である
役員であれ、他の役員であれ、
その取引によって発生する損益については
会社に帰属するものであると考えられる為、
有価証券売却損益・運用損益などとし
会社の損益として認められると思われます。
しかし、これが取締役会などの決議を経ず、
その役員が独断で行ったものであると
認められる場合には、その役員は
損害賠償責任を負うことになります。
損害賠償請求を会社が行った場合、
その損害賠償額が決定するまでは
その損失額は繰り延べられ、
その損害賠償額が確定した際に
損失額と同額までは相殺され、
損失額に届かなかった部分は
損失として損金処理されると
思われます。
また、損失額が少なく、
会社としても世間体などを考慮し
事を荒立てたくない場合、
損害賠償請求を行わないことも
あるかと思います。
この場合には、その役員に
その損失額を返済する意思がある場合には
その役員に対する債権が発生し、
その損失額を返済する意思がない場合には
その役員に対する賞与となると思われます。
賞与とされる場合には会社は源泉徴収の義務
を負いますのでご注意下さい。
また、役員賞与は一定の場合を除き
損金不算入となります。
以上につきまして
ご回答させていただきます。
リクエストありがとうございました!
※ 税務は個別的事案により
取扱がことなりますので
あくまで参考としていただき、
実際にアクションを起こす際には
顧問税理士などにご相談の上、
処理を行ってください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

本日は金曜日にコメントでリクエストを
寄せていただきましたので、
その内容についてお答えしたいと思います。
Q:「同族会社の社長の息子
(役員をしているものとします)
が会社の金で株式投資をして、
それで大穴を開けた時の財務処理」
はどのような処理になるのですか?
A:その株式投資の状況が詳しく分かりませんので、
想定できる状況に応じて、基本的な取扱を
回答していきます。
?会社の経営方針に則り株式投資を行い
失敗した場合には、その損失部分は
会社の経費として処理できるものと思われます。
?会社の経営方針に則らない、または、
個人的な株式投資を会社のお金で
行ったと認められる場合には、
その後の会社の取る方法により
損害賠償をとして請求する場合、
その役員に対する貸付となる場合、
その役員の賞与となる場合の
3パターンに分かれると思われます。
株式投資は通常、会社が行う業務とは異なり、
会社の余裕資金であったりを有利に運用し
会社に利益をもたらそうとするものと
考えられます。
そのため、通常は株式投資などは
取締役会の決議などの経営方針会議を行い
会社の経営方針として行って行く物で
あるため、同族会社の社長の息子である
役員であれ、他の役員であれ、
その取引によって発生する損益については
会社に帰属するものであると考えられる為、
有価証券売却損益・運用損益などとし
会社の損益として認められると思われます。
しかし、これが取締役会などの決議を経ず、
その役員が独断で行ったものであると
認められる場合には、その役員は
損害賠償責任を負うことになります。
損害賠償請求を会社が行った場合、
その損害賠償額が決定するまでは
その損失額は繰り延べられ、
その損害賠償額が確定した際に
損失額と同額までは相殺され、
損失額に届かなかった部分は
損失として損金処理されると
思われます。
また、損失額が少なく、
会社としても世間体などを考慮し
事を荒立てたくない場合、
損害賠償請求を行わないことも
あるかと思います。
この場合には、その役員に
その損失額を返済する意思がある場合には
その役員に対する債権が発生し、
その損失額を返済する意思がない場合には
その役員に対する賞与となると思われます。
賞与とされる場合には会社は源泉徴収の義務
を負いますのでご注意下さい。
また、役員賞与は一定の場合を除き
損金不算入となります。
以上につきまして
ご回答させていただきます。
リクエストありがとうございました!
※ 税務は個別的事案により
取扱がことなりますので
あくまで参考としていただき、
実際にアクションを起こす際には
顧問税理士などにご相談の上、
処理を行ってください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月22日
道路等の使用許可は消費税がかかる?かからない?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
国又は地方公共団体等の有する道路などを
一般的使用行為以外の特別な使用行為により
使用をする場合、道路使用許可が必要となります。
特別な使用行為とはどのようなものかと言うと、
?道路において工事もしくは
作業をしようとする行為
?道路に石碑、広告板、アーチ等の
工作物を設けようとする行為
?場所を移動しないで、
道路に露店、屋台等を出そうとする行為
?道路において祭礼行事、
ロケーション等をしようとする行為
(警察庁HP参照)
つまりこういったことを行う場合に
道路使用許可が必要となります。
ではこの道路使用許可の申請費用には
消費税はかかるのでしょうか?
道路使用許可申請にかかる手数料は、
国又は地方公共団体への支払いであるため、
租税公課に該当し非課税となります。
また道路占有使用料は、
道路という敷地である土地の使用料
ともいうべき性格を有していることから
消費税は非課税となります。
**参考**
(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)
消費税法基本通達6−1−7
国又は地方公共団体等がその有する海浜地、
道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)
の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、
道路占用料又は河川占用料は、
いずれも土地の貸付けに係る対価に
該当するものとして取り扱う。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

国又は地方公共団体等の有する道路などを
一般的使用行為以外の特別な使用行為により
使用をする場合、道路使用許可が必要となります。
特別な使用行為とはどのようなものかと言うと、
?道路において工事もしくは
作業をしようとする行為
?道路に石碑、広告板、アーチ等の
工作物を設けようとする行為
?場所を移動しないで、
道路に露店、屋台等を出そうとする行為
?道路において祭礼行事、
ロケーション等をしようとする行為
(警察庁HP参照)
つまりこういったことを行う場合に
道路使用許可が必要となります。
ではこの道路使用許可の申請費用には
消費税はかかるのでしょうか?
道路使用許可申請にかかる手数料は、
国又は地方公共団体への支払いであるため、
租税公課に該当し非課税となります。
また道路占有使用料は、
道路という敷地である土地の使用料
ともいうべき性格を有していることから
消費税は非課税となります。
**参考**
(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)
消費税法基本通達6−1−7
国又は地方公共団体等がその有する海浜地、
道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)
の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、
道路占用料又は河川占用料は、
いずれも土地の貸付けに係る対価に
該当するものとして取り扱う。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月21日
外貨での取引を行った場合の換算方法
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人が外貨建で取引を行った場合、
その金額を円に換算する必要があります。
これは会計においても、税法においても
単位は全て“円”と定められているためです。
これは単位を統一することにより、
会計上は、投資家などに誤った判断をさせないように、
税法上は、課税の公平を図るために、
すべて“円”と定められています。
**参考**
(外貨建取引の換算)
法人税法第六十一条の八
内国法人が外貨建取引(外国通貨で
支払が行われる資産の販売及び購入、
役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、
剰余金の配当その他の取引をいう。
以下この目において同じ。)を
行つた場合には、
当該外貨建取引の金額の円換算額
(外国通貨で表示された金額を
本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。
以下この目において同じ。)は、
当該外貨建取引を行つた時における
外国為替の売買相場により換算した金額とする。
でこの際に用いられる売買相場は、
T.T.M(電信売相場と電信買相場の中値)
によりおこなわれます。
ただし、継続適用の条件を満たす場合に限り、
売上その他の収益又は資産については
取引日のT.T.B(電信買相場)、
仕入れその他の費用(原価及び損失を含みます)
又は負債については取引日のT.T.S(電信売相場)
によることも出来ます。
**参考**
(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)
法人税法基本通達13の2−1−2
法第61条の8第1項《外貨建取引の換算》
及び法第61条の9第1項第1号イ
《発生時換算法の意義》の規定に基づく
円換算(法第61条の8第2項の規定の適用を
受ける場合の円換算を除く。)は、
その取引を計上すべき日(以下この章において
「取引日」という。)における
対顧客直物電信売相場(以下この章において
「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場
(以下この章において「電信買相場」という。)
の仲値(以下この章において「電信売買相場の仲値」
という。)による。
ただし、継続適用を条件として、
売上その他の収益又は資産については
取引日の電信買相場、仕入その他の費用
(原価及び損失を含む。以下この章において同じ。)
又は負債については取引日の電信売相場
によることができるものとする。
(平12年課法2−7「十九」により追加、
平12年課法2−19「十五」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

法人が外貨建で取引を行った場合、
その金額を円に換算する必要があります。
これは会計においても、税法においても
単位は全て“円”と定められているためです。
これは単位を統一することにより、
会計上は、投資家などに誤った判断をさせないように、
税法上は、課税の公平を図るために、
すべて“円”と定められています。
**参考**
(外貨建取引の換算)
法人税法第六十一条の八
内国法人が外貨建取引(外国通貨で
支払が行われる資産の販売及び購入、
役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、
剰余金の配当その他の取引をいう。
以下この目において同じ。)を
行つた場合には、
当該外貨建取引の金額の円換算額
(外国通貨で表示された金額を
本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。
以下この目において同じ。)は、
当該外貨建取引を行つた時における
外国為替の売買相場により換算した金額とする。
でこの際に用いられる売買相場は、
T.T.M(電信売相場と電信買相場の中値)
によりおこなわれます。
ただし、継続適用の条件を満たす場合に限り、
売上その他の収益又は資産については
取引日のT.T.B(電信買相場)、
仕入れその他の費用(原価及び損失を含みます)
又は負債については取引日のT.T.S(電信売相場)
によることも出来ます。
**参考**
(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)
法人税法基本通達13の2−1−2
法第61条の8第1項《外貨建取引の換算》
及び法第61条の9第1項第1号イ
《発生時換算法の意義》の規定に基づく
円換算(法第61条の8第2項の規定の適用を
受ける場合の円換算を除く。)は、
その取引を計上すべき日(以下この章において
「取引日」という。)における
対顧客直物電信売相場(以下この章において
「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場
(以下この章において「電信買相場」という。)
の仲値(以下この章において「電信売買相場の仲値」
という。)による。
ただし、継続適用を条件として、
売上その他の収益又は資産については
取引日の電信買相場、仕入その他の費用
(原価及び損失を含む。以下この章において同じ。)
又は負債については取引日の電信売相場
によることができるものとする。
(平12年課法2−7「十九」により追加、
平12年課法2−19「十五」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月20日
購入契約をした建物を購入しなかった場合の違約金の取扱は?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
建物を購入する場合、
契約の際に手付金を支払います。
この手付金は、通常は購入代金の
一部前払いとして、
その建物を購入した際に、
購入代金から差引いてもらえます。
しかし、もしその建物を購入せず
その契約を解除した場合には
その手付金は違約金として
没収されてしまいます。
ではこの没収されてしまった
手付金(違約金)はどのように
取り扱うこととなるのでしょう?
これの取扱は以下のように定められています。
(固定資産の取得価額に
算入しないことができる費用の例示)
法人税法基本通達7−3−3の2
次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に
関連して支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に
算入しないことができる。
(昭50年直法2−21「19」により追加、
昭55年直法2−8「二十一」により改正)
(3) いったん締結した固定資産の
取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に
支出する違約金の額
契約を解除しただけの場合も、
契約を解除し、他の建物を購入した場合にも、
その手付金(違約金)は一時の損失として
取り扱うこととなります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

建物を購入する場合、
契約の際に手付金を支払います。
この手付金は、通常は購入代金の
一部前払いとして、
その建物を購入した際に、
購入代金から差引いてもらえます。
しかし、もしその建物を購入せず
その契約を解除した場合には
その手付金は違約金として
没収されてしまいます。
ではこの没収されてしまった
手付金(違約金)はどのように
取り扱うこととなるのでしょう?
これの取扱は以下のように定められています。
(固定資産の取得価額に
算入しないことができる費用の例示)
法人税法基本通達7−3−3の2
次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に
関連して支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に
算入しないことができる。
(昭50年直法2−21「19」により追加、
昭55年直法2−8「二十一」により改正)
(3) いったん締結した固定資産の
取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に
支出する違約金の額
契約を解除しただけの場合も、
契約を解除し、他の建物を購入した場合にも、
その手付金(違約金)は一時の損失として
取り扱うこととなります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月19日
借金をして建物を取得する場合の利息の取扱は?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
建物を購入する際に借金をして
購入することが多くありますが、
例えば、借金をして建設を始めた場合、
まだその建物が使用できる前から
借金の利息が発生することになります。
ではこの借入金の利息の取扱は
どうなるのでしょう?
この借入金の利息の取扱は
以下のように定められています。
(借入金の利子)
法人税法基本通達7−3−1の2
固定資産を取得するために借り入れた
借入金の利子の額は、
たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に
係るものであっても、
これを当該固定資産の取得価額に
算入しないことができるものとする。
(昭55年直法2−8「二十一」により追加)
(注) 借入金の利子の額を建設中の
固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、
当該利子の額は固定資産の取得価額に
算入されたことになる。
つまり、建物を購入するためにした借金の
利息のうち、建物使用前に発生した利息については
会社の判断により、『支払利息』として
経費にも出来るし、『建物の取得価額』に
含めることも出来ます。
と言うことは、その事業年度の節税
と言う観点から見ると、『支払利息』
として処理をすると、
その事業年度では節税となります。
ただし、利息を『支払利息』とするか
『建物の取得価額』とするかは、
その利息の支払をした事業年度で
選択ができるものであるため、
例えばその利息を支払った事業年度において
『建物の取得価額』としていたものを
翌事業年度において『支払利息』に
変更することは出来ません。
建物が完成するまでの間の勘定科目としての
『建設仮勘定』とした場合にも、
建物の取得価額に含めたものとされるため、
翌事業年度において、『支払利息』に
振り替えることは出来ませんので、
注意してください!!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

建物を購入する際に借金をして
購入することが多くありますが、
例えば、借金をして建設を始めた場合、
まだその建物が使用できる前から
借金の利息が発生することになります。
ではこの借入金の利息の取扱は
どうなるのでしょう?
この借入金の利息の取扱は
以下のように定められています。
(借入金の利子)
法人税法基本通達7−3−1の2
固定資産を取得するために借り入れた
借入金の利子の額は、
たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に
係るものであっても、
これを当該固定資産の取得価額に
算入しないことができるものとする。
(昭55年直法2−8「二十一」により追加)
(注) 借入金の利子の額を建設中の
固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、
当該利子の額は固定資産の取得価額に
算入されたことになる。
つまり、建物を購入するためにした借金の
利息のうち、建物使用前に発生した利息については
会社の判断により、『支払利息』として
経費にも出来るし、『建物の取得価額』に
含めることも出来ます。
と言うことは、その事業年度の節税
と言う観点から見ると、『支払利息』
として処理をすると、
その事業年度では節税となります。
ただし、利息を『支払利息』とするか
『建物の取得価額』とするかは、
その利息の支払をした事業年度で
選択ができるものであるため、
例えばその利息を支払った事業年度において
『建物の取得価額』としていたものを
翌事業年度において『支払利息』に
変更することは出来ません。
建物が完成するまでの間の勘定科目としての
『建設仮勘定』とした場合にも、
建物の取得価額に含めたものとされるため、
翌事業年度において、『支払利息』に
振り替えることは出来ませんので、
注意してください!!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月18日
駐車場用地を貸し付けた場合の消費税の取扱は?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
今、金曜日の投稿がUPされていない事に
気が付きました・・・(汗
な、何故でしょう・・・
とは言え、過ぎたことはしょうが無いので、
気分を入れ替えて、
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
消費税法上、土地の貸付は
非課税とされており、消費税は発生しません。
**参考**
(非課税)
消費税法第六条
国内において行われる資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
消費税法別表第一(第六条関係)
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の
譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合
その他の政令で定める場合を除く。)
これは、消費税は『消費』に対して
税金を課するものであり、
土地は消費するものでは無い
という考え方に則り非課税とされています。
しかし、土地の貸付が全て非課税かと言うと
そうではありません。
上記にもあるように、
『一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く』
とされています。
では駐車場を貸し付ける場合はどうでしょう?
駐車場の貸付が非課税になる場合は
?駐車している車両の管理をしていない
?駐車設備などを設置していない
を満たす場合です。
つまり、何ら管理をせず、
駐車設備のまったく無い更地を
駐車場として貸す場合には
土地の貸付として非課税になりますが、
例えば?の場合には、
車両を管理すると言う
役務の提供に対して消費税がかかります。
そして?の場合には、
駐車設備などの貸付として
消費税がかかります。
土地の貸付なので消費税はかからない
と安易に判断しないように、
十分注意してください。
**参考**
(土地付建物等の貸付け)
消費税法基本通達6−1−5
令第8条《土地の貸付けから除外される場合》
の規定により、施設の利用に伴って
土地が使用される場合のその土地を
使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、
例えば、建物、野球場、プール又は
テニスコート等の施設の利用が
土地の使用を伴うことになるとしても、
その土地の使用は、
土地の貸付けに含まれないことに留意する。
(注)
1事業者が駐車場又は駐輪場として
土地を利用させた場合において、
その土地につき駐車場又は
駐輪場としての用途に応じる
地面の整備又はフェンス、区画、
建物の設置等をしていないとき
(駐車又は駐輪に係る車両又は
自転車の管理をしている場合を除く。)
は、その土地の使用は、
土地の貸付けに含まれる。
2建物その他の施設の貸付け又は
役務の提供(以下6−1−5において
「建物の貸付け等」という。)
に伴って土地を使用させた場合において、
建物の貸付け等に係る対価と
土地の貸付けに係る対価とに
区分しているときであっても、
その対価の額の合計額が
当該建物の貸付け等に係る
対価の額となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
今、金曜日の投稿がUPされていない事に
気が付きました・・・(汗
な、何故でしょう・・・
とは言え、過ぎたことはしょうが無いので、
気分を入れ替えて、
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

消費税法上、土地の貸付は
非課税とされており、消費税は発生しません。
**参考**
(非課税)
消費税法第六条
国内において行われる資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
消費税法別表第一(第六条関係)
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の
譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合
その他の政令で定める場合を除く。)
これは、消費税は『消費』に対して
税金を課するものであり、
土地は消費するものでは無い
という考え方に則り非課税とされています。
しかし、土地の貸付が全て非課税かと言うと
そうではありません。
上記にもあるように、
『一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く』
とされています。
では駐車場を貸し付ける場合はどうでしょう?
駐車場の貸付が非課税になる場合は
?駐車している車両の管理をしていない
?駐車設備などを設置していない
を満たす場合です。
つまり、何ら管理をせず、
駐車設備のまったく無い更地を
駐車場として貸す場合には
土地の貸付として非課税になりますが、
例えば?の場合には、
車両を管理すると言う
役務の提供に対して消費税がかかります。
そして?の場合には、
駐車設備などの貸付として
消費税がかかります。
土地の貸付なので消費税はかからない
と安易に判断しないように、
十分注意してください。
**参考**
(土地付建物等の貸付け)
消費税法基本通達6−1−5
令第8条《土地の貸付けから除外される場合》
の規定により、施設の利用に伴って
土地が使用される場合のその土地を
使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、
例えば、建物、野球場、プール又は
テニスコート等の施設の利用が
土地の使用を伴うことになるとしても、
その土地の使用は、
土地の貸付けに含まれないことに留意する。
(注)
1事業者が駐車場又は駐輪場として
土地を利用させた場合において、
その土地につき駐車場又は
駐輪場としての用途に応じる
地面の整備又はフェンス、区画、
建物の設置等をしていないとき
(駐車又は駐輪に係る車両又は
自転車の管理をしている場合を除く。)
は、その土地の使用は、
土地の貸付けに含まれる。
2建物その他の施設の貸付け又は
役務の提供(以下6−1−5において
「建物の貸付け等」という。)
に伴って土地を使用させた場合において、
建物の貸付け等に係る対価と
土地の貸付けに係る対価とに
区分しているときであっても、
その対価の額の合計額が
当該建物の貸付け等に係る
対価の額となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月14日
個人事業者が生活用資産を売却したら消費税の取扱は?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人事業を営まれている方も
課税事業者となれば消費税を
納めなければなりません。
つまり商品などを販売すると
消費税を預ることとなり、
毎年3月31日までに、
消費税の申告と納税を行います。
では、個人で事業を営まれている方が
生活用資産を売却した場合も
消費税を預ることとなり、
毎年3月31日までに、
消費税の申告と納税をわなければ
ならないのでしょうか?
消費税の課税対象となる取引は、
『事業者が事業として対価を得て
行う資産の譲渡等』と定められています。
つまり、生活用資産の売却は
事業として行うものではないため、
消費税はかかりません。
たとえば、
個人事業者が自家用車を
販売したような場合には、
その販売した自家用車に
かかる部分については
消費税は発生しません。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

個人事業を営まれている方も
課税事業者となれば消費税を
納めなければなりません。
つまり商品などを販売すると
消費税を預ることとなり、
毎年3月31日までに、
消費税の申告と納税を行います。
では、個人で事業を営まれている方が
生活用資産を売却した場合も
消費税を預ることとなり、
毎年3月31日までに、
消費税の申告と納税をわなければ
ならないのでしょうか?
消費税の課税対象となる取引は、
『事業者が事業として対価を得て
行う資産の譲渡等』と定められています。
つまり、生活用資産の売却は
事業として行うものではないため、
消費税はかかりません。
たとえば、
個人事業者が自家用車を
販売したような場合には、
その販売した自家用車に
かかる部分については
消費税は発生しません。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月13日
所有期間に応じて按分した固定資産税の取扱は?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
中古の建物を購入した場合、
その契約引渡し日から12月31日までの
固定資産税を負担することと
されている契約が多くあると思います。
これは前所有者が1年分の
固定資産税を支払っているため
所有期間に応じてそれぞれが
負担しようとするものです。
では、この固定資産税の
負担按分部分、不動産の購入時に
負担した場合どのように
取り扱うのでしょう?
これ固定資産税だから
『租税公課』と思っている人が
とても多いのですが、
実はこの負担部分は
租税公課ではなく、
建物の取得価額に含まれるのです。
なぜこのような取扱になるのか?
実はこの固定資産税の負担部分、
名目上固定資産税の負担部分と
されているだけで、
固定資産税ではないのです。
どういうことかというと、
固定資産税の納税義務者(税金を
支払う義務がある人)は、
その年の1月1日時点における
土地・建物等の所有者と決められているのです。
つまり、固定資産税として
支払ができるのは1月1日の時点で
土地・建物等の所有者だけなのです。
そのため、年の途中で購入した方は
固定資産税の支払と言う名目なだけで、
固定資産税を支払わなくても良い部分の
金額を土地・建物等の価格に
上乗せされた分を支払っているに
過ぎないのです。
そのため、
名目上が固定資産税の所有期間における
按分部分の負担とされていても、
租税公課として経費となるのではなく、
資産の取得価額として
減価償却を通じて、各事業年度の
経費となるので注意して下さいね!
**参考**
(固定資産の取得価額に
算入しないことができる費用の例示)
法人税法基本通達7−3−3の2
次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に関連して
支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に
算入しないことができる。
(昭50年直法2−21「19」により追加、
昭55年直法2−8「二十一」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち
土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は
登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、
測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより
不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の
取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に
支出する違約金の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

中古の建物を購入した場合、
その契約引渡し日から12月31日までの
固定資産税を負担することと
されている契約が多くあると思います。
これは前所有者が1年分の
固定資産税を支払っているため
所有期間に応じてそれぞれが
負担しようとするものです。
では、この固定資産税の
負担按分部分、不動産の購入時に
負担した場合どのように
取り扱うのでしょう?
これ固定資産税だから
『租税公課』と思っている人が
とても多いのですが、
実はこの負担部分は
租税公課ではなく、
建物の取得価額に含まれるのです。
なぜこのような取扱になるのか?
実はこの固定資産税の負担部分、
名目上固定資産税の負担部分と
されているだけで、
固定資産税ではないのです。
どういうことかというと、
固定資産税の納税義務者(税金を
支払う義務がある人)は、
その年の1月1日時点における
土地・建物等の所有者と決められているのです。
つまり、固定資産税として
支払ができるのは1月1日の時点で
土地・建物等の所有者だけなのです。
そのため、年の途中で購入した方は
固定資産税の支払と言う名目なだけで、
固定資産税を支払わなくても良い部分の
金額を土地・建物等の価格に
上乗せされた分を支払っているに
過ぎないのです。
そのため、
名目上が固定資産税の所有期間における
按分部分の負担とされていても、
租税公課として経費となるのではなく、
資産の取得価額として
減価償却を通じて、各事業年度の
経費となるので注意して下さいね!
**参考**
(固定資産の取得価額に
算入しないことができる費用の例示)
法人税法基本通達7−3−3の2
次に掲げるような費用の額は、
たとえ固定資産の取得に関連して
支出するものであっても、
これを固定資産の取得価額に
算入しないことができる。
(昭50年直法2−21「19」により追加、
昭55年直法2−8「二十一」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち
土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は
登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、
測量、設計、基礎工事等で
その建設計画を変更したことにより
不要となったものに係る費用の額
(3) いったん締結した固定資産の
取得に関する契約を解除して
他の固定資産を取得することとした場合に
支出する違約金の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月12日
購入した資産の取得価額は?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
資産の中でも減価償却資産は
取得価額がいくらになるか
によって会社の損益は大きく
変動します。
どういうことかというと、
この損益を大きく変動させる原因、
それは、付随費用が発生した場合です。
減価償却資産の取得価額は、
以下のように定められています。
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から
第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)
に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二
(定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した
費用がある場合には、
その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
つまり、これを間違うと
経費としていたものが否認され、
減価償却資産の取得価額として
減価償却を通じて、
費用化して行くようになります。
もう少し具体的に説明すると、
例えば中古の賃貸用のマンションを
購入した場合、
マンション本体・・・1億円
部屋を賃貸する為にした改装費・・・1,000万円
の場合、
マンション本体については
有無を言わさず取得価額となります。
ここで問題なのは、
部屋を賃貸する為にした改装費の1,000万円。
ここで重要となるのが、上記の
『当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額』
今回で考えると、
当該資産=マンション
事業の用に供するため=賃貸を開始するため
直接要した費用の額=1,000万円
となります。
もうお解かりですよね!!
今回の部屋を賃貸する為にした改装費は
当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額に該当するため、
支払った時の経費ではなく、
資産の取得価額を構成し、
減価償却を通じて、
各事業年度の費用となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

資産の中でも減価償却資産は
取得価額がいくらになるか
によって会社の損益は大きく
変動します。
どういうことかというと、
この損益を大きく変動させる原因、
それは、付随費用が発生した場合です。
減価償却資産の取得価額は、
以下のように定められています。
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から
第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)
に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二
(定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した
費用がある場合には、
その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
つまり、これを間違うと
経費としていたものが否認され、
減価償却資産の取得価額として
減価償却を通じて、
費用化して行くようになります。
もう少し具体的に説明すると、
例えば中古の賃貸用のマンションを
購入した場合、
マンション本体・・・1億円
部屋を賃貸する為にした改装費・・・1,000万円
の場合、
マンション本体については
有無を言わさず取得価額となります。
ここで問題なのは、
部屋を賃貸する為にした改装費の1,000万円。
ここで重要となるのが、上記の
『当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額』
今回で考えると、
当該資産=マンション
事業の用に供するため=賃貸を開始するため
直接要した費用の額=1,000万円
となります。
もうお解かりですよね!!
今回の部屋を賃貸する為にした改装費は
当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額に該当するため、
支払った時の経費ではなく、
資産の取得価額を構成し、
減価償却を通じて、
各事業年度の費用となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月11日
書画骨董を購入した場合の取扱は?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
応接室に飾る為などに
絵画や骨董などを購入した場合
どのような取扱になるのでしょう?
通常、資産を購入した場合には
減価償却を通じて経費としていきます。
それは、資産は通常使用することにより
また、時の経過に伴い価値が
減少していくものと認められるため、
購入時に一括して費用として計上するのではなく、
資産として計上し、減価償却により
各事業年度の経費としていきます。
ではここで問題が1つ。
名画と呼ばれるものや、
骨董的な価値のある壷など
これらは使用する事、
使用と言っても
こういった書画骨董は
飾っておくものなので
応接に飾ることにより
または、時の経過により
価値は減少するのでしょうか?
こういった骨董としての
価値のあるものは、
時の経過により価値は
増加はしても減少することは無い
と考えられます。
そこで、
古美術品、古文書、出土品、
遺物などのように歴史的価値又は
希少価値を有し、代替性の無いもの
又は、美術関係の年鑑等に登録されている
作者の製作にかかる書画、彫刻、
工芸品等は原則、書画骨董に該当し、
減価償却資産に該当しません。
したがって、書画骨董品は
資産計上したままという取扱となります。
**参考**
(減価償却資産の範囲)
法人税法施行令第十三条
法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
のうち次に掲げるもの
(事業の用に供していないもの及び
時の経過によりその価値の減少しないもの
を除く。)とする。
ただしこの場合、
その書画骨董が複製である場合
その絵画や絵画以外の美術品が
書画骨董に該当するか不明な場合で、
絵画については号当たりの取得価額が2万円未満
絵画以外の美術品等については
その取得価額が1点あたり20万円未満
である場合には、減価償却資産として
取り扱うことができます。
**参考**
(書画骨とう等)
法人税法基本通達7−1−1
書画骨とう(複製のようなもので、
単に装飾的目的にのみ使用されるもの
を除く。以下7−1−1において同じ。)
のように、時の経過により
その価値が減少しない資産は
減価償却資産に該当しないのであるが、
次に掲げるようなものは原則として
書画骨とうに該当する。
(昭55年直法2−8「十九」、
平元年直法2−7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等
のように歴史的価値又は希少価値を有し、
代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の
制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが
明らかでない美術品等でその取得価額が
1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満
であるものについては、減価償却資産として
取り扱うことができるものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

応接室に飾る為などに
絵画や骨董などを購入した場合
どのような取扱になるのでしょう?
通常、資産を購入した場合には
減価償却を通じて経費としていきます。
それは、資産は通常使用することにより
また、時の経過に伴い価値が
減少していくものと認められるため、
購入時に一括して費用として計上するのではなく、
資産として計上し、減価償却により
各事業年度の経費としていきます。
ではここで問題が1つ。
名画と呼ばれるものや、
骨董的な価値のある壷など
これらは使用する事、
使用と言っても
こういった書画骨董は
飾っておくものなので
応接に飾ることにより
または、時の経過により
価値は減少するのでしょうか?
こういった骨董としての
価値のあるものは、
時の経過により価値は
増加はしても減少することは無い
と考えられます。
そこで、
古美術品、古文書、出土品、
遺物などのように歴史的価値又は
希少価値を有し、代替性の無いもの
又は、美術関係の年鑑等に登録されている
作者の製作にかかる書画、彫刻、
工芸品等は原則、書画骨董に該当し、
減価償却資産に該当しません。
したがって、書画骨董品は
資産計上したままという取扱となります。
**参考**
(減価償却資産の範囲)
法人税法施行令第十三条
法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
のうち次に掲げるもの
(事業の用に供していないもの及び
時の経過によりその価値の減少しないもの
を除く。)とする。
ただしこの場合、
その書画骨董が複製である場合
その絵画や絵画以外の美術品が
書画骨董に該当するか不明な場合で、
絵画については号当たりの取得価額が2万円未満
絵画以外の美術品等については
その取得価額が1点あたり20万円未満
である場合には、減価償却資産として
取り扱うことができます。
**参考**
(書画骨とう等)
法人税法基本通達7−1−1
書画骨とう(複製のようなもので、
単に装飾的目的にのみ使用されるもの
を除く。以下7−1−1において同じ。)
のように、時の経過により
その価値が減少しない資産は
減価償却資産に該当しないのであるが、
次に掲げるようなものは原則として
書画骨とうに該当する。
(昭55年直法2−8「十九」、
平元年直法2−7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等
のように歴史的価値又は希少価値を有し、
代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の
制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが
明らかでない美術品等でその取得価額が
1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満
であるものについては、減価償却資産として
取り扱うことができるものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月08日
相続を放棄した人が貰った財産は贈与税?相続税?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
たとえば親から、健在中に現金の贈与を
受けたとします。
通常であれば、この贈与は、
その次の年の3月15日までに
贈与税の申告と納税を行います。
たとえばこの贈与があったのが、
平成23年の4月とします。
ところがこの贈与があった年の
平成23年の10月に、
その贈与をした親が亡くなった場合、
この4月に貰った現金は、
贈与税の申告が必要なのか?
それとも、
相続税の申告が必要なのか?
では次の2つのケースで説明します。
?贈与を受けた子供が相続も受ける場合
?贈与を受けた子供が相続を放棄する場合
?については、
子供が受けた贈与にかかる現金は、
相続財産として、
相続税の申告・納税を行います。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二4
相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始の年において当該相続に係る
被相続人から受けた贈与により取得した
財産の価額で第十九条の規定により
相続税の課税価格に加算されるものは、
前三項の規定にかかわらず、
贈与税の課税価格に算入しない。
続いて、?の場合ですが、
この場合は相続又は遺贈により財産を
取得しない為、上記相続税法第二十一条の二4
の規定の適用は無く、
贈与税の申告・納税が必要になります。
(ただし、暦年課税を受けている場合に限ります)
**参考**
(相続又は遺贈により財産を
取得しなかった者の贈与税の課税価格)
相続税法基本通達21の2−3
相続開始の年において、
当該相続に係る被相続人からの贈与により
財産を取得した者が当該被相続人からの
相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合の
贈与税の課税価格は、
法第21条の5から第21条の7までの規定
(以下「暦年課税」という。)の適用を受けるもの
又は相続時精算課税の適用を受けるものの
いずれであるかに応じて、
それぞれ次に掲げるとおりとなるのであるから留意する。
(平15課資2−1改正)
(1) 暦年課税
法第21条の2第4項の規定は適用されず、
当該贈与により取得した財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入される。
(2) 相続時精算課税
法第21条の10の規定により、
当該贈与により取得した財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入されるが、
法第28条第4項の規定により
贈与税の申告書の提出を要しない。
この場合、当該財産の価額について
贈与税の更正又は決定は行わないのであるから
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

たとえば親から、健在中に現金の贈与を
受けたとします。
通常であれば、この贈与は、
その次の年の3月15日までに
贈与税の申告と納税を行います。
たとえばこの贈与があったのが、
平成23年の4月とします。
ところがこの贈与があった年の
平成23年の10月に、
その贈与をした親が亡くなった場合、
この4月に貰った現金は、
贈与税の申告が必要なのか?
それとも、
相続税の申告が必要なのか?
では次の2つのケースで説明します。
?贈与を受けた子供が相続も受ける場合
?贈与を受けた子供が相続を放棄する場合
?については、
子供が受けた贈与にかかる現金は、
相続財産として、
相続税の申告・納税を行います。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二4
相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始の年において当該相続に係る
被相続人から受けた贈与により取得した
財産の価額で第十九条の規定により
相続税の課税価格に加算されるものは、
前三項の規定にかかわらず、
贈与税の課税価格に算入しない。
続いて、?の場合ですが、
この場合は相続又は遺贈により財産を
取得しない為、上記相続税法第二十一条の二4
の規定の適用は無く、
贈与税の申告・納税が必要になります。
(ただし、暦年課税を受けている場合に限ります)
**参考**
(相続又は遺贈により財産を
取得しなかった者の贈与税の課税価格)
相続税法基本通達21の2−3
相続開始の年において、
当該相続に係る被相続人からの贈与により
財産を取得した者が当該被相続人からの
相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合の
贈与税の課税価格は、
法第21条の5から第21条の7までの規定
(以下「暦年課税」という。)の適用を受けるもの
又は相続時精算課税の適用を受けるものの
いずれであるかに応じて、
それぞれ次に掲げるとおりとなるのであるから留意する。
(平15課資2−1改正)
(1) 暦年課税
法第21条の2第4項の規定は適用されず、
当該贈与により取得した財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入される。
(2) 相続時精算課税
法第21条の10の規定により、
当該贈与により取得した財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入されるが、
法第28条第4項の規定により
贈与税の申告書の提出を要しない。
この場合、当該財産の価額について
贈与税の更正又は決定は行わないのであるから
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月07日
ホームページの製作費用の取扱は・・・?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今や会社経営に欠かせないホームページ。
名刺交換をして、名刺にHPのURLの
記載がないと、なんだか不安になる
という方も多いと思います。
会社=HPを持っていて当たり前
そんな時代ですね!
そして何と言ってもHPは、
24時間365日フル稼働で
営業をしてくれるとっても優秀な
営業マン(ウーマンかもしれませんが・・・)。
そんなHPを持たない手はないですよね。
ただそこで気になるのはHPの製作費用。
業者に頼むと何十万、何百万といった
費用がかかることも珍しくありません。
そこで問題となるのが、
HPの製作費用を一括で経費として計上
できるのか否か。
実はHPの製作費用は、
一括で経費として計上できる部分と
資産として計上し、5年間で
随時経費となる部分とがあるんです。
例えばHPを広告宣伝のみで活用する場合、
HPのデザインなどは1年以内のサイクルで
更新が必要となります。
こういった、短い期間において更新が必要
となるようなデザイン料については、
一括で経費として計上することができます。
反対に、HPにデータベースやネットワークと
アクセスする為のプログラムを作成し
組み込む場合があります。
こういった場合、そのプログラムの
製作費用は、一括で経費とならず、
5年間に渡って随時経費として計上
することとなります。
この取扱を間違えると
大きな金額の否認をくらうこととなります、
HPの製作費用の明細をよく確認して
処理を行ってくださいね!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

今や会社経営に欠かせないホームページ。
名刺交換をして、名刺にHPのURLの
記載がないと、なんだか不安になる
という方も多いと思います。
会社=HPを持っていて当たり前
そんな時代ですね!
そして何と言ってもHPは、
24時間365日フル稼働で
営業をしてくれるとっても優秀な
営業マン(ウーマンかもしれませんが・・・)。
そんなHPを持たない手はないですよね。
ただそこで気になるのはHPの製作費用。
業者に頼むと何十万、何百万といった
費用がかかることも珍しくありません。
そこで問題となるのが、
HPの製作費用を一括で経費として計上
できるのか否か。
実はHPの製作費用は、
一括で経費として計上できる部分と
資産として計上し、5年間で
随時経費となる部分とがあるんです。
例えばHPを広告宣伝のみで活用する場合、
HPのデザインなどは1年以内のサイクルで
更新が必要となります。
こういった、短い期間において更新が必要
となるようなデザイン料については、
一括で経費として計上することができます。
反対に、HPにデータベースやネットワークと
アクセスする為のプログラムを作成し
組み込む場合があります。
こういった場合、そのプログラムの
製作費用は、一括で経費とならず、
5年間に渡って随時経費として計上
することとなります。
この取扱を間違えると
大きな金額の否認をくらうこととなります、
HPの製作費用の明細をよく確認して
処理を行ってくださいね!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月06日
保証債務を履行するために資産を売却した場合消費税は?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
知り合いの銀行借入について
保証人となった場合、
もしその知り合いの方が
返済できなくなると
保証人は一旦肩代わりして
銀行に借金の返済を
行わなければなりません。
ではもし保証債務の履行を
行う場合、手許にお金が無く
例えば自社工場や
所有する機械、土地などを
売却し、お金を用立てて
保証債務の履行を行った場合、
この資産の売却に消費税は
かかるのでしょうか?
実は消費税法上、
資産の譲渡について
その原因を問いません。
原因を問わないと言うことは
たとえそれが商売上の譲渡であっても、
借金の返済の為の譲渡であっても
区分することなく消費税が
課税されてしまいます。
そのため保証債務を履行するために
資産を売却するときは、
消費税も計画に入れておかなければ
ならないことを注意してください。
**参考**
(定義)
消費税法第二条八
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
貸付け又は役務の提供に類する行為
として政令で定めるものを含む。)をいう。
(保証債務等を履行するために行う資産の譲渡)
消費税法基本通達5−2−2
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》
に規定する事業として対価を得て行われる
資産の譲渡は、その原因を問わないのであるから、
例えば、他の者の債務の保証を履行するために行う
資産の譲渡又は強制換価手続により換価された場合
の資産の譲渡は、同号に規定する事業として
対価を得て行われる資産の譲渡に
該当することに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

知り合いの銀行借入について
保証人となった場合、
もしその知り合いの方が
返済できなくなると
保証人は一旦肩代わりして
銀行に借金の返済を
行わなければなりません。
ではもし保証債務の履行を
行う場合、手許にお金が無く
例えば自社工場や
所有する機械、土地などを
売却し、お金を用立てて
保証債務の履行を行った場合、
この資産の売却に消費税は
かかるのでしょうか?
実は消費税法上、
資産の譲渡について
その原因を問いません。
原因を問わないと言うことは
たとえそれが商売上の譲渡であっても、
借金の返済の為の譲渡であっても
区分することなく消費税が
課税されてしまいます。
そのため保証債務を履行するために
資産を売却するときは、
消費税も計画に入れておかなければ
ならないことを注意してください。
**参考**
(定義)
消費税法第二条八
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
貸付け又は役務の提供に類する行為
として政令で定めるものを含む。)をいう。
(保証債務等を履行するために行う資産の譲渡)
消費税法基本通達5−2−2
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》
に規定する事業として対価を得て行われる
資産の譲渡は、その原因を問わないのであるから、
例えば、他の者の債務の保証を履行するために行う
資産の譲渡又は強制換価手続により換価された場合
の資産の譲渡は、同号に規定する事業として
対価を得て行われる資産の譲渡に
該当することに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月05日
親から財産を安く購入した場合の注意点
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
親から子供へ別荘を譲る場合、
ただで渡してしまうと贈与税が
かかってしまうということで、
親から時価5,000万円の別荘を
1,000万円で購入した場合、
税務上どういう取扱になるのか?
実は、著しく低い対価で
財産を譲り受けた場合にも、
実質的には贈与を受けたものとして
贈与税が課税されてしまいます。
つまり、財産を著しく低い対価で
譲り受けたときに、
その対価と財産の時価との差額に
相当する金額を、
その財産を譲り渡した人から
贈与により取得したものとして
贈与税が課税されます。
今回の例で行くと、
5,000万円−1,000万円=4,000万円
となり、4,000万円の贈与があったものとして
贈与税が課税されてしまいます。
**参考**
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
相続税法第七条
著しく低い価額の対価で
財産の譲渡を受けた場合においては、
当該財産の譲渡があつた時において、
当該財産の譲渡を受けた者が、
当該対価と当該譲渡があつた時における
当該財産の時価(当該財産の評価について
第三章に特別の定めがある場合には、
その規定により評価した価額)
との差額に相当する金額を
当該財産を譲渡した者から贈与
(当該財産の譲渡が遺言により
なされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該財産の譲渡が、
その譲渡を受ける者が資力を喪失して
債務を弁済することが困難である場合において、
その者の扶養義務者から
当該債務の弁済に充てるために
なされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により取得したものと
みなされた金額のうち
その債務を弁済することが困難である
部分の金額については、この限りでない。
(負担付贈与又は対価を伴う取引により
取得した土地等及び家屋等に係る評価
並びに相続税法第7条及び第9条の
規定の適用について)
負贈通1
土地及び土地の上に存する権利
(以下「土地等」という。)並びに家屋
及びその附属設備又は構築物
(以下「家屋等」という。)のうち、
負担付贈与又は個人間の対価を伴う
取引により取得したものの価額は、
当該取得時における通常の取引価額に
相当する金額によって評価する。
ただし、贈与者又は譲渡者が
取得又は新築した当該土地等又は
当該家屋等に係る取得価額が
当該課税時期における
通常の取引価額に相当すると
認められる場合には、
当該取得価額に相当する金額によって
評価することができる。
(注)「取得価額」とは、当該財産の
取得に要した金額並びに改良費
及び設備費の額の合計額をいい、
家屋等については、
当該合計金額から、
評価基本通達130((償却費の額等の計算))
の定めによって計算した
当該取得の時から課税時期までの期間の
償却費の額の合計額又は
減価の額を控除した金額をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

親から子供へ別荘を譲る場合、
ただで渡してしまうと贈与税が
かかってしまうということで、
親から時価5,000万円の別荘を
1,000万円で購入した場合、
税務上どういう取扱になるのか?
実は、著しく低い対価で
財産を譲り受けた場合にも、
実質的には贈与を受けたものとして
贈与税が課税されてしまいます。
つまり、財産を著しく低い対価で
譲り受けたときに、
その対価と財産の時価との差額に
相当する金額を、
その財産を譲り渡した人から
贈与により取得したものとして
贈与税が課税されます。
今回の例で行くと、
5,000万円−1,000万円=4,000万円
となり、4,000万円の贈与があったものとして
贈与税が課税されてしまいます。
**参考**
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
相続税法第七条
著しく低い価額の対価で
財産の譲渡を受けた場合においては、
当該財産の譲渡があつた時において、
当該財産の譲渡を受けた者が、
当該対価と当該譲渡があつた時における
当該財産の時価(当該財産の評価について
第三章に特別の定めがある場合には、
その規定により評価した価額)
との差額に相当する金額を
当該財産を譲渡した者から贈与
(当該財産の譲渡が遺言により
なされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該財産の譲渡が、
その譲渡を受ける者が資力を喪失して
債務を弁済することが困難である場合において、
その者の扶養義務者から
当該債務の弁済に充てるために
なされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により取得したものと
みなされた金額のうち
その債務を弁済することが困難である
部分の金額については、この限りでない。
(負担付贈与又は対価を伴う取引により
取得した土地等及び家屋等に係る評価
並びに相続税法第7条及び第9条の
規定の適用について)
負贈通1
土地及び土地の上に存する権利
(以下「土地等」という。)並びに家屋
及びその附属設備又は構築物
(以下「家屋等」という。)のうち、
負担付贈与又は個人間の対価を伴う
取引により取得したものの価額は、
当該取得時における通常の取引価額に
相当する金額によって評価する。
ただし、贈与者又は譲渡者が
取得又は新築した当該土地等又は
当該家屋等に係る取得価額が
当該課税時期における
通常の取引価額に相当すると
認められる場合には、
当該取得価額に相当する金額によって
評価することができる。
(注)「取得価額」とは、当該財産の
取得に要した金額並びに改良費
及び設備費の額の合計額をいい、
家屋等については、
当該合計金額から、
評価基本通達130((償却費の額等の計算))
の定めによって計算した
当該取得の時から課税時期までの期間の
償却費の額の合計額又は
減価の額を控除した金額をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月04日
消費税は利益にかかるのではないので注意です!
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
3月が決算日で今決算作業を行っている
と言う会社さんも多いと思います。
原則的には、3月末日から2月以内に
申告と納税を完了させなければなりません。
そこで気になるのが、いくらの税金を
支払う必要があるのか?
ということ。
中には月次決算もしておらず
半年とか1年とかまとめて
帳簿作成を行い、決算作業をしている
と言う会社さんもあると思います。
毎月月次決算を行っていれば、
だいたいどの程度の税金が必要か
把握できますが、
そうでなければ経営者さんの
感により、黒字か?赤字か?
を判断していると思います。
法人税であれば、利益が出ない限り
税金はかかりません。
しかし消費税はそうではありません。
たとえ赤字でも消費税を支払わなければ
ならなくなります。
なぜこういった事がおきるのか?
それは・・・
例)
売上高 100,000,000円(税抜き)
消費税 5,000,000円
原価 50,000,000円(税抜き)
消費税 2,500,000円
人件費 25,000,000円
その他経費 30,000,000円(税抜き)
消費税 1,500,000円
経常利益 △5,000,000円
この会社さん、500万円の赤字です。
赤字と言うことは、法人税の支払は
発生しません。
では消費税はどうでしょう??
まず、預った消費税は、5,000,000円
そして支払った消費税は、
2,500,000円(原価分)+1,500,000円(経費分)
=4,000,000円
となります。
その差額は、
5,000,000円−4,000,000円=1,000,000円
となり、
1,000,000円の納税となります。
赤字であれば、お金が無い場合が
ほとんどです。
そのような状態で、
1,000,000円もの消費税を
納めることが出来るでしょうか?
きっと厳しいと思います。
では何故このようなことが起こるのか?
それは、経費の中には消費税の
かからないものが存在するためです。
その代表的なものとしては、
ここでも掲げた人件費。
給与には消費税はかかりません。
他に消費税のかからない代表的な
経費を掲げておきます。
こういった経費が多くあり
赤字となっている場合には
注意してくださいね!
**参考**
基本的に消費税が非課税となるものの
代表的な項目
・土地の売買
・土地の貸付
・有価証券の売買
・両替
・税金
・保険料
・居住用住宅の賃貸 etc
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

3月が決算日で今決算作業を行っている
と言う会社さんも多いと思います。
原則的には、3月末日から2月以内に
申告と納税を完了させなければなりません。
そこで気になるのが、いくらの税金を
支払う必要があるのか?
ということ。
中には月次決算もしておらず
半年とか1年とかまとめて
帳簿作成を行い、決算作業をしている
と言う会社さんもあると思います。
毎月月次決算を行っていれば、
だいたいどの程度の税金が必要か
把握できますが、
そうでなければ経営者さんの
感により、黒字か?赤字か?
を判断していると思います。
法人税であれば、利益が出ない限り
税金はかかりません。
しかし消費税はそうではありません。
たとえ赤字でも消費税を支払わなければ
ならなくなります。
なぜこういった事がおきるのか?
それは・・・
例)
売上高 100,000,000円(税抜き)
消費税 5,000,000円
原価 50,000,000円(税抜き)
消費税 2,500,000円
人件費 25,000,000円
その他経費 30,000,000円(税抜き)
消費税 1,500,000円
経常利益 △5,000,000円
この会社さん、500万円の赤字です。
赤字と言うことは、法人税の支払は
発生しません。
では消費税はどうでしょう??
まず、預った消費税は、5,000,000円
そして支払った消費税は、
2,500,000円(原価分)+1,500,000円(経費分)
=4,000,000円
となります。
その差額は、
5,000,000円−4,000,000円=1,000,000円
となり、
1,000,000円の納税となります。
赤字であれば、お金が無い場合が
ほとんどです。
そのような状態で、
1,000,000円もの消費税を
納めることが出来るでしょうか?
きっと厳しいと思います。
では何故このようなことが起こるのか?
それは、経費の中には消費税の
かからないものが存在するためです。
その代表的なものとしては、
ここでも掲げた人件費。
給与には消費税はかかりません。
他に消費税のかからない代表的な
経費を掲げておきます。
こういった経費が多くあり
赤字となっている場合には
注意してくださいね!
**参考**
基本的に消費税が非課税となるものの
代表的な項目
・土地の売買
・土地の貸付
・有価証券の売買
・両替
・税金
・保険料
・居住用住宅の賃貸 etc
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年04月01日
安易な値引きはいけません!!
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
ここ数日、売上の簡易シミュレーションツールを
作成していました。
今日で大筋は完成し、マニュアルの作成も
ほぼ完成しました。
あとは不具合などを調べて
完成すれば、また皆さんに
配布したいと思います。
さて、今回その
簡易シミュレーションツールを
作成する上で一番伝えたかった
内容を盛り込みました。
それは、
安易な値引きはしてはダメ
ということと、
何故ダメなのかが
数字で分かるようにしました。
どういうことかというと、
例えば
販売単価 1,500円
仕入単価 1,000円
販売数量 500個
粗利益 250,000円
の会社があったとします。
では問題!
もしこの会社が
販売価格を10%値引きすると、
値引きする前の粗利を稼ぐ為には
何個商品を販売しないといけないでしょうか?
販売価格を10%値引きしたから
販売数を10%増やせばOK
だと思いますか?
では実際に計算して見ましょう。
販売単価 1,500円−1,500円×10%=1,350円
仕入単価 1,000円
粗利益 250,000円
販売数量 250,000円/(1,350円−1,000円)=714個
(端数切捨て)
販売数増加率 714個/500個=42.8%
つまり、10%の値引きをすることにより
42.8%増(714個−500個)214個販売数を伸ばして
やっと元通りです。
安易に値引きは恐くないですか??
この計算が簡単に出来るように
していますので、完成まで
しばらくお待ち下さいね!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!
*********************************************
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

ここ数日、売上の簡易シミュレーションツールを
作成していました。
今日で大筋は完成し、マニュアルの作成も
ほぼ完成しました。
あとは不具合などを調べて
完成すれば、また皆さんに
配布したいと思います。
さて、今回その
簡易シミュレーションツールを
作成する上で一番伝えたかった
内容を盛り込みました。
それは、
安易な値引きはしてはダメ
ということと、
何故ダメなのかが
数字で分かるようにしました。
どういうことかというと、
例えば
販売単価 1,500円
仕入単価 1,000円
販売数量 500個
粗利益 250,000円
の会社があったとします。
では問題!
もしこの会社が
販売価格を10%値引きすると、
値引きする前の粗利を稼ぐ為には
何個商品を販売しないといけないでしょうか?
販売価格を10%値引きしたから
販売数を10%増やせばOK
だと思いますか?
では実際に計算して見ましょう。
販売単価 1,500円−1,500円×10%=1,350円
仕入単価 1,000円
粗利益 250,000円
販売数量 250,000円/(1,350円−1,000円)=714個
(端数切捨て)
販売数増加率 714個/500個=42.8%
つまり、10%の値引きをすることにより
42.8%増(714個−500個)214個販売数を伸ばして
やっと元通りです。
安易に値引きは恐くないですか??
この計算が簡単に出来るように
していますので、完成まで
しばらくお待ち下さいね!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました




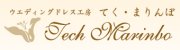


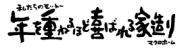




 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン





